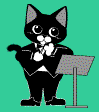ヤンソンスの1989年来日公演ライブCDを聴く (注 / ほとんど内容に触れていません) [クラシック百銘盤]

1989年にレニングラードフィルが来日した時のマリス・ヤンソンスが指揮した日のCDが昨秋発売されたけど、それを聴いての感想
山崎浩太郎氏が解説でいろいろ書かれているので、そことはなるべく重複しない話を中心にします。
この公演はレニングラードフィルの2年ぶり8度目の来日公演で、このオケが秋に日本に来るのは前回1986年以来2年ぶり三度目のこと。
ゴルバチョフ政権誕生後の1986年、春にモスクワ放送響がフェドセーエフ指揮で11年ぶり三度目の来日、夏にはソビエト文化省響がロジェストヴェンスキー指揮で初来日、そして秋にレニングラードフィルの来日と続くことになって以来、ソ連の来日オケは再び活況を呈しはじめます。
だがこの時のレニングラードフィルは今までと違っていました。
前年にこのオケにとって絶対的存在だったムラヴィンスキーが他界し、ユーリ・テミルカーノフがそのトップに就いたからです。
そんな中で行われた今回のこのコンサート。
ではそのツアー内容を記します。
レニングラード・フィルハーモニー・アカデミー
(指揮者:ユーリ・テミルカーノフ、マリス・ヤンソンス)
9月28日:群馬県民会館/ヤンソンス
リムスキー・コルサコフ/シェエラザード
ベートーヴェン/交響曲第7番
9月29日:千葉県民文化会館/ヤンソンス
リムスキー・コルサコフ/シェエラザード
ベートーヴェン/交響曲第7番
10月1日:神奈川県民ホール/ヤンソンス
リムスキー・コルサコフ/シェエラザード
リスト:ピアノ協奏曲第1番(P/ワレリー・クレショフ)
チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ
10月2日:聖徳学園川並記念講堂/ヤンソンス
リムスキー・コルサコフ/シェエラザード
レスピーギ/ローマの松
10月4日:名古屋市民会館/ヤンソンス
ワーグナー/マイスタージンガー、第一幕への前奏曲
リスト/ピアノ協奏曲第1番(P/ワレリー・クレショフ)
ベルリオーズ/幻想交響曲
10月5日:長野県民文化センター/ヤンソンス
ベートーヴェン/交響曲第7番
リスト:ピアノ協奏曲第1番(P/ワレリー・クレショフ)
チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ
10月6日:金沢観光会館/ヤンソンス
リムスキー・コルサコフ/シェエラザード
べートーヴェン/交響曲第7番
10月7日:富山市公会堂/ヤンソンス
ワーグナー/マイスタージンガー、第一幕への前奏曲
リスト/ピアノ協奏曲第1番(P/ワレリー・クレショフ)
ベルリオーズ/幻想交響曲
10月9日:神奈川県民ホール/テミルカーノフ
ショスタコーヴィチ/祝典序曲
ムソルグスキー/展覧会の絵
チャイコフスキー/くるみわり人形、第二幕全曲
10月10日:オーチャードホール/テミルカーノフ
ショスタコーヴィチ/祝典序曲
ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第1番(P/ワレリー・クレショフ)
マーラー/交響曲第1番
10月11日:オーチャードホール/テミルカーノフ
ショスタコーヴィチ/祝典序曲
ムソルグスキー/展覧会の絵
チャイコフスキー/くるみわり人形、第二幕全曲
10月13日:福岡サンパレス/テミルカーノフ
ショスタコーヴィチ/祝典序曲
ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第1番(P/ワレリー・クレショフ)
チャイコフスキー/くるみわり人形、第二幕全曲
10月14日:佐賀文化会館/テミルカーノフ
ショスタコーヴィチ/祝典序曲
モーツァルト/ピアノ協奏曲第23番(P/ワレリー・クレショフ)
ムソルグスキー/展覧会の絵
10月15日:熊本市民会館/テミルカーノフ
ショスタコーヴィチ/祝典序曲
ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第1番(P/ワレリー・クレショフ)
マーラー/交響曲第1番
10月16日:鹿児島文化センター/テミルカーノフ
ショスタコーヴィチ/祝典序曲
モーツァルト/ピアノ協奏曲第23番(P/ワレリー・クレショフ)
チャイコフスキー/くるみわり人形、第二幕全曲
10月18日:下関市民会館/テミルカーノフ
ショスタコーヴィチ/祝典序曲
ムソルグスキー/展覧会の絵
プロコフィエフ/交響曲第5番
10月19日:姫路文化センター/ヤンソンス
ワーグナー/マイスタージンガー、第一幕への前奏曲
リスト/ピアノ協奏曲第1番(P/ワレリー・クレショフ)
ベルリオーズ/幻想交響曲
10月20日:フェスティバルホール/ヤンソンス
ベートーヴェン/交響曲第7番
チャイコフスキー/ロココ風の主題による変奏曲(VC/アレクサンドル・ルッディン)
チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ
10月21日:フェスティバルホール/ヤンソンス
ベートーヴェン/交響曲第7番
チャイコフスキー/ロココ風の主題による変奏曲(VC/アレクサンドル・ルッディン)
チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ
10月22日:シンフォニーホール/ヤンソンス
リムスキー・コルサコフ/シェエラザード
リスト:ピアノ協奏曲第1番(P/ワレリー・クレショフ)
レスピーギ/ローマの松
10月24日:柏市民文化会館/ヤンソンス
リムスキー・コルサコフ/シェエラザード
チャイコフスキー/ロココ風の主題による変奏曲(VC/アレクサンドル・ルッディン)
チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ
10月25日:オーチャードホール/ヤンソンス
ワーグナー/マイスタージンガー、第一幕への前奏曲
リスト/ピアノ協奏曲第1番(P/ワレリー・クレショフ)
ベルリオーズ/幻想交響曲
10月26日:オーチャードホール/ヤンソンス
ベートーヴェン/交響曲第7番
チャイコフスキー/ロココの主題による変奏曲(VC/アレクサンドル・ルッディン)
レスピーギ/ローマの松
というもの。
今回のCDはこの公演の最後から二日目のものだが、この公演じつはテミルカーノフとヤンソンスが交互に指揮したというものではない。
つまり
9/28~10/7迄がヤンソンス
10/9~10/18迄がテミルカーノフ
10/19~10/26迄がヤンソンス
と、今までのこのオケには無い、ひじように変則的ともいえる担当となっている。
自分はこのうち10/1と10/26のヤンソンス、そして10/10のテミルカーノフに聴きに行っている。
じつはこの時の演奏会は正直あまり思い出したくないというのが本音。
というのも、この時のレニングラードフィルは、自分が聴いた限り来日公演でいちばん最悪最低の状態。
とにかくオケに覇気がない。音は汚い。ただ音がデカいだけでバランスは最悪という、86年に聴いてからたった3年でこうも悲惨な崩壊をオケは遂げてしまうのかと、聴いてて呆然とした程だった。
1日のシェエラザードなどほとんどやっただけの無表情な音楽、協奏曲で若干持ち直し、最後のチャイコフスキーはムラヴィンスキーの十八番なだけに、前半はかつての響きを取り戻し、「おおっ」と思わせたが、中盤以降はガス欠でもしたのか急速に緊張感が失せていった。
だが大問題だったのは10日の公演。冒頭のショスタコーヴィチはオケが勝手に突っ走って終わりという、確かに迫力はあったがとてつもなく雑な出来、協奏曲はすべてに渡り平板低調、そして最後のマーラーもオケが散漫で、第二楽章など一瞬オケが崩壊するのではないかというくらいバラバラになって唖然とさせられた。
第四楽章でかなり大きな地震に見舞われたものの、音楽が止まらなかったのが救いというくらいだった。
正直指揮者とオケにまったく意思の疎通がない。こんな事も珍しいが、演奏中に弦楽器の一部がやたら椅子を動かし位置を少しではあるが変えている事が何度となく、しかも複数人がやっていたが、そのガタゴトという音がこれまた気になってしかたなかった。とにかくこれなどは今迄見た事もない光景だった。
また別の日の指揮者がヤンソンスの時、指揮者の登場より遅れて奏者が慌てて舞台に上がってくるという、これまたこのオケではかつてみられない光景もあったという。
もう緊張感も集中力もない、完全に糸の切れた凧というかんじになっていた。
その後、テミルカーノフが打ち出した全面的なムラヴィンスキー否定が、オケの多くの団員から猛反発をくい、フィルハーモニーの事務方の一部でも反発が起きていたという話を聞く。またそれと同時に真偽不明のテミルカーノフに対する噂も飛び交ったらしく、とにかく最悪の状況での日本公演で、ヤンソンスをもってしてもそれは如何ともしがたい状況だったという事を知った。
ムラヴィンスキー未亡人の同オケ首席のフルート、アレクサンドラ女史が問答無用で即解雇されたことも大きかったらしいが、とにかく「このオケはもう10年は聴く必要無し」と思わせるほど10日の公演は最悪だった。
ただ最終日は前半のベートーヴェンは低調だったが、ロココあたりからオケに気合が入り、「ローマの松」では、舞台近くの一階席右側壁際に陣取っていたバンダが最後立ち上がってのそれも加わってのじつに輝かしい演奏となったが、それはこのオケの将来にようやく光が差したような感すらするほどで、そんな素晴らしい演奏で終わったのが本当に幸いだった。
あと最悪だった10日の公演。最悪の上をいく最悪にならなかったのは、アンコールで演奏されたチャイコフスキーの「くるみ割り人形」から「パ・ド・ドゥ」。これがムラヴィンスキーの十八番だったこともあってか、指揮者そっちのけで、ムラヴィンスキーの音が突然成りだしたこと。
それこそムラヴィンスキーが日本のファンに最後の別れを言いに突然オケに乗り移ったかのようなそれは名演だった。
だが謎なのは、そうなることを分かっていたのに、テミルカーノフがなぜこの曲を指揮したのだろうかということ。それだけが未だに自分の心の中でこの演奏はひじょうに引っ掛かっている。
(因みにこの時はまだニムロッドはアンコールとして演奏していませんでした)
レニングラードフィルはその後都市名の変更とともに名前を変え、そしてこの公演以降10年程かけ、じつに楽団員の七割程が入れ替わり、テミルカーノフのオケへと変貌していく。
それはレニングラードフィル=ムラヴィンスキーであるように、サンクトペテルブルクフィル=テミルカーノフとなった証でもありました。
そんなことを思いながらこのCDを聴く。
さてこのCD。
残念ながら自分はこの日の公演には行ってないし、この公演を上記の理由から今以上に避けていた部分があるので、その放送も当時耳にしていないが、聴いてみて思った事に、このCDと同時発売された1986年の同オケのライブ同様、テープが劣化しているのかな?とちょっと思ってしまった。
オケがなんか気持ち遠いというか、そのせいかこんなに柔らかかったかなあ?というのが印象としてすぐに来たし、音全体は綺麗にとれているけど、やや綺麗すぎて聴きやすい反面、生々しさが後退したように感じられた。
ただ今回はそのおかけで、あの雑然とした感覚がかなりオブラートに包まれたような感じになったため、あの時のような粗さが目立たないのは幸いだった。
そして1986年盤と同様に、次にヘッドホーンを外してスピーカーにして聴いてみた。
そしたらこれまた聴いたら「おお、凄い」という音が出てきた。
ひょっとしたらこのCDも、そういうことよりも聴く装置や環境によってかなり変わるのかなあという感じがして、今は専ら安物のスピーカーで聴いている。
で、演奏は直線的といっていいくらい、真正直かつ正攻法ともいえる演奏だけど、シベリウスなどはそれだけにとどまらないなかなかの味わい深いものがありました。
もっともヤンソンスは、前年当時音楽監督をしていたオスロフィルとの初来日公演でも、やはりアンコールでこの曲を見事な演奏を聴かせているので、本当に十八番中の十八番だったのでしょう。
あと幻想は、1979年に彼の父アルヴィドが同じレニングラードフィルを指揮した同曲とどことなく似た感じを持ちました。
ただ父の方が弓を弦にベッタリつけたような、分厚く粘り気のある、より暗く重心が低く巨大な演奏ではありましたが。
と、聴いていてこれくらいの印象しか今はありません。
最後に。
当時、レニングラードフィルはテミルカーノフではなく、ヤンソンスがそのトップに就くだろうと誰もが予想していただけにテミルカーノフがなった時は、その人選に誰もが驚きましたが、後に「ヤンソンスがなれなかったのは、彼がロシア人ではないからだ」という話を聞かされた時、驚くと同時にいくつかの疑問も氷解しました。
ロジェストヴェンスキー離任後のモスクワ放送響、キタエンコ離任後のモスクワフィルで、後任に彼が噂されたものの結局別の指揮者が後任になった事などがそれでした。
ただそれもはたしてどこまで事実なのかは正直不明ではあります。
もっともソ連でのポストに恵まれなかったものの、オスロで評価を次第に上げ、さらにピッツバーグでステップアップした彼は、2000年にあったベルリンフィル公演で、アバドとともに来日するほどにその評価はさらに高まり、その後コンセルトヘボウとバイエルン放送という二大オケとともに大輪の花を咲かせたことは、結果的に彼の歩んだ道がじつは彼にとって最高の道のりだったということなのかもしれません。
これはそんな道のりを歩みだす前のヤンソンスの記録という意味では貴重な資料ともいえる録音かもしれません。
以上で〆
追伸
上で10日の公演をボロクソ言いましだか、じつは今もし録音が残っていたら聴いてみたいもののひとつがその公演。
今聴くとはたしてどうなのか。じつは全然そんなことなかったのか、それともやはりあれだったのか。
最近特に気になっています。
本〆
※このブログにおけるムラヴィンスキー関連の項目
https://orch.blog.ss-blog.jp/archive/c2305360029-1
ヤンソンスの1986年来日公演ライブCDを聴く [クラシック百銘盤]

1986年にマリス・ヤンソンスがレニングラードフィルと来日した時のCDが昨秋発売されたけど、それを聴いての感想
山崎浩太郎氏が解説でいろいろ書かれているので、そことはなるべく重複しない話を中心にします。
この公演はレニングラードフィルの7年ぶり7度目の来日公演で、このオケが秋に日本に来るのは1977年以来9年ぶり二度目のこと。
1970年以降、73、75、77、79、と、1970~1980年当時の海外のオーケストラとしては最も来日頻度が高く、特にムラヴィンスキーは二年ごとに四度も来日していた。
これは極めて異例で、それはムラヴィンスキー自身が初来日時に大の親日家になったことが要因としてあったらしい。
だが1979年の来日公演最終日前日にNHKのニュースでも流れた二人の楽団員の亡命、さらに翌年開催のモスクワ五輪の日本のボイコット、そして亡命事件でのムラヴィンスキーと当局の売り言葉に買い言葉ともいえるやりとりが致命傷となり、当局とは良好ではなかっただけでなく、自身も共産党員でなかったこともあり、1981年の来日直前に公演が事実上潰されるという事態に発展、それが元で、ミュンヘンバッハが来日直前にリヒターが死去したことで、大きな損害をこうむっていた新術家協会が止めを刺され倒産する事態に発展した。
これ以降ソ連からは1983年にスヴェトラーノフとヴェルビツキーの指揮によるソビエト国立響が来日した以外は、まったく来日が途絶えてしまった。
結局、ゴルバチョフ政権誕生後の1986年、それによりまるで堰を切ったかのように、春にモスクワ放送響がフェドセーエフ指揮で11年ぶり三度目の来日、夏にはソビエト文化省響がロジェストヴェンスキー指揮で初来日、そして秋にレニングラードフィルの来日と続くことになった。
この1986、はじつは1977年に匹敵する来日オケの当たり年で、上記三団体以外にも小澤指揮ボストン響、マゼール指揮ウィーンフィル、ショルティ指揮シカゴ響、クライバー指揮バイエルン国立菅、ヨッフムとアシュケナージ指揮のコンセルトヘボウ、チェリビダッケ指揮ミュンヘンフィル、スラットキン指揮セントルイス響、そしてカラヤンの代役として指揮に立った小澤征爾指揮ベルリンフィル等々、秋のサントリーホール杮落しもあいまって、質量ともに大盛況な年となった。
そんな中で行われた今回のこのコンサート。残念ながらムラヴィンスキーは体調不良の為来日できず、ヤンソンスとカヒッゼによる体制でのツアーとなった。
ではそのツアー内容を記します。
レニングラード・フィルハーモニー・アカデミー
(指揮者:マリス・ヤンソンス、ジャンスィク・カヒッゼ)
9月25日:昭和女子大人見記念講堂/ヤンソンス
[ショスタコーヴィチ生誕80周年記念演奏会]
ショスタコーヴィチ/交響曲第6番
チャイコフスキー/交響曲第5番
↓
※当初は指揮ムラヴィンスキー
チャイコフスキー/交響曲第5番
ショスタコーヴィチ/交響曲第6番
9月26日:甲府県民文化センター/ヤンソンス
グリンカ/幻想的円舞曲
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
9月28日:神奈川県民ホール/ヤンソンス
チャイコフスキー/ロミオとジュリエット
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
チャイコフスキー/交響曲第6番
9月29日:京都会館/ヤンソンス
ベルリオーズ/ローマの謝肉祭
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
チャイコフスキー/交響曲第6番
10月1日:シンフォニーホール/ヤンソンス
ショスタコーヴィチ/交響曲第6番
チャイコフスキー/交響曲第5番
↓
※当初は指揮ムラヴィンスキー
チャイコフスキー/交響曲第5番
ショスタコーヴィチ/交響曲第6番
10月3日:宮崎市民会館/ヤンソンス
グリンカ/幻想的円舞曲
ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
10月4日:都城市民会館/ヤンソンス
ベルリオーズ/ローマの謝肉祭
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
チャイコフスキー/交響曲第6番
10月5日:延岡総合文化センター/ヤンソンス
グリンカ/幻想的円舞曲
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
チャイコフスキー/交響曲第6番
10月8日:徳島文化センター/ヤンソンス
ベルリオーズ/ローマの謝肉祭
ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
10月9日:倉敷市民会館/ヤンソンス
ベルリオーズ/ローマの謝肉祭
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
チャイコフスキー/交響曲第6番
10月11日:市川文化会館/ヤンソンス
ベルリオーズ/ローマの謝肉祭
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
チャイコフスキー/交響曲第5番
10月12日:ノバホール/ヤンソンス
グリンカ/幻想的円舞曲
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
10月14日:宮城県民会館/ヤンソンス
チャイコフスキー/ロミオとジュリエット
チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲(VN/石川静)
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
10月15日:静岡市民文化会館/ヤンソンス
ベルリオーズ/ローマの謝肉祭
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
チャイコフスキー/交響曲第6番
10月16日:聖徳学園川並記念講堂/カヒッゼ
グリンカ/幻想的円舞曲
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
↓
※当初は指揮ヤンソンス
10月17日:東京文化会館/ヤンソンス
ベルリオーズ/ローマの謝肉祭
ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番(P/エリソ・ヴィルサラーゼ)
チャイコフスキー/交響曲第5番
10月18日:東京文化会館/カヒッゼ
グリンカ/幻想的円舞曲
チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲(VN/石川静)
チャイコフスキー/交響曲第6番
↓
※当初は指揮ヤンソンス
10月19日:サントリーホール/ヤンソンス
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
チャイコフスキー/交響曲第4番
↓
※当初は指揮ムラヴィンスキー
チャイコフスキー/交響曲第5番
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
というもの。
今回のCDはこの公演の最終日だが、ムラヴィンスキーの日はすべて曲順、もしくは曲目が変更されたことが分かる。
特に最終日が、いきなりツアーでまったく演奏予定のなかった4番を、しかもショスタコーヴィチと順番を入れ替えてまで持ってきたのは、ヤンソンスにいろいろと思うところがあったのかもしれない。
というのも初日のチャイコフスキーの5番など、確かに凄い演奏だったけど、ヤンソンスの音楽とこのオケにムラヴィンスキーが刻んだ深い刻印が最も色濃く押された曲とのそれにより、音楽がやや小型にまとまってしまったようにも感じられていたからだ。
また当初はこのツァーでヤンソンスが5番を指揮するのはわずか2回のみだったことからも、この曲をこのオケで指揮するのは当初から多少荷が重かったのかも。
因みに前回77年にムラヴィンスキーと来日した時も5番は指揮しておらず、ドヴォルザークの新世界と、今回急遽取り上げた4番、そしてムラヴィンスキーが初演したものの、すぐにレパートリーから外し録音すら残さなかった、ショスタコーヴィチの9番を指揮している。これは何とも当時意味深に思ったものだけど、残念ながら自分は聴く事がかなわなかった。
とにもかくにも最終日は、曲順変更+曲目変更という、同オケの来日公演でも異例の事がここで起きた。
あとこの曲はムラヴィンスキーがかなり以前に自分のレパートリーから外していた事もあり、それもまた急遽演奏される要因になったような気がする。
(実際この曲はレニングラードフィルにより1970年以降、73年を除いて毎回演奏されているが、指揮はすべてヤンソンス父子かドミトリエフによって行われている。因みに1958年のレニングラードフィル初来日時には、当初ムラヴィンスキーが指揮する予定となっていたが、来日中止となったため、代わりに来日したガウクが同曲を指揮している)
(今、急に思い出したけど、前述した77年公演時の4番は、聞いた話ではなかなか好評だったそうなので、案外オケ側からの提案もあったのかもしれない)
とにかくこの日のメインはこの曲となり、同オケ初の、まだオープンしたばかりのサントリーホールのコンサートになったというのがここまでのあらまし。
因みに同ホールではその三日後の22日にはチェリビダッケとミュンヘンフィルにわるブルックナーの5番、そして28日から急病のカラヤンの代わりに指揮台に立つ小澤指揮のべルリンフィルが三日間続けての公演が行われている。
※しかしこの頃のサントリーホールの扉。ホール内から外に出るとき本当に重くて、肩で押しながら体全体で押し開けるような事がよくあった。あれはいったい何だったんだろう。気圧?
さてこのCD。
残念ながら自分はこの日の公演には行ってないので、後日テレビでみたりしかしてないけど、このCDに対してはじつは賛否両論。特に録音に対してのそれに辛辣なものがあり当初購入を躊躇していたところがあった。
で、聴いてみて思った事に、テープが劣化しているのかな?とちょっと思ってしまった。
オケがなんか気持ち遠いというか、そのせいかこんなに柔らかかったかなあ?というのが印象としてすぐに来た。初日に聴いたオケの音とはほとんど別物という感じだけど、ホールのせいあるのかなとも思ったが、それでも以前みたテレビともかなり違う。音全体は綺麗にとれているけど、やや綺麗すぎて聴きやすい反面、生々しさが後退したように感じられた。
ただひょっとするとサントリーホールの音をすくい過ぎているのかもしれないとも思った。
ここのホールは「一階席中央のほぼ真上付近」+「二階席中央に座り真っ直ぐ正面をみたあたり」に、音の逃げ場がなくもやもやと固まってしまうような領域がときおり、特にオケの音が大きく速くなる時にあらわれるように感じられ、それごとこの録音はすくったように感じられた。
この音の領域は、1990年のスヴェトラーノフのチャイコフスキーの4番でも悪さをし、自分はいまいちの印象だったが、その後のCDではそこをうまく捌いたことで、むしろ実演より素晴らしく感じたほど。
ただこの領域はいつの間にか感じられなくなったので、時間が経つとホールの音響が落ち着くというそれにより解消されたのかもしれません。
とにかく何か腑に落ちないので、次にヘッドホーンを外してスピーカーにして聴いてみた。
これがまたなんともな安物な代物だけど、なぜかこれで聴いたら「おお、凄い」という音が出てきた。
ひょっとしたらこのCDは、そういうことよりも聴く装置や環境によってかなり変わるのかなあという感じがして、今は専ら安物のスピーカーで聴いている。
で、演奏はどちらも直線的といっていいくらい、真正直かつ正攻法ともいえる演奏。オケはときおり疲れのようなものを感じさせる瞬間がショスタコーヴィチに感じる時があるけど、それでも全体的にはかなりしっかりとしたものになっている。
そしてこの日のために用意された後半のチャイコフスキーはとにかくオケが凄い。ムラヴィンスキーという手綱を離れた時、このオケはこういうタイプの凄い演奏をするのかという感じだった。しかも音のバランスも崩れないのにも感心しきり。もっともこのあたりはヤンソンスの指揮の確かさのあらわれもあるだろう。
またオケ全体の持つエネルギーと情報量が「巨大なオーケストラ」というくらい凄まじく、そのヤンソンスをもってしても、その情報量の波に飲み込まれ過ぎたかのような感があり、正直指揮者が不在といっていいくらいオケが全面的に主導権を握っているような、そんな状況がけっこう感じられた。
ただそんなヤンソンスも、どちらの曲も後半になるとかなり地力を発揮しており、そういう意味では聴き終わるとそれ相応の満足感が得られる演奏となっている。
これを聴いていると、翌年の晩秋にダブリンでシャンドスに録音した、同オケとのプロコフィエフの5番が思い起こされる。
あれも前半は指揮者がオケに埋没してしまう瞬間が多々あったが、後半になると次第にヤンソンスがオケをドライブしはじめなかなかの演奏にまとめ上げていた。
もしこの演奏が、あのダブリンセッションレベルの音質だったらまた違った印象だったかもしれない。
あとこの録音はムラヴィンスキー在世中のレニングラードフィルによる最後の来日公演の記録というだけでなく、同じく最後のショスタコーヴィチとチャイコフスキーの記録という意味でも、とても貴重な史料的価値のある音盤ということも言えると思います。
と、こんなところが聴き終わった今の感想です。
あとは余談を少し。
じつはこの来日公演、初日なのか最終日なのかは不明ですが、当時メロディアと契約していた日本ビクターが、ムラヴィンスキーの公演を、当時ビクターが開発していたVHD(VHSではない)用に録画録音しようという企画があった。
当時ブーニン旋風によりビクターのクラシックはたいへんな売り上げを出していたこともあり、さらにこの公演にかなり期待していたようだったし、当時のビクターの技術なら、最高レベルのムラヴィンスキーの映像&録音が残されていただけに、自分も含めこれを知っていた人たちには本当に残念な結果となってしまった。
もうひとつ。
マリス・ヤンソンスの初来日は1977年のレニングラードフィルとの公演だが、じつは1975年にも来日の予定があった。
ただしそれはレニングラードフィルではなくモスクワ放送響との来日公演。
ロジェストヴェンスキーが同オケを退任した後、その後継者は一時もめたと言われているが、結果フェドセーエフが就任し今日(2021年3月)まで続いている。
だが当初は1971年にカラヤン指揮者コンクールで二位になり、当時レニングラードフィルの指揮者陣にも加わっていたヤンソンスも来日指揮者として、フェドセーエフとともにクレジットされていた。
その後ヤンソンスの名前はいつの間にか消え、フェドセーエフのみの単独来日となったが、ソ連のオケで指揮者が単独でひとつのオケとまるまる来日公演をするというのはそれまで前例がなく、そういう意味では珍しいツアーとなった。ただし一か月以上の長期滞在で、じつに21公演を北海道から九州まで一人でこなすというたいへんなツアーとなってしまったようです。
このツアーにもしヤンソンスが同行していたら当時どんな指揮をし、どう評価されていたことでしょう。
最後に。
86年公演の前回来日公演にあたる1979年レニングラードフィル来日時には、マリスの父アルヴィドもチャイコフスキーの4番を指揮している。
特にマリスと父はときおり同じ解釈を曲によってスコアに記す事もあったというので、そのあたりの事など特に興味があったのですが、79年公演はヤンソンスの指揮では「幻想交響曲」の日しか聴けなかったので(当時の懐の事情により)こちらもまた不明です。
以上で〆です。
※このブログにおけるムラヴィンスキー関連の項目
https://orch.blog.ss-blog.jp/archive/c2305360029-1
カラヤン指揮のバッハ「マタイ受難曲」 [クラシック百銘盤]
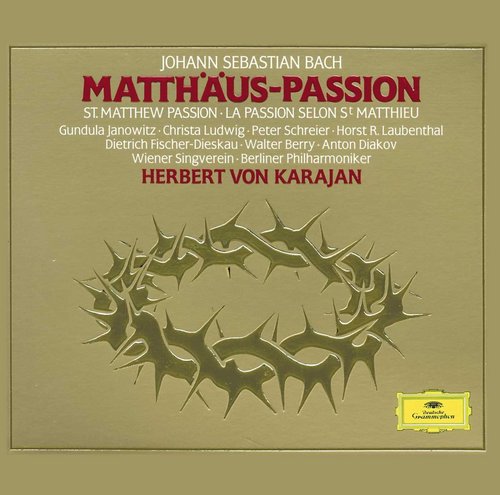
ペーター・シュライアー(T):エヴアンゲリスト(福音史家)
ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br):イエス
グンドゥラ・ヤノヴィッツ(S):アリア、第一の女とピラトの妻
クリスタ・ルートヴィヒ(A):アリア、第一の証人と第二の女
ホルスト・ラウベンタール(T):アリア、第二の証人
ヴァルター・ベリー(Bs):アリア
アントン・ディアコフ(Bs):ペテロ、ピラト、祭司長とユダ
ウィーン楽友協会合唱団(合唱指揮:ヘルムート・フロシャウアー)
ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団(祭司長たち:第50曲)
(合唱指揮:ヴァルター・ハーゲン=グロル)
ベルリン国立合唱団少年団員及びベルリン大聖堂聖歌隊少年隊員
(合唱指揮:カール・ハインツ・カイザー)
ミシェル・シュヴァルベ、レオン・シュピーラー(ヴァイオリン)
アンドレアス・ブラウ、ヨハネス・メルテンス(フルート)
ローター・コッホ(オーボエ)
ゲルハルト・シュテムプニク、ゲルハルト・コッホ(イングリッシュ・ホルン)
オトマール・ボルヴィツキー(チェロ)
ヘルムート・シュレーフォート、ハインリヒ・ケルヒャー(オーボエ・ダモーレ)
通奏低音
エバーハルト・フィンケ、オトマール・ボルヴィツキー(チェロ)
ライナー・ツエペリッツ、フリードリッヒ・ヴィット(コントラバス)
ヴォルフガング・マイヤー(オルガン)
ホルスト・ケーベル(オルガン/チェンバロ)
ヘルベルト・フォン・カラヤン(オルガン:第41曲)
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
収録場所、ベルリンのイエス・キリスト教会。
収録日
① 1972年2月1日~4日、7日~11日。3月15日~17日、28日~30日。4月4日、5日。5月22日。6月28日~30日。7月3日~6日、11月5日。
(※1973年2月迄録音という説あり))
② 1971年12月14日、72年1月5~7日、2月14日、6月7~26日、7月1日、11月1日。
(※6月7~27日という説あり)
録音は①と②の二種類がデータとしてあるけど、どちらにせよ約一年程の長期間に渡るセッション録音となった。
また1972年の3月28日と31日に、ザルツブルグ復活祭音楽祭で、ほぼ同じメンバーでマタイを演奏しているが、①のデータだとそのあたりとモロに被っているので、もし①があっているとしたら、この時期にソロを中心として、かなりの部分が録音されたような気がする。
また何人かの歌手はその前後の「トリスタン」やヴェルディの「レクイエム」でも共演しているので、②があっているのなら、そのあたりでもソロパートの部分が多少録音が行われたのかも。
自分が「マタイ受難曲」を最初に聴いたのは、1974年の「マタイ」が初演された日と同じ4月11日に、前年開場したばかりのNHKホールで、ヘルムート・リリング指揮のシュッツトガルト・バッハ・コレギウムによる同曲の演奏を、後日テレビで放送したものだった。
だがこれは自分にバッハとの距離を遠ざけるものとなってしまい、以降バッハとはかなり疎遠になってしまった。
それは演奏の良し悪しではなく、やはり当時の自分には難解だったのだろう。
その後「マタイが分からないものは精神的に低いレベル」とか糞みそに言われた事もあいまって、ますますバッハを敬遠してしまった。
それから長い年月の後、「ロ短調ミサ」や「ヨハネ受難曲」を好んで聴くようになってから、その余勢をかって「マタイ」を聴き始めたが、メンゲルベルク、クレンペラー、マウエルスベルガー、フルトヴェングラーと、やはり聴いていてしんどいものがあった。
その後、林達次氏やショルティ、そしてリヒターの日本公演のライブ盤を聴き、どうにかこうにか聴けるようにはなったものの、とにかく「マタイ」との相性はすこぶる悪かった。
そんな時聴いたのが上記カラヤン盤。
この盤のことはカラヤンが1973年秋の来日にあわせ10月にLP4枚組で発売された時から知っていた。そして当時の広告には、
「カラヤン65歳、だから今、マタイ」
というような謳い文句がおどっていた。
正直、だからどうしたというくらい意味不明などうでもいい広告だったけど、レコードメーカーの入れ込みとは対照的に演奏の評判はすこぶる芳しくなく、バッハの権威といわれた磯山氏からは、これでもかというくらいボロクソにけなされたらしい。
ただ当時自分はバッハのこの曲にまったく興味がなく、また翌年前述したとおり、さらにこの曲から遠ざかってしまったため、これらの悪評をまったく目にすることがなかったのはむしろ幸いだった。
すでに発売されてから数十年が経ち、世紀替わりもしてのそれだったが、初めて聴いた時の印象は意外なくらい良好だった。
確かにバッハ「らしくない」。
それはハイフェッツの無伴奏と似たそれと言っていいのかもしれない。
つまり「カラヤンのカラヤンによるカラヤンのためのマタイ」というべきこれはそれだったし、ハイフェッツのバッハを聴いて「天才はかならずしも求道者ではない」というそれにも似たものを感じた。
この演奏の芳しくない理由の多くは禁欲的ではないというそれもあるかもしれないが、それ以上にカラヤンのレガート多様の、いわゆるバロック音楽としては些か厚化粧(自分はかならずしもそうは思っていないけど)のそれに代表されるような、とにかくバッハらしくない、もしくは今の感覚から言うと「やってはいけない」とよく言われている演奏スタイルだった。
もっともらしくないといえば、メンゲルベルクだってそうだけど、カラヤンのそれは、そのメンゲルベルクを好んだ人達からも支持されていないように感じられた。
おそらくそれはメンゲルベルクのようなドラマ性、特に「歌」の凄みや説得力が希薄に感じられたからだろう。
これはウィーン楽友協会の合唱団の音程の怪しさを含むアマチュア感や、基本的な腰の弱さみたいなものもあるかもしれないけど、どうも技術以前の熱量の方が問題にされているようだった。
確かにカラヤンの「マタイ」はある意味とても冷めている。熱くなったり叫んだりというドラマがあまり感じられない。最近のピリオド系の熱さにも繋がる、切り込みや俊敏さなども微塵にない。
ただだからといって覇気の無い音の羅列ということもなく、過剰な劇性を排し、むしろその有機的とも形容したくなる長大な音の繋がりによって生まれた音響による、延々三時間以上続くその様は、まるで大河か大海原のような趣さえある。
ベートーヴェンは、「バッハは小川でなく大海だ」と言ったそうだが、正直この演奏ほどそれを感じさせるものも無いような気がした。
もうひとつ、このように感じたことの理由に、歌手に対するカラヤンの計算があるようにも思えた。
今回カラヤンはかなり豪華なソリストを揃えたが、バスとテナーに、各一人ずつやや豪華とはいえない歌手を配している。しかも明らかにこの二人は他の歌手に比べ影か薄い。
ここからは推測だが、この二人は同じ音域の三人の男性歌手(シュライヤー、ディースカウ、ベリー)とは役割が違うのではないかという気がした。
つまり三人はそれぞれカラヤンの指示の下でも、当然その存在感や個は出てきてしまうし、またそれなくしてはこの作品はかなり厳しい。
だが残りの二人はそれが無い。そこの部分はカラヤンの手兵ベルリンフィルの音の中に組み込み、オケのパートとして機能させようとした。つまりカラヤンのマタイにおけるソリストは5人しかいない、それ以外はすべてベルリンフィル同様、自分の手足として機能させようとした選んだのではないかということだ。
このような歌手にスタンドプレーを許さず、すべてを指揮者の統率下に完全に組み込むやり方としては、トスカニーニがNBCとともに録音したオペラの数々がでてくるが、ここでのカラヤンがまさにそれをここでも行ったということ。
ただしトスカニーニと違うのは、5人(もしくはヤノヴィッツを除く4人)のみ、それを厳格には施さなかったということ。(もっともその歌手たちも自由にできたというわけではないと思う)
そしてこの演奏の最大の特徴として、オケの音楽が、ソリストや合唱以上に雄弁かつ全体の主導権を強く握っているということ。極端に言ってしまうと、「歌詞」よりも「音楽」そして「響き」を前面に出し、それで曲を引っ張ろうとしていると言っていいのかも。
しかもその音が大きな繋がりと、遅く重い音質のためよりその趣が強く感じられ、合唱も全体的にオケに引っ張られるように声を出している部分があり、これがまたさらに「音楽」主導に聴こえる要因のひとつとなっている気がする。
それにしてもオケの表情。
編成が大きくないので、ワーグナーやRシュトラウスみたいなことにはならないけど、それでもこの細かい表情のつけかた、そしてその多さはかなりのもの。
ただそれがこれだけ連続すると、何故か音色や音質の統一感と相まって、かえってその細かさが相殺されたかのように、大きなフレーズの連続と、磨かれた濁りの無い艶やかかつ雄弁な響きの方が強く印象に残る。
そのせいだろうか、この演奏のオケの表情の変化や動きのたびに、自分は何度も対訳をその都度見返しているが、音そのものに引っ張られてこういうことをしているのは、この演奏くらいかもしれない。
そういえばシュライアーはこのセッションの二年前にあった、マウエルスベルガー指揮の「マタイ受難曲」で同じエヴァンゲリストをやっているが、マウエルスベルガーに比べ、この重く遅い、そして背後で驚くほど自己主張するオケの音に、そのバッハ観がかなり自分と違うこともあり、本人もなかなか難しかったのではないだろうか。
これはカラヤンのマーラーの9番でも聴かれた傾向だけど、バッハでやるというのはさすがに驚くと同時に、カラヤンの自分のスタイルに対する信念のようなものすら感じられる。
ここまでこう言ってくる、カラヤン独自のスタイルによる異形のバッハと聞こえるかもしれないし、じっじさいそうかもしれないけれど、じつは自分にとってこれほど聴きやすいというか、耳をとらえて離さないバッハというのも稀という気がする。
おそらくそれは、自分がキリスト教や聖書、さらにはドイツ語に精通していないことが、この「音」と「響き」主導のマタイがとっつきやすかったことと、あまりにもオケがいろいろと表情を細かく凝らすため、それにより今迄ぼんやりしていた歌詞やストーリーが、その音を頼りに次々と自分の中でフォーカスが合っていったためではないかと思う。
言葉という障壁を取り除いて、音楽のみでも充分解説をしているといってもいいのかもしれないが、ただそうなると「言葉はどうなった」「もっと歌を大切にしろ」と聖書等に詳しい方から異論が間違いなくでてくる類の演奏だろうなあという気もした。
あとこういう事を言われると怒られるかもしれないけど、もし「マタイ受難曲」を喫茶店やサロンでのBGMとして使いたいという人には、ダイナミックレンジも大きくなく、音は流麗で濁りが少なく、ゆったりと悠久の流れを紡ぐようなこの演奏は最適かもしれないという気がした。
もちろんそれだけにとどまらず、随所にかなりの聴きどころもあり、特に最後の「われらは涙流してひざまずき」におけるたっぷりとした響き、そして最後の音の尋常じゃない引き延ばしなどは、その好例だと思う。
最後に。
最初この演奏「らしくない」と言ったけど、そもそも「らしい」とはどんな定義があり、その発端や動機付けは何なのかというと、これらの多くは特定の大看板を背負った人の大きな声による発言であったり、なんとなく昔からそういうのが主流だからという、ひじょうに漠然としたもの、もしくは理由付けや論理性が見受けられ辛い慣習から端を発しているのではないかというものもある。
それはバッハだけでなく、モーツァルトやブルックナーも然り。
確かに多くの研究成果により、そうはじき出されたものもあるとは思うが、数学や化学などとは違い、最後にはその研究者の主観や価値観による判断がどうしても入り込まなければならない部分も多々あることを思うと、はたして今の聴き手や演奏側が、「らしさ」というものに対し漠然とそれを「正しい」もしくは「唯一無二」と広く吹聴したり決めつけていいのかという疑問はどうしても残る。
それを思うと、ピリオドや小編成ものが評価されるのは良い事かもしれないが、だからといって、より大きな編成、さらにはかつてのモダンスタイルといわれているそれを排除し、黙殺否定してしまうのはいかがなものかという気もする。
また得るものがある時はかならず失っているものがある。問題はその選択が何を基準として判断し、何をもって「らしさ」と直結させているかという精査の部分にある。
そこが曖昧のまま「らしさ」をいくら強調されても、自分にはそれはただの慣習であり惰性ととらえてしまう事もある。
それと音楽とは、自分の立つ位置によって同じ山をみていてもまるで違う、もしくは正反対の印象を受けることが日常茶飯事にある。
そこに上で延々と話した「らしさ」のことを再度考えると、何ともいろいろとそれに対して考え込んでしまう。
また「らしさ」がそのまま「正しい演奏」となるかというとこれまたどうなんだろうと、別の問題がそこにはでてきてしまう。
とにかく今回のカラヤンのマタイを聴いていて、そのこともとても強く考えさせられたものでした。
だからといってカラヤンのマタイは「らしさ」を否定した、最も惰性や慣習から離れた、大胆かつ挑戦的なものなのと言い切るつもりはない。何故ならそこにはいつものカラヤンのスタイルを踏襲した、カラヤンのやり方を惰性と慣習で推し進めたという考え方も可能だからです。
以上で〆
マゼールのバッハ [クラシック百銘盤]

マゼールは1960年代半ばにかなり集中してバロック音楽を録音している。
1964年にまずヘンデルの「水上の音楽」と「王宮の花火の音楽」。
1965年の9月にバッハの「ロ短調ミサ」、
その翌10月に「ブランデンブルク協奏曲」、
さらにその翌11月に「管弦楽組曲」、
1966年に「復活祭オラトリオ」を録音している。
演奏はすべてベルリン放送交響楽団(現ベルリン・ドイツ交響楽団)。
マゼールはフリッチャイの死後空席となっていたこのオケの首席指揮者に1964年から就任していることから、その直後からヘンデルとバッハに取り組んでいた事になる。
当時このオケは1962年に29歳で入団した豊田耕児氏がコンサートマスターに就任し、さらには1965年から25歳のゲルハルト・ヘッツェルが入団ということで、かなり若い力が台頭したオケという趣があった。
またバッハの三作品のソロを担当したほとんどが三十代前後で、ロ短調ミサの独唱者でもヘフリガー以外、やはり同世代の人たちが揃っている。
そのせいかこれらの演奏でマゼールはじつに他に気兼ねすることなく、思う存分自らの音楽を展開している。
特に特徴的なのは弦楽器の響きと表情。
節度とデフォルメが交錯しながらも、繊細かつ清澄な響きとリズムの良さが全編に感じられるだけでなく、それらがどの曲でも主導権を握っているのが面白い。
しかしこれほど弦が全面的に、しかも厚ぼったさや鈍さと無縁の響きをモダンオケから引き出したバロック音楽というのを、自分はあまり聴いたことがない。
なので、濃厚な表情をときおりみせながらも、とても爽やかな印象が強く残るのはそのためなのだろう。
因みにブランデンブルクの2番ではこれまた当時三十代のモーリス・アンドレが担当しているが、彼は同年イ・ムジチと、そして翌年にはシューリヒトとこの曲のソロをとり録音しているので、このあたりの聴き比べもまたなかなか面白いかも。
この当時、何故マゼールにこれほどバッハを録音させたのがちょっと不思議だったが、いろいろ調べていてなんとなくその理由の一端が分かったような気がしました。
当時これを録音したフィリップスはドイツ・グラモフォンと業務提携していたことで、マゼールの指揮がこのレーベルで実現したのだろう。
またバッハについてですが、1955年にグールドによる「ゴルトベルク変奏曲」、1958年にリヒターの「マタイ受難曲」やそれに続くバッハの名曲の数々、そしてバッハではないがイ・ムジチが1955年と1959年に録音した「四季」が、バロック音楽、そしてバッハを広め、そして「商い」になることを証明したことが大きく、フィリップスもその流れに乗ったとみるべきなのだろう。
じっさい1965年はマゼールの三作品だけでなく、イ・ムジチのブランデンブルク、ジャンドロンの無伴奏チェロ組曲、そしてヨッフムとコンセルトヘボウによる「マタイ受難曲」が録音されているし、翌年以降もマゼールの「復活祭オラトリオ」、ヨッフムの「ヨハネ受難曲」、シェリングとヴァルヒャによるヴァイオリン・ソナタ、アーヨの無伴奏ソナタとパルティータ、ヨッフムの「クリスマス・オラトリオ」等々が録音されていった。
このマゼールのバッハ。
今はほぼまったくといっていいほど省みられていない。
ただハイフェッツのバッハがシゲティのそれと聴き比べてみると
「天才はかならずしも求道者ではない」
という印象が強く残ると同じように、これらのバッハもたしかに「らしく」はないのかもしれないけど、マゼールという天才にしかできない、というかその語法を認めれば素晴らしく聴き応えがあり、そして聴いてもまるで疲れを感じさせない、じつに見事なバッハと言える。
あとマゼールのバッハ。ロ短調、ブランデンブルク、管弦楽組曲と、後に行けば行くほど、音楽がオケともども、よりこなれているのが面白い。
以上で〆
「ジョン・ウィリアムズ&ウィーン・フィル/ライヴ・イン・ウィーン」を聴く [クラシック百銘盤]

1. ネヴァーランドへの飛行(『フック』から)
2. 『未知との遭遇』から抜粋
3. 悪魔のダンス(『イーストウィックの魔女たち』から)
4. 地上の冒険(『E.T.』から)
5. 『ジュラシック・パーク』のテーマ
6. ダートムア、1912年(『戦火の馬』から)
7. 鮫狩り - 檻の用意!(『ジョーズ』から)
8. マリオンのテーマ(『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』から)
9. メイン・タイトル(『スター・ウォーズ/新たなる希望』から)
10. レベリオン・イズ・リボーン(『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』から)
11. ルークとレイア(『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還』から)
12. 帝国のマーチ(『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』から)
13. レイダース・マーチ(『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』から)
ジョン・ウィリアムズ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
アンネ=ゾフィー・ムター(ヴァイオリン3 & 13)
録音時期:2020年1月18日&19日
録音場所:ウィーン、ムジークフェラインザール
というCDが発売された。
同時発売された映像には、これプラス6曲ということで、自分はコンプリードCDが出ないかと待っていたけど、さすがに一ヵ月待って我慢できなくなりCDを購入した。
なので自分は全13曲のみしか聴いていません。
ジョン・ウィリアムズが1980年にボストンポップスの常任指揮者になった時、自分は彼らの来日公演が実現できないものだろうかと期待していたけど、なにしろジョン・ウィリアムズは作曲家としても多忙なので、それはさすがに実現しないだろうと思っていた。
しかも1984年にオケの一部メンバーによる不遜な態度が、それまでも似たような姿勢に不満を持っていたウィリアムズの堪忍袋が真っ二つに切れ、辞表を事務方に叩きつけたという。
結局オケの事務方トップと、オケの該当メンバーの謝罪により最悪の事態は免れ、雨降って地固まるなのかもしれないが、その後両者の関係は1995年迄続き、その後も桂冠指揮者として関係は続いている。
そんな事件の四年後、ジョン・ウィリアムズとボストンポップスの両者ともに初来日となる公演が1987年に行われ、以降、1991年、そして1995年と三度来日することとなる。これは本当に望外の喜びでした。
(ただし初来日はボストンポップス・エスプラネードオケで、ボストンポップスは残りの二度を担当)
このうち自らの常任指揮者の最終シーズンの、その終わりに挙行された三度目の来日公演の最終日に、当時自らも初めてという、「オール・ジョン・ウィリアムズプロ」が行われた。
内容は、
6月21日昭和女子大人見記念講堂
バルセロナ・オリンピック・NBC-TV用ファンファーレ
11人のカウボーイ
JFK
スター・ウォーズ
(ダース・ベイダーのマーチ、王女レイアのテーマ、メイン・テーマ)
スーパーマン
未知との遭遇
イーストウィックの魔女たち(悪魔の踊り)
偶然の旅行者(愛のテーマ)
E.T.(地上の冒険)
アンコールのみ他公演でもアンコールで演奏されたスーザのマーチだったけど、とにかくこれが彼の初のオール自作自演プロとなった。
当然会場は沸きに沸き、誰もが大満足の公演となりました。
月日は流れ、2019年の3月に世界的名指揮者ドゥダメルが手兵LAPOとともに、オール・ジョン・ウィリアムズプロをアメリカでウィリアムズ自身を招き行われ、その後ウィリアムズは同行しなかったものの、同内容の公演が日本でも行われた。
これはアメリカでも日本でも、当然のごとく大きな話題になり、アメリカ公演はライブ盤として来日時に緊急発売され、日本公演はNHKで放送され、さらに異例ともいえる再放送まで行われた。
そして今年1月。
とうとう作曲者自身がウィーン・フィルを指揮して、オール・ジョン・ウィリアムズプロを、ウィーン・フィルの本拠地、ウィーン楽友協会大ホールで演奏した。
四半世紀前には、本人すら想像できないことだっただろう。
ウィーン・フィルのジョン・ウィリアムズというと、10年前の6月に行われたシェーンブルン宮殿夏の夜のコンサートにおける、当初はジョン・ウィリアムズの招聘が予定されていたコンサートにおける、ウェルザー=メスト指揮の「スター・ウォーズ」が有名だけど、そこでの曲も今回メイン・テーマや帝国のマーチなどが演奏されている。
今年88歳となるジョン・ウィリアムズが自作を、あの楽友協会大ホールでウィーン・フィルを指揮。そしてゲストにムター。
もしこれが日本で実現していたら、かつてのカルロス・クライバーのウィーン国立歌劇場との「ばらの騎士」並みの入場料金(最高ランクで6万5千円)でも瞬時に全席完売していただろう。
そんな超がいくつついても足りないようなスペシャルコンサートだけど、過去二度この組み合わせが流れた事と、この二か月後に新型コロナによりウィーン・フィルのコンサートが長期休止に追い込まれたことを思うと、まさにこの時期しかないというタイミングによる、それこそ奇跡のようなコンサートといっていいのかもしれない。
演奏を聴いてすぐに1974年にマゼールがウィーン・フィルを指揮して録音した、ストラヴィンスキーの「春の祭典」を思い出した。
確かあれも同曲をウィーン・フィル初の録音ということで、かなりユニークな演奏となっていたが、これも同様に過去のジョン・ウィリアムズの曲の演奏としてはユニークな感じがした。
特にときおりウィーン・フィルをはじめ、いくつかの古い語法を守っているオーケストラがみせる、楽譜としてはズレながらも音楽としては合わせるという独特の技術が随所で散見され、ときおりそれによりリズムの明晰さやキレが後退する場面があり、けっこうそこで好き嫌いが分かれるのでは?という気がした。
ただそれ以外では聴きどころ満載!
「フック」や「ジュラシック・パーク」の冒頭のホルンなど、ホールの響きも相まった、いかにもという光沢と膨らみをもった豊かな響きが魅力的だし、ゆったりとしたメロディの歌い方など、いかにもオペラで多くの場数を踏んできたオケだけあって、米英のシンフォニックな歌い方とはまた違った味のあるそれを聴かせている。
そしてリズムが重い。
これは前述したズレとも関係しているが、ひとつひとつの音は太くないし重くもない、むしろ音質としては軽い部類だろうけど、それがひとつになり、そしてリズムを刻むと、独特のズレとそれに乗っかる各パートのバランスにより、独得の質感の重さがでてくる。
これが随所で力を発揮し、マーチ系ではときおりボストンあたりよりも重い響きが聴こえてくる。
またホールの残響な豊かなこともあって、打楽器群の重低音のそれがかなりの迫力で響いてくる。ただこれまたホールの特性からだろうか、ボストンあたりの録音に比べると、やや横の拡がりが窮屈に感じられる時がたまにあるけど、聴き進めていくうちに気にならなくなっていくのは、やはりそれらを乗り越えてくる、圧倒的な情報量と魅力がそこにあるからだろう。
指揮のジョン・ウィリアムズ。
彼の指揮は1980年頃に比べると年々遅く、そしてやや穏やかにものになっていく傾向があり、それがここでもときおり感じられるけど、それは他の高齢な指揮者に比べるずっと小さいといっていいと思う。
確かに曲によっては、もう少しはやい演奏を、オリジナル等に耳が慣れた人には感じられるかもしれないけど、個人的には数回聴いたら、あまりそのあたりも気にならなくなった。
また遅くなったことが、曲によってはウィーン・フィルの前述した重さと相まって、他の演奏では感じられない、独得の凄みと迫力を生んでいて、それがこのアルバムの大きな聴きものとなっている。
とにかく全体的に、今までのジョン・ウィリアムズのアルバムとしては異色かもしれないけど、予想以上に聴きどころの多いものとなっている。
しかしウィーン・フィルによるジョン・ウィリアムズを聴いていると、ワーグナーがもしあと百年遅く生まれていたら、彼もまたウィリアムズと同じ道を辿ったのではないかと、ふとそんなことを思ってしまいました。
以上で〆
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮フィラデルフィア管弦楽団 [クラシック百銘盤]
トスカニーニが1941年の11月から翌年2月にかけてフィラデルフィア管弦楽団に客演し、その時演奏した曲目の多くがセッション録音されました。
トスカニーニが何故この時期フィラデルフィアに客演したかというと、トスカニーニとNBC上層部にオーケストラ団員にまつわるいくつかの事実が発覚、それを知ったトスカニーニが激怒し1941年秋からのNBCとの契約を拒否し楽団から去ってしまったことがそもそもの発端とか。
このためトスカニーニはその機会にNBC以外のオケに客演することになるのですが、彼にとって最大のハイライトとなったのがフィラデルフィアへの客演となりました。
当時このフィラデルフィアのトップに立っていたのはユージン・オーマンディで、フィラデルフィアはボストン響と並んで名実ともに全米最高の楽団といわれていました。
オーマンディは1936年からこのオケのトップにいましたが、1940年のシーズン迄は前任者ストコフスキーとの共同だっため、彼自身が単独でこのオケのトップとなったのは、この1941年のシーズンからでした。
オーマンディはトスカニーニを生涯深く尊敬していたこともあり、その最初のシーズンにこの報せはオーマンディにとって願ったり叶ったりだったかもしれません。
トスカニーニは11月中旬にまず、
・シューベルト:交響曲第9番ハ長調 D.944『グレイト』
・ドビュッシー:『イベリア』
・レスピーギ:交響詩『ローマの祭り』
を演奏し、その直後にこれらを録音。
翌年1月と2月にはニューヨークとワシントンで三回ずつ指揮台に立ち
1月に
・ハイドン:交響曲第99番変ホ長調 Hob.I:99
・バッハ(レスピーギ編) :パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582
・メンデルスゾーン:『真夏の夜の夢』より7曲[1942年1月11,12日]
・R.シュトラウス:交響詩『死と変容』 Op.24
2月に
・チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調 Op.74『悲愴』
・ドビュッシー:交響詩『海』
を演奏し、これらも1月と2月にそれぞれ録音がされました。
ですがこれらの音盤の制作過程で事故が起き、不純物が制作時に混ざったことや、戦時中ということで、素材が良質のものではなかった等の理由により、音盤はノイズの激しいものとして仕上がってしまったようです。
トスカニーニはこれを聴き一部は破棄を命じたもの、残りは許可を出したり、再録音をするということでいったんは落ち着きました。
ところが1942年から 1944年にかけて全米音楽家ユニオンによるレコーディング禁止令のため再録音が出来ず、そうこうしているうちにフィラデルフィアがRCAからコロンビアに移籍したことから、RCAはこれらをすべて廃盤扱いにし、すべてNBCと再録音することに決定ということになったようです。
このときトスカニーニはそれを聞いてかなり激怒したようですが、じつはそれくらいトスカニーニはこの録音を高く評価していたようです。
結局この録音はトスカニーニの生前ついに日の目をみませんでしたが、1962年のトスカニーニの没後5年時に、この時の録音を何とか使えないかと当時のスタッフがシューベルトのグレイトのテープを修復したものの、原盤の状態がかなり劣悪で、最初の二つの楽章だけで、修復に750時間かかるという大苦戦を強いられたとか。
最終的に残り二つの楽章を含めた四つの楽章を復刻、翌年にはこれがLPになり、それは日本でも発売されました。
その後さらに7曲が修復され1977年にLPで発売されました。
さらにその後CDの時代になり1990年の晩秋に四枚組の紙製のボックス入りでこれら全8曲が発売されました。
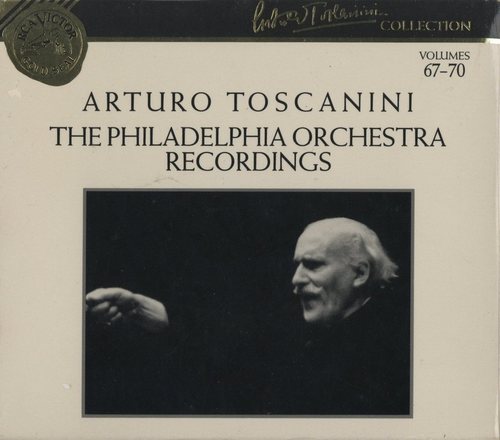
自分はシューベルトのみかつて1970年代にFMで聴いたことはあるものの、それ以外はこの時初めて聴いたのですが、正直その音質の悪さ、特に盛大なノイズのそれにはかなり驚いてしまいました。また回転ムラによる音のふらつきも曲によっては散見され、正直いくらテープ録音以前とはいえ、これはいかがなものかという感じがしたものでした。
ですが、それでも演奏はかなりのものがあり捨てがたい魅力があり、手放すことはさすがにできませんでした。
ところが2006年。RCAがソニーに権利が移った事で、トスカニーニのこのセッションを再度最新の技術で復刻、さらにワルターやセルでも使用され音質向上に成果を上げたDSDも使用し、CD3枚に収めで発売されました。
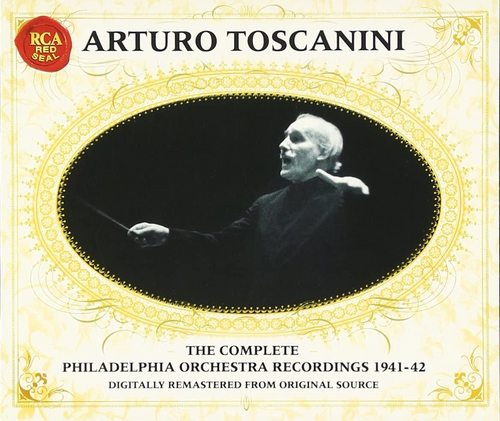
トスカニーニ没後50年に合わせてのそれということですが、これが素晴らしかった。
確かにあいかわらずノイズや原盤の傷、また以前はノイズでマスクされていた原盤の切れ目の繋ぎなどがハッキリ聴きとれるようになったという痛し痒しの部分はあるものの、とにかく1990年のCDよりはるかにノイズが後退、音の立ち上がりや質感の向上、そして緯線より管もクリアに前面に出るようになりました。
最初はその分弦が引っ込んだように聴こえたものの、聴いているうちに前の録音同様の厚みも艶も確保された音質に仕上がっていることが確認され、ようやく年代相応にほぼ近い音質にまで改善され、おかげで繰り返し聴いてもまったく苦にならず、このセッションを愉しく聴くことができるようになりました。
もしトスカニーニが生前このレベルの音を耳にしていたら随喜の涙を流したのではないかというくらい、とにかくようやくまともな音になってくれた。
ところでこの演奏。
聴いていて、なにかベーム指揮のウィーンフィルのセッション録音とどこか重なるような感じがした。
ベームというと初期はトレスデン、その後ウィーンフィルと録音したものの、ウィーン国立歌劇場の地位を去った頃からドイツのグラモフォンに移籍し、主にベルリンフィルと録音をするようになった。
この時期のベームを色気や柔軟性に乏しいという意見が多く、そのためウィーンとの共演は互いにかけている部分を補った演奏と、高く評価された。
このトスカニーニにとフィラデルフィアにも自分はどこかそれを強く感じる
確かにNBCのようなアタックの強さや、ティバニーの強靭な響きは感じられないものの、NBCの時の柔軟さや色彩感の不足がここでは払拭され、トスカニーニのNBCでは聴くことのできなかった、より自然な流動感、強弱のデリケートなコントロール、そして決して過度に刺激的にならない陰影の妙など、隠れた、もしくは彼本来の魅力のそれが表出されたように聴こえるように感じられた。
そしてひょっとして、もし戦後彼がウィーンフィルとこれらの曲を録音したらこんな感じに仕上がったのではないかとすら感じられたものでした。
ところで自分は最近このトスカニーニのフィラデルフィアセッションを録音された順に聴くようにしているが、それを聴いているとかつてセルの後を継いだマゼールが、クリーヴランドを指揮してその最初のシーズンの終盤に録音したプロコフィエフを思い出した。
それは最高の状態にある最高のヴィルトゥオーソオケを指揮した喜びといっていいのだろうか。無駄な練習に時間を割くことなく、自らの思う理想的な音楽を練習する以前からすでに奏でる事のできる団体と対峙することで、自分の音楽をより強くオケに投影できる満足感というのだろうか。
とにかくそういうものが、最初のシューベルトのグレイトからもすでにそれが溢れんばかりに伝わってくる。トスカニーニがこの録音を廃盤にされた怒りと嘆きがあらためて感じられるほど、とにかくトスカニーニの気持ちのノリが素晴らしい。
その軽やかな足取りと弾力性のあるリズム感、そして隅々まで瑞々しく歌いつくされたそれは、天性のメロディーメーカー、シューベルトの二十代の若々しい息吹すら感じさせるもので、これは間違いなく同曲屈指の超名演といっていいと思う。
(ただオケの方も決して通常運転でトスカニーニに対応できたというわけではなく、全団員が今迄にないほどかなり強い緊張感をもち、個人個人のレベルでもいつも以上の練習をした上でこのセッションにのぞんだようです)
この雰囲気は翌年のセッションでももちろん健在だけど、トスカニーニとフィラデルフィアが互いに手の内がつかめてきたのか、41年の11月のセッションの時のような他流試合的な緊張感よりも、共同作業的な雰囲気が若干強くなったように感じられる。
特に2月の「悲愴」はストコフスキーはもちろん、オーマンディもすでにフィラデルフィアと録音しているので。トスカニーニもフィラデルフィアの語法と伝統というものを尊重しているようなものが感じられる。ただそれは妥協とはまた違うものかと。
この時期がすぎると戦争の激化等の状況の変化もありトスカニーニは再びNBCに戻り指揮をするようになる。
(因みにあの有名なNBCとの「レニングラード」アメリカ初演はこのフィラデルフィアの「悲愴」の五か月後)
そしてトスカニーニはNBCと1954年までその関係を結び続けることになる。
もしというのはあれだけど、もしトスカニーニがNBCに戻らず、またフィラデルフィアもコロンビアに移籍しなかったら、トスカニーニとフィラデルフィアははたしてどうなっていただろう。
さらに十年以上その関係が続き、NBCとの録音されたその多くがフィラデルフィアと録音されたかもしれないし、その中にはベートーヴェンやブラームスの全集も含まれていたかもしれないし、そうなっていたら、トスカニーニのイメージは少なからず今とは違っていたかもしれない。
とにかくそんなことをふとこの一連の録音を聴いて思ったりしました。
トスカニーニとフィラデルフィア。
決して録音は多くありませんが、いろいろと考えさせられる珠玉のセッションといえると思います。
◎録音内容
① シューベルト:交響曲第9番ハ長調 D.944『グレイト』[1941年11月16日]
② ドビュッシー:『イベリア』[1941年11月18日]
③ レスピーギ:交響詩『ローマの祭り』[1941年11月19日]
④ メンデルスゾーン:『真夏の夜の夢』より7曲[1942年1月11,12日]
エドウィナ・エウスティス(ソプラノ)
フローレンス・カーク(ソプラノ)
ペンシルヴァニア大学グリークラブ女声合唱団
⑤ チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調 Op.74『悲愴』[1942年2月8日]
⑥ ドビュッシー:交響詩『海』[1942年2月8、9日]
⑦ ベルリオーズ:『マブ女王のスケルツォ』[1942年2月9日]
⑧ R.シュトラウス:交響詩『死と変容』 Op.24[1942年2月11日]
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮フィラデルフィア管弦楽団
録音場所:フィラデルフィア、アカデミー・オブ・ミュージック
トスカニーニが何故この時期フィラデルフィアに客演したかというと、トスカニーニとNBC上層部にオーケストラ団員にまつわるいくつかの事実が発覚、それを知ったトスカニーニが激怒し1941年秋からのNBCとの契約を拒否し楽団から去ってしまったことがそもそもの発端とか。
このためトスカニーニはその機会にNBC以外のオケに客演することになるのですが、彼にとって最大のハイライトとなったのがフィラデルフィアへの客演となりました。
当時このフィラデルフィアのトップに立っていたのはユージン・オーマンディで、フィラデルフィアはボストン響と並んで名実ともに全米最高の楽団といわれていました。
オーマンディは1936年からこのオケのトップにいましたが、1940年のシーズン迄は前任者ストコフスキーとの共同だっため、彼自身が単独でこのオケのトップとなったのは、この1941年のシーズンからでした。
オーマンディはトスカニーニを生涯深く尊敬していたこともあり、その最初のシーズンにこの報せはオーマンディにとって願ったり叶ったりだったかもしれません。
トスカニーニは11月中旬にまず、
・シューベルト:交響曲第9番ハ長調 D.944『グレイト』
・ドビュッシー:『イベリア』
・レスピーギ:交響詩『ローマの祭り』
を演奏し、その直後にこれらを録音。
翌年1月と2月にはニューヨークとワシントンで三回ずつ指揮台に立ち
1月に
・ハイドン:交響曲第99番変ホ長調 Hob.I:99
・バッハ(レスピーギ編) :パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582
・メンデルスゾーン:『真夏の夜の夢』より7曲[1942年1月11,12日]
・R.シュトラウス:交響詩『死と変容』 Op.24
2月に
・チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調 Op.74『悲愴』
・ドビュッシー:交響詩『海』
を演奏し、これらも1月と2月にそれぞれ録音がされました。
ですがこれらの音盤の制作過程で事故が起き、不純物が制作時に混ざったことや、戦時中ということで、素材が良質のものではなかった等の理由により、音盤はノイズの激しいものとして仕上がってしまったようです。
トスカニーニはこれを聴き一部は破棄を命じたもの、残りは許可を出したり、再録音をするということでいったんは落ち着きました。
ところが1942年から 1944年にかけて全米音楽家ユニオンによるレコーディング禁止令のため再録音が出来ず、そうこうしているうちにフィラデルフィアがRCAからコロンビアに移籍したことから、RCAはこれらをすべて廃盤扱いにし、すべてNBCと再録音することに決定ということになったようです。
このときトスカニーニはそれを聞いてかなり激怒したようですが、じつはそれくらいトスカニーニはこの録音を高く評価していたようです。
結局この録音はトスカニーニの生前ついに日の目をみませんでしたが、1962年のトスカニーニの没後5年時に、この時の録音を何とか使えないかと当時のスタッフがシューベルトのグレイトのテープを修復したものの、原盤の状態がかなり劣悪で、最初の二つの楽章だけで、修復に750時間かかるという大苦戦を強いられたとか。
最終的に残り二つの楽章を含めた四つの楽章を復刻、翌年にはこれがLPになり、それは日本でも発売されました。
その後さらに7曲が修復され1977年にLPで発売されました。
さらにその後CDの時代になり1990年の晩秋に四枚組の紙製のボックス入りでこれら全8曲が発売されました。
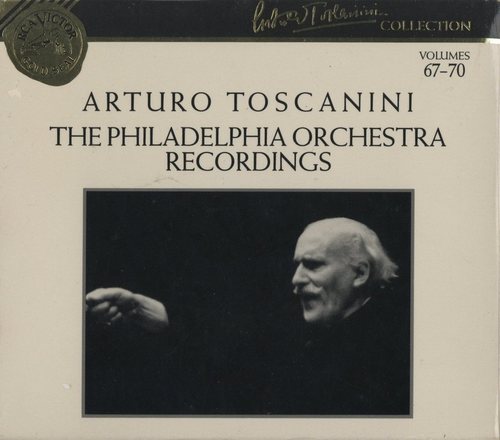
自分はシューベルトのみかつて1970年代にFMで聴いたことはあるものの、それ以外はこの時初めて聴いたのですが、正直その音質の悪さ、特に盛大なノイズのそれにはかなり驚いてしまいました。また回転ムラによる音のふらつきも曲によっては散見され、正直いくらテープ録音以前とはいえ、これはいかがなものかという感じがしたものでした。
ですが、それでも演奏はかなりのものがあり捨てがたい魅力があり、手放すことはさすがにできませんでした。
ところが2006年。RCAがソニーに権利が移った事で、トスカニーニのこのセッションを再度最新の技術で復刻、さらにワルターやセルでも使用され音質向上に成果を上げたDSDも使用し、CD3枚に収めで発売されました。
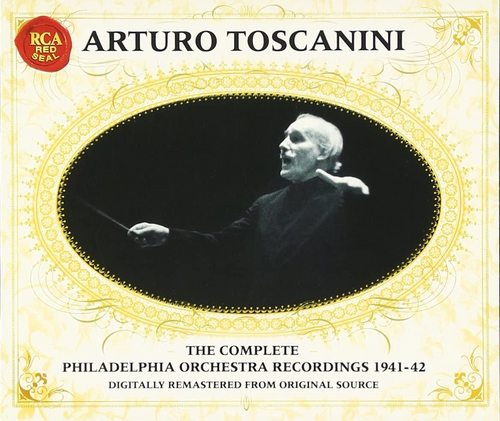
トスカニーニ没後50年に合わせてのそれということですが、これが素晴らしかった。
確かにあいかわらずノイズや原盤の傷、また以前はノイズでマスクされていた原盤の切れ目の繋ぎなどがハッキリ聴きとれるようになったという痛し痒しの部分はあるものの、とにかく1990年のCDよりはるかにノイズが後退、音の立ち上がりや質感の向上、そして緯線より管もクリアに前面に出るようになりました。
最初はその分弦が引っ込んだように聴こえたものの、聴いているうちに前の録音同様の厚みも艶も確保された音質に仕上がっていることが確認され、ようやく年代相応にほぼ近い音質にまで改善され、おかげで繰り返し聴いてもまったく苦にならず、このセッションを愉しく聴くことができるようになりました。
もしトスカニーニが生前このレベルの音を耳にしていたら随喜の涙を流したのではないかというくらい、とにかくようやくまともな音になってくれた。
ところでこの演奏。
聴いていて、なにかベーム指揮のウィーンフィルのセッション録音とどこか重なるような感じがした。
ベームというと初期はトレスデン、その後ウィーンフィルと録音したものの、ウィーン国立歌劇場の地位を去った頃からドイツのグラモフォンに移籍し、主にベルリンフィルと録音をするようになった。
この時期のベームを色気や柔軟性に乏しいという意見が多く、そのためウィーンとの共演は互いにかけている部分を補った演奏と、高く評価された。
このトスカニーニにとフィラデルフィアにも自分はどこかそれを強く感じる
確かにNBCのようなアタックの強さや、ティバニーの強靭な響きは感じられないものの、NBCの時の柔軟さや色彩感の不足がここでは払拭され、トスカニーニのNBCでは聴くことのできなかった、より自然な流動感、強弱のデリケートなコントロール、そして決して過度に刺激的にならない陰影の妙など、隠れた、もしくは彼本来の魅力のそれが表出されたように聴こえるように感じられた。
そしてひょっとして、もし戦後彼がウィーンフィルとこれらの曲を録音したらこんな感じに仕上がったのではないかとすら感じられたものでした。
ところで自分は最近このトスカニーニのフィラデルフィアセッションを録音された順に聴くようにしているが、それを聴いているとかつてセルの後を継いだマゼールが、クリーヴランドを指揮してその最初のシーズンの終盤に録音したプロコフィエフを思い出した。
それは最高の状態にある最高のヴィルトゥオーソオケを指揮した喜びといっていいのだろうか。無駄な練習に時間を割くことなく、自らの思う理想的な音楽を練習する以前からすでに奏でる事のできる団体と対峙することで、自分の音楽をより強くオケに投影できる満足感というのだろうか。
とにかくそういうものが、最初のシューベルトのグレイトからもすでにそれが溢れんばかりに伝わってくる。トスカニーニがこの録音を廃盤にされた怒りと嘆きがあらためて感じられるほど、とにかくトスカニーニの気持ちのノリが素晴らしい。
その軽やかな足取りと弾力性のあるリズム感、そして隅々まで瑞々しく歌いつくされたそれは、天性のメロディーメーカー、シューベルトの二十代の若々しい息吹すら感じさせるもので、これは間違いなく同曲屈指の超名演といっていいと思う。
(ただオケの方も決して通常運転でトスカニーニに対応できたというわけではなく、全団員が今迄にないほどかなり強い緊張感をもち、個人個人のレベルでもいつも以上の練習をした上でこのセッションにのぞんだようです)
この雰囲気は翌年のセッションでももちろん健在だけど、トスカニーニとフィラデルフィアが互いに手の内がつかめてきたのか、41年の11月のセッションの時のような他流試合的な緊張感よりも、共同作業的な雰囲気が若干強くなったように感じられる。
特に2月の「悲愴」はストコフスキーはもちろん、オーマンディもすでにフィラデルフィアと録音しているので。トスカニーニもフィラデルフィアの語法と伝統というものを尊重しているようなものが感じられる。ただそれは妥協とはまた違うものかと。
この時期がすぎると戦争の激化等の状況の変化もありトスカニーニは再びNBCに戻り指揮をするようになる。
(因みにあの有名なNBCとの「レニングラード」アメリカ初演はこのフィラデルフィアの「悲愴」の五か月後)
そしてトスカニーニはNBCと1954年までその関係を結び続けることになる。
もしというのはあれだけど、もしトスカニーニがNBCに戻らず、またフィラデルフィアもコロンビアに移籍しなかったら、トスカニーニとフィラデルフィアははたしてどうなっていただろう。
さらに十年以上その関係が続き、NBCとの録音されたその多くがフィラデルフィアと録音されたかもしれないし、その中にはベートーヴェンやブラームスの全集も含まれていたかもしれないし、そうなっていたら、トスカニーニのイメージは少なからず今とは違っていたかもしれない。
とにかくそんなことをふとこの一連の録音を聴いて思ったりしました。
トスカニーニとフィラデルフィア。
決して録音は多くありませんが、いろいろと考えさせられる珠玉のセッションといえると思います。
◎録音内容
① シューベルト:交響曲第9番ハ長調 D.944『グレイト』[1941年11月16日]
② ドビュッシー:『イベリア』[1941年11月18日]
③ レスピーギ:交響詩『ローマの祭り』[1941年11月19日]
④ メンデルスゾーン:『真夏の夜の夢』より7曲[1942年1月11,12日]
エドウィナ・エウスティス(ソプラノ)
フローレンス・カーク(ソプラノ)
ペンシルヴァニア大学グリークラブ女声合唱団
⑤ チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調 Op.74『悲愴』[1942年2月8日]
⑥ ドビュッシー:交響詩『海』[1942年2月8、9日]
⑦ ベルリオーズ:『マブ女王のスケルツォ』[1942年2月9日]
⑧ R.シュトラウス:交響詩『死と変容』 Op.24[1942年2月11日]
アルトゥーロ・トスカニーニ指揮フィラデルフィア管弦楽団
録音場所:フィラデルフィア、アカデミー・オブ・ミュージック
山形交響楽団のブルックナーの6番 [クラシック百銘盤]
2011年3月11日。
日本にとって忘れられない一日だった。
自分は当時横浜の西区高島の帷子川にかかる万里橋の側でこの揺れに遭遇した。
時間は午後二時四十六分を少し過ぎたころだろう。
このとき自分「ついに東南海が来た」と思ったが、その後震源が東北と聞いて仰天した。
確かに宮城県沖で震度7クラスの地震が起きると警告されてはいたが、この揺れはそれとは規模があまりにも桁違いだった。
それからはまさに未曾有の体験の連続だった。そして福島原発の予想もしなかった崩壊。
今のコロナとはまた違った、というより終末感はもっとあったような、そんな日が続いていった。
それから一年ほど経った翌2012年2月22日に、山形交響楽団が当時音楽監督だった現芸術総監督の飯森範親氏の指揮で録音したブルックナーの交響曲第6番が発売された。
録音は2011年4月25日と翌26日。
十日ほど前に行われた第212回定期公演で演奏された後にセッション録音されたもの。
311当時、山形は最大震度5強の揺れにみまわれた。自分が横浜で経験したそれと同じかなり強い揺れだ。
海に面していなかったこと、廻りを高い山に囲まれていたこと、地盤が固かったことなどがあり、他の太平洋に面した東北の県に比べれば人的被害も、そして放射能の直接的な影響も小さかったが、それでも翌12日の山形交響楽団の定期公演は「建物への影響の点検に時間がかかるなどの理由から中止になった」(山形新聞)。
また多くの質的被害、停電やガソリン不足、そして新幹線の運行休止など起こったが、宮城県等がより壊滅的被害を受けた地区があったこともあり、早くも11日の夕方から宮城県への医療救護活動を行っている。
その後4月初旬に再度大きな地震があり一時復旧にブレーキがかかったものの、山形新幹線、そして山形空港という陸と空の交通機関は同月中旬にはしっかりと動いていた。特に山形空港は早い時期から機能していたことが幸いしたとのこと。
この中で山形交響楽団の定期公演が行われた。当時評論家の東条碩夫氏は大阪伊丹から空路山形へ飛びこの演奏会を聴きにきておりこのときの定期演奏会の事を書かれている。
そしてその十日程後にこのブルックナーが録音された。
.jpg)
さてこの演奏。
山形交響楽団はもともと弦の人数が三十人程しかいないため、他のブルックナーの録音のような分厚く迫力のある弦の響きはここでは感じられない。
ただ19世紀中ごろのブルックナーが交響曲を書いていたころの欧州のオケの多くは二管+弦が多くて四十人程だったというので、そういう意味では当時の規模に近いそれなのかもしれない。
全体的にはちょっとワルター指揮のコロンビア響のそれにも似たようにも感じられるが、こちらの方が神経の細やかな響きを弦が奏ででおり、弦が痩せてか細く苦し気に演奏しているようなそれも感じられない。
あえていうと、ちょっと水彩画的な弦の響きに、それよりも油絵のような色合いが濃く感じられる管楽器が、違和感なくひとつの響きの中でブレンドされているといっていいのかもしれない。これは録音の力やホールの特性もあると思う。
演奏会当日は東条氏のそれによると、かなりトランペットが強靭に吹いていたというけど、ここではそれはあまり感じられないが、それでも終楽章のコーダではなんとなくそれを彷彿とさせるものがあった。
それにしても人間的なものと自然の美しさのようなものが見事に調和された、じつに自然体のブルックナーだ。
ふつうここまで自然体にすぎると小味になってしまいかねないけど、オケの響きが端正ながら伸びやかにに歌っている事でそういう感じをうけないのだろう。
それはじつに瑞々しく清々しいとさえ感じられるほどだった。これにはもちろん指揮をされている飯森さんの力がかなりあることも強調しておきたい。
演奏時間は、
16:29、17:15、9:19、15:12
最後に、
自分はこれを聴いていて、ここにはすでに311の傷のようなものなく、むしろ復興に向かって力強く歩み出した東北の姿をみる思いの方が強く感じられた。
実際、まだ仙台フィルなどは定期公演を開ける状況ではなく、先の山形交響楽団による定期では苦境にある仙台フィルに対して募金が会場で行われていたという。
だけど繰り返すように、決して声高に叫ぶような演奏ではないにもかかわらず、ここにはそのような苦しみの中からも、間違いなく立ち上がろうとしている人たちの姿が自分には強く感じられた。それは6番という剛毅な力を内包した曲だったから余計そう感じられたからなのかもしれない。
とにかく今もまた苦しい時代だけど、この演奏を聴いていると、それでもまたいつかしっかりと立ち上がり前へ進むことができるということを確信させられる、そう強く感じさせられるこれはブルックナーという気が強くしました。
コロナが収まったら、今度はいつか山形交響楽団の演奏でブルックナーの2番を聴いてみたいです。
以上で〆。
日本にとって忘れられない一日だった。
自分は当時横浜の西区高島の帷子川にかかる万里橋の側でこの揺れに遭遇した。
時間は午後二時四十六分を少し過ぎたころだろう。
このとき自分「ついに東南海が来た」と思ったが、その後震源が東北と聞いて仰天した。
確かに宮城県沖で震度7クラスの地震が起きると警告されてはいたが、この揺れはそれとは規模があまりにも桁違いだった。
それからはまさに未曾有の体験の連続だった。そして福島原発の予想もしなかった崩壊。
今のコロナとはまた違った、というより終末感はもっとあったような、そんな日が続いていった。
それから一年ほど経った翌2012年2月22日に、山形交響楽団が当時音楽監督だった現芸術総監督の飯森範親氏の指揮で録音したブルックナーの交響曲第6番が発売された。
録音は2011年4月25日と翌26日。
十日ほど前に行われた第212回定期公演で演奏された後にセッション録音されたもの。
311当時、山形は最大震度5強の揺れにみまわれた。自分が横浜で経験したそれと同じかなり強い揺れだ。
海に面していなかったこと、廻りを高い山に囲まれていたこと、地盤が固かったことなどがあり、他の太平洋に面した東北の県に比べれば人的被害も、そして放射能の直接的な影響も小さかったが、それでも翌12日の山形交響楽団の定期公演は「建物への影響の点検に時間がかかるなどの理由から中止になった」(山形新聞)。
また多くの質的被害、停電やガソリン不足、そして新幹線の運行休止など起こったが、宮城県等がより壊滅的被害を受けた地区があったこともあり、早くも11日の夕方から宮城県への医療救護活動を行っている。
その後4月初旬に再度大きな地震があり一時復旧にブレーキがかかったものの、山形新幹線、そして山形空港という陸と空の交通機関は同月中旬にはしっかりと動いていた。特に山形空港は早い時期から機能していたことが幸いしたとのこと。
この中で山形交響楽団の定期公演が行われた。当時評論家の東条碩夫氏は大阪伊丹から空路山形へ飛びこの演奏会を聴きにきておりこのときの定期演奏会の事を書かれている。
そしてその十日程後にこのブルックナーが録音された。
.jpg)
さてこの演奏。
山形交響楽団はもともと弦の人数が三十人程しかいないため、他のブルックナーの録音のような分厚く迫力のある弦の響きはここでは感じられない。
ただ19世紀中ごろのブルックナーが交響曲を書いていたころの欧州のオケの多くは二管+弦が多くて四十人程だったというので、そういう意味では当時の規模に近いそれなのかもしれない。
全体的にはちょっとワルター指揮のコロンビア響のそれにも似たようにも感じられるが、こちらの方が神経の細やかな響きを弦が奏ででおり、弦が痩せてか細く苦し気に演奏しているようなそれも感じられない。
あえていうと、ちょっと水彩画的な弦の響きに、それよりも油絵のような色合いが濃く感じられる管楽器が、違和感なくひとつの響きの中でブレンドされているといっていいのかもしれない。これは録音の力やホールの特性もあると思う。
演奏会当日は東条氏のそれによると、かなりトランペットが強靭に吹いていたというけど、ここではそれはあまり感じられないが、それでも終楽章のコーダではなんとなくそれを彷彿とさせるものがあった。
それにしても人間的なものと自然の美しさのようなものが見事に調和された、じつに自然体のブルックナーだ。
ふつうここまで自然体にすぎると小味になってしまいかねないけど、オケの響きが端正ながら伸びやかにに歌っている事でそういう感じをうけないのだろう。
それはじつに瑞々しく清々しいとさえ感じられるほどだった。これにはもちろん指揮をされている飯森さんの力がかなりあることも強調しておきたい。
演奏時間は、
16:29、17:15、9:19、15:12
最後に、
自分はこれを聴いていて、ここにはすでに311の傷のようなものなく、むしろ復興に向かって力強く歩み出した東北の姿をみる思いの方が強く感じられた。
実際、まだ仙台フィルなどは定期公演を開ける状況ではなく、先の山形交響楽団による定期では苦境にある仙台フィルに対して募金が会場で行われていたという。
だけど繰り返すように、決して声高に叫ぶような演奏ではないにもかかわらず、ここにはそのような苦しみの中からも、間違いなく立ち上がろうとしている人たちの姿が自分には強く感じられた。それは6番という剛毅な力を内包した曲だったから余計そう感じられたからなのかもしれない。
とにかく今もまた苦しい時代だけど、この演奏を聴いていると、それでもまたいつかしっかりと立ち上がり前へ進むことができるということを確信させられる、そう強く感じさせられるこれはブルックナーという気が強くしました。
コロナが収まったら、今度はいつか山形交響楽団の演奏でブルックナーの2番を聴いてみたいです。
以上で〆。
ハイティンクのエルガーの1番 [クラシック百銘盤]
ハイティンクというと、今でこそベートーヴェン、ブルックナー、ブラームス、マーラーという独墺系の交響曲のスペシャリストというイメージがあるけど、実際は他の作曲家、特にイギリスの作曲家に対しても深い造詣をもっていた。
彼がいつからイギリス音楽に深い造詣をもったかは分からいないが、1960年代の彼はバルトークやドヴォルザークも演奏し、初来日の時はオランダの作曲家ヘンケマンスが二年前に作曲した「パルティータ」を演奏しているため、19世紀後半から20世紀半ばにかけて隆盛を誇った同時代のイギリスの作曲家に興味を抱いていたことはさして不思議なことではないと思う。
そんな彼がイギリスの名門、ロンドンフィルの首席指揮者になったのは1967年。同団にとって初のイギリス出身以外の首席となった。
彼はその二年後日本に同団初来日公演にも同行したが、ここではイギリスのオケと深い関係があるシベリウスが演奏されているが、イギリスの作曲家の交響曲は取りあけられていない。ただこれは当時の日本のイギリスの作曲家の交響曲に対する認知の極端な低さもあり、それを考慮してのものだった可能性もあるので、これをみてハイティンクがまだこの時期イギリス音楽に対してどうこうというのは早計かもしれない。
因みにこの年の秋、ハイティンクはコンセルトヘボウの演奏会を中断しなければならない、いわゆる「くるみ割り人形」事件に巻き込まれている。これはハイティンクと当時のコンセルトヘボウの芸術監督のプログラム選定が、あまりにも保守的すぎるといったことに対する一部勢力の抗議によるもので、その時その勢力からは同団の指揮者にブルーノ・マデルナも就任させろという要求まであったという。
後にこれは沈静化したが、これは当時大きな話題と問題になった。尚、ハイティンクがあの武満を録音したのはこの翌月、そして一緒に収録されているメシアンはこの年の二月に演奏されている。
閑話休題
ハイティンクとロンドンフィルの関係はひじょうに良好で、この関係は十シーズン以上も続いた。そして1974年から1976年にかけて、1977年のベートーヴェン没後150年にあわせ自ら初のベートーヴェン交響曲全集を録音した。
だがこの時期いちばん同オケと活発に録音していのはじつはハイティンクではなく、当時同団の会長に就任していたエードリアン・ボールトだった。
彼はこの時期、ブラームス、ワーグナー、チャイコフスキー等を中心とした作品を大量かつ集中的に録音していた。そしてそれらはハイティンクのレパートリーと重なるものがあった。
(余談ですが1976年にはヨッフムもロンドンフィルでブラームスの交響曲全集を録音している)
ここで面白いのは、ボールトがこれらの曲を録音している近しい時期に、ハイティンクもまたコンセルトヘボウで、これらの作曲家の曲を録音しているということ。シューベルトのグレイト、ワーグナーの管弦楽曲、ブラームスの管弦楽曲と交響曲全集がそれ。
(尚、ボールトはブラームスの3番を含む一部の曲はロンドンフィルではなくロンドン響と録音をしています)
それを思うとこの状況下、ハイティンクがボールトの録音をまったく意識してなかったということはないと思うけど、なかなか興味深い関係をこの時期この二人がもっていたことは偶然の部分があるとはいえ確かだと思う。
そんな中、デッカがかつてこのオケと関係がありイギリスでも活躍しているショルティに、じつに17年ぶりにロンドンフィルと録音するという話をもちこんだ。しかも曲がエルガーの交響曲第1番。
これはハイティンクにとってもあれだったかもしれないが、より強く反応したのはボールトだったようだ。
ショルティが1972年の1番に続き、1975年の2月にエルガーの2番を録音すると、ボールトはその年の秋から翌年にかけ同曲を、そして1976年の秋には1番をそれぞれロンドンフィルと録音した。
(また1978年の2月にショルティが「惑星」を録音すると、前年秋から演奏会から遠ざかっていたボールトがその三か月後に同曲五度目の録音を挙行し、12月にパリーの作品を録音している。翌年ショルティがロンドンフィルの首席になるが、それ以降ボールトは録音を一切行っていない。ボールトが引退を正式表明したのは1981年)
※ハイティンクもロンドンフィルと「惑星」を録音しているが、時期は1970年3月と前者とはかなり離れている。
当然ハイティンクはこの動きをしっかりとみているが、結果的に二人の全くタイプの違う名指揮者によるエルガーの二つの交響曲全集(3番の補筆がはじまったのは1990年代)が、よりによって自分の手兵を使って当時最高レベルの録音で完成されてしまったため、ハイティンクがエルガーの交響曲にこの時期手を出すことはなかった。
その後ハイティンクはロンドンフィルをはなれたが、その後もグラインドボーン音楽祭等での関係で繋がりを持ち続け、1984年からヴォーン=ウィリアムズの交響曲の録音を、テンシュテットが首席指揮者になったロンドンフィルと開始した。これは結局マズアが同団に赴任する直前まで、じつに十年以上続くことになる。
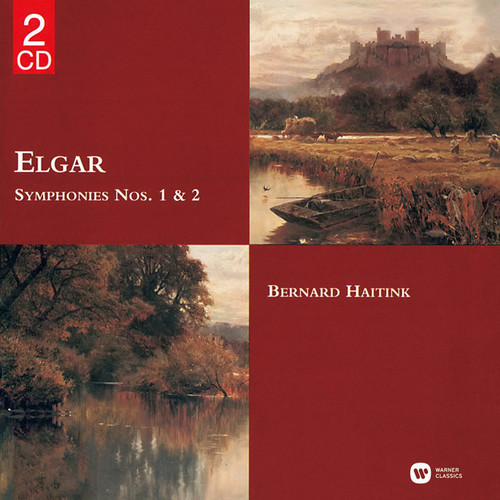
自分は以上のことからハイティンクがエルガーを録音、しかもEMIから発売と当時聞いた時、オケを確かめもせずロンドンフィルだとばかり思いこんでいた。
だがオケは意外にもフィルハーモニア管弦楽団だった。録音はボールトが逝去した二か月後の1983年4月から1984年春にかけて行われた。この当時フィルハーモニアはムーティがフィラデルフィアに去り、シノーポリが赴任する前の空白期間だった。
そのせいかハイティンクのこのエルガーは、ロンドンフィルを指揮しなかったことで、ショルティやボールトと比較されることも、必要以上に意識することもなく、そして当時首席が空席だったこともあり、誰にも気兼ねせず伸び伸びと自分のやりたよいように演奏している。
この中で自分は2番についてはやや疎遠な部分があるので1番のみよく聴いているけど、ボールトのような壮麗さや、ショルティのようなメリハリの利いたスペクタクルともいえるものとは違って、ややくすんだ、だけどロンドンフィルの時よりも明るく、そして構えの大きなバランスのとれた、この時期のハイティンクがブルックナーやマーラーでみせるそれがここでも展開されている。
また今回のこれはデジタル録音ということもあり、音の立ち上がり、特にティンパニーの粒立ちがかなりしっかりとらえられていて、これが小気味よさと力強さの両方を兼ね備えた響きを全体にもたらしている。
しかしいちばんの特徴は大太鼓とシンバルだろう。
この交響曲の好き嫌いが最も分かれるとしたら、この大太鼓やシンバルがときおりドンシャンドンシャンと鳴り響く部分だろう。
この独特のそれは、独墺系の交響曲ではあまり聴かれないもので、正直聴く人にとってはけたたましい、もしくは耳障りで喧騒にすぎると聴こえるだろう。自分も最初ショルティの指揮でこれを初めて聴いた時、やはりちょっとついていけないように感じられたものでした。
だがハイティンクのそれでは大太鼓はティンパニーの響きの延長感が強く、シンバルも鳴ってはいるが、録音のせいか奥に退いた感じで響いていて、シンバル独特のあの堅い質感があまり感じられない。砕いていってしまうと、大太鼓とシンバルの存在感が極めて希薄。
そのため通常イメージとてしある「エルガーらしさ」なるものが後退したともいえるけど、ハイティンクのマーラーが刺激的要素を必要以上に強調しないそれが、この曲でもあらわれたことを思うと、ハイティンクの指揮の特徴や語法を尊重した場合当然の結果といえるし、むしろこのやり方をみとめればこの演奏は大成功の部類といえるかもしれない。
ただこのため聴きようによってはイギリス風ブルックナーにも聴こえないでもないが、以上の理由から自分はこれを失敗とは思ってないし、むしろかつて自分の手兵上で繰り広げられた二人の指揮者のエルガー合戦の事を思うと、このどちらにも組しない、しかもいかにもこの時期のハイティンクらしいしっかりとした自らのエルガー像を確立したハイティンクのそれは、いくら称賛してもいいと自分は思っている。
素晴らしい同曲屈指の名演ですが、それと同時にエルガーのこの曲にいまいち感を持っている人にはぜひ聴いてほしい演奏です。
演奏時間は、
21:59、06:50、12:35、12:28
因みにハイティンクはその後ロンドンではロンドンフィルとロイヤルオペラ、そしてその後ロンドン響と強く繋がりをもち、自身三度目のベートーヴェン全集をロンドン響と録音していますがフィルハーモニアとはどうだったんでしょう。
けっこうハイティンクは客演や録音する時のオケのトップとの相性に煩いので、もしフィルハーモニーと疎遠になってしまったとしたら、シノーポリとはちょっとあれだったのかもしれません。
以上で〆
彼がいつからイギリス音楽に深い造詣をもったかは分からいないが、1960年代の彼はバルトークやドヴォルザークも演奏し、初来日の時はオランダの作曲家ヘンケマンスが二年前に作曲した「パルティータ」を演奏しているため、19世紀後半から20世紀半ばにかけて隆盛を誇った同時代のイギリスの作曲家に興味を抱いていたことはさして不思議なことではないと思う。
そんな彼がイギリスの名門、ロンドンフィルの首席指揮者になったのは1967年。同団にとって初のイギリス出身以外の首席となった。
彼はその二年後日本に同団初来日公演にも同行したが、ここではイギリスのオケと深い関係があるシベリウスが演奏されているが、イギリスの作曲家の交響曲は取りあけられていない。ただこれは当時の日本のイギリスの作曲家の交響曲に対する認知の極端な低さもあり、それを考慮してのものだった可能性もあるので、これをみてハイティンクがまだこの時期イギリス音楽に対してどうこうというのは早計かもしれない。
因みにこの年の秋、ハイティンクはコンセルトヘボウの演奏会を中断しなければならない、いわゆる「くるみ割り人形」事件に巻き込まれている。これはハイティンクと当時のコンセルトヘボウの芸術監督のプログラム選定が、あまりにも保守的すぎるといったことに対する一部勢力の抗議によるもので、その時その勢力からは同団の指揮者にブルーノ・マデルナも就任させろという要求まであったという。
後にこれは沈静化したが、これは当時大きな話題と問題になった。尚、ハイティンクがあの武満を録音したのはこの翌月、そして一緒に収録されているメシアンはこの年の二月に演奏されている。
閑話休題
ハイティンクとロンドンフィルの関係はひじょうに良好で、この関係は十シーズン以上も続いた。そして1974年から1976年にかけて、1977年のベートーヴェン没後150年にあわせ自ら初のベートーヴェン交響曲全集を録音した。
だがこの時期いちばん同オケと活発に録音していのはじつはハイティンクではなく、当時同団の会長に就任していたエードリアン・ボールトだった。
彼はこの時期、ブラームス、ワーグナー、チャイコフスキー等を中心とした作品を大量かつ集中的に録音していた。そしてそれらはハイティンクのレパートリーと重なるものがあった。
(余談ですが1976年にはヨッフムもロンドンフィルでブラームスの交響曲全集を録音している)
ここで面白いのは、ボールトがこれらの曲を録音している近しい時期に、ハイティンクもまたコンセルトヘボウで、これらの作曲家の曲を録音しているということ。シューベルトのグレイト、ワーグナーの管弦楽曲、ブラームスの管弦楽曲と交響曲全集がそれ。
(尚、ボールトはブラームスの3番を含む一部の曲はロンドンフィルではなくロンドン響と録音をしています)
それを思うとこの状況下、ハイティンクがボールトの録音をまったく意識してなかったということはないと思うけど、なかなか興味深い関係をこの時期この二人がもっていたことは偶然の部分があるとはいえ確かだと思う。
そんな中、デッカがかつてこのオケと関係がありイギリスでも活躍しているショルティに、じつに17年ぶりにロンドンフィルと録音するという話をもちこんだ。しかも曲がエルガーの交響曲第1番。
これはハイティンクにとってもあれだったかもしれないが、より強く反応したのはボールトだったようだ。
ショルティが1972年の1番に続き、1975年の2月にエルガーの2番を録音すると、ボールトはその年の秋から翌年にかけ同曲を、そして1976年の秋には1番をそれぞれロンドンフィルと録音した。
(また1978年の2月にショルティが「惑星」を録音すると、前年秋から演奏会から遠ざかっていたボールトがその三か月後に同曲五度目の録音を挙行し、12月にパリーの作品を録音している。翌年ショルティがロンドンフィルの首席になるが、それ以降ボールトは録音を一切行っていない。ボールトが引退を正式表明したのは1981年)
※ハイティンクもロンドンフィルと「惑星」を録音しているが、時期は1970年3月と前者とはかなり離れている。
当然ハイティンクはこの動きをしっかりとみているが、結果的に二人の全くタイプの違う名指揮者によるエルガーの二つの交響曲全集(3番の補筆がはじまったのは1990年代)が、よりによって自分の手兵を使って当時最高レベルの録音で完成されてしまったため、ハイティンクがエルガーの交響曲にこの時期手を出すことはなかった。
その後ハイティンクはロンドンフィルをはなれたが、その後もグラインドボーン音楽祭等での関係で繋がりを持ち続け、1984年からヴォーン=ウィリアムズの交響曲の録音を、テンシュテットが首席指揮者になったロンドンフィルと開始した。これは結局マズアが同団に赴任する直前まで、じつに十年以上続くことになる。
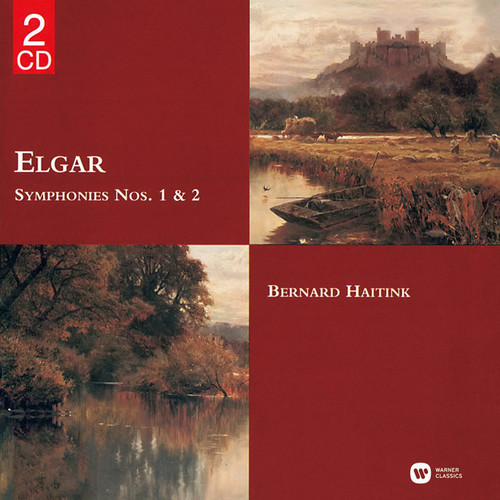
自分は以上のことからハイティンクがエルガーを録音、しかもEMIから発売と当時聞いた時、オケを確かめもせずロンドンフィルだとばかり思いこんでいた。
だがオケは意外にもフィルハーモニア管弦楽団だった。録音はボールトが逝去した二か月後の1983年4月から1984年春にかけて行われた。この当時フィルハーモニアはムーティがフィラデルフィアに去り、シノーポリが赴任する前の空白期間だった。
そのせいかハイティンクのこのエルガーは、ロンドンフィルを指揮しなかったことで、ショルティやボールトと比較されることも、必要以上に意識することもなく、そして当時首席が空席だったこともあり、誰にも気兼ねせず伸び伸びと自分のやりたよいように演奏している。
この中で自分は2番についてはやや疎遠な部分があるので1番のみよく聴いているけど、ボールトのような壮麗さや、ショルティのようなメリハリの利いたスペクタクルともいえるものとは違って、ややくすんだ、だけどロンドンフィルの時よりも明るく、そして構えの大きなバランスのとれた、この時期のハイティンクがブルックナーやマーラーでみせるそれがここでも展開されている。
また今回のこれはデジタル録音ということもあり、音の立ち上がり、特にティンパニーの粒立ちがかなりしっかりとらえられていて、これが小気味よさと力強さの両方を兼ね備えた響きを全体にもたらしている。
しかしいちばんの特徴は大太鼓とシンバルだろう。
この交響曲の好き嫌いが最も分かれるとしたら、この大太鼓やシンバルがときおりドンシャンドンシャンと鳴り響く部分だろう。
この独特のそれは、独墺系の交響曲ではあまり聴かれないもので、正直聴く人にとってはけたたましい、もしくは耳障りで喧騒にすぎると聴こえるだろう。自分も最初ショルティの指揮でこれを初めて聴いた時、やはりちょっとついていけないように感じられたものでした。
だがハイティンクのそれでは大太鼓はティンパニーの響きの延長感が強く、シンバルも鳴ってはいるが、録音のせいか奥に退いた感じで響いていて、シンバル独特のあの堅い質感があまり感じられない。砕いていってしまうと、大太鼓とシンバルの存在感が極めて希薄。
そのため通常イメージとてしある「エルガーらしさ」なるものが後退したともいえるけど、ハイティンクのマーラーが刺激的要素を必要以上に強調しないそれが、この曲でもあらわれたことを思うと、ハイティンクの指揮の特徴や語法を尊重した場合当然の結果といえるし、むしろこのやり方をみとめればこの演奏は大成功の部類といえるかもしれない。
ただこのため聴きようによってはイギリス風ブルックナーにも聴こえないでもないが、以上の理由から自分はこれを失敗とは思ってないし、むしろかつて自分の手兵上で繰り広げられた二人の指揮者のエルガー合戦の事を思うと、このどちらにも組しない、しかもいかにもこの時期のハイティンクらしいしっかりとした自らのエルガー像を確立したハイティンクのそれは、いくら称賛してもいいと自分は思っている。
素晴らしい同曲屈指の名演ですが、それと同時にエルガーのこの曲にいまいち感を持っている人にはぜひ聴いてほしい演奏です。
演奏時間は、
21:59、06:50、12:35、12:28
因みにハイティンクはその後ロンドンではロンドンフィルとロイヤルオペラ、そしてその後ロンドン響と強く繋がりをもち、自身三度目のベートーヴェン全集をロンドン響と録音していますがフィルハーモニアとはどうだったんでしょう。
けっこうハイティンクは客演や録音する時のオケのトップとの相性に煩いので、もしフィルハーモニーと疎遠になってしまったとしたら、シノーポリとはちょっとあれだったのかもしれません。
以上で〆
ロストロポーヴィチとボールトのドヴォルザーク [クラシック百銘盤]
ロストロポーヴィチがソロをとったドヴォルザークのチェロ協奏曲は、ラフリンから小澤までじつに七種類あるという。
特に有名なのはカラヤンとのもので、次いで小澤やターリヒのものがよく知られ、そして聴かれているようです。
そんな中で1957年4月にロストロポーヴィチが初めて西側で、しかもステレオで録音したのがこのエードリアン・ボールトとの共演のもの。

だがじつはこの録音、とても気になっている事がある。
それはオケがロイヤル・フィルハーモニーだということ。
自分は最初これがロンドンフィルだとばかり思っていたので、ロイヤルフィルと分かった時は正直かなり驚いた。
ボールトが指揮するオーケストラというと、まずは1924年に初代の首席指揮者となったBBC交響楽団、第二次大戦後はロンドンフィル、その後ロンドン響やニュー・フィルハーモニアと録音が増え、晩年はロンドンフィルとBBCがまた増えるというかんじだった。
それを考えるとこのドヴォルザーク録音時、ボールトが指揮をするのなら首席指揮者をしていたロンドンフィルと録音をするのがふつうなのだが、なぜかオケは前述したとおりロイヤルフィル。しかもその時のロイヤルフィルの指揮者は、ボールトと決して良好な関係ではなかったビーチャムだから猶更だ。
ここからは自分の勝手な想像だけど、おそらく当初は前年彼と共演し録音もしたマルコム・サージェントがこのセッションの指揮も担当するはずだったのが、何らかの理由で不可能となり、急遽ボールトにそれがまわってきたのではないかという気がした。
ロストロポーヴィチは当時まだ三十歳になったばかりだし、ソ連の当時の事を思うと指揮者に希望とかそういうものを言える立場にはなかったので、彼の希望によりボールトが登場したという可能性は低いが、彼がこの時それとなく誰だったらいいのかと聞かれ、前年ソ連にロンドンフィルととともに訪問し好評を博したボールトに好印象をもっていたとしたら、その名前を出したかもしれない。
とにかく最初からこの組み合わせありきで組まれたとはちょっと思えない気が自分にはしている。
ただそれにもかかわらずこの演奏はいい。
録音はステレオ初期のせいか弦の横の拡がりがあまりなかったり、ロイヤルフィルというあまり縁のない、それこそボールトにとってはある意味アウェイな状況であったにもかかわらず、彼らしい端正ながら瑞々しい響きと味わい深さが素晴らしく、しっかりとした聴き応えのあるものとなっているが、ドヴォルザークよりもブラームス風の佇まいをみせているのはボールトらしいというべきか。
ロストロポーヴィチもその響きの中、五年前のターリヒとの共演とまた違う、やや寛いだ感のある演奏を展開している。
演奏時間は、14:43、11:46、12:45。
かつてLP時代はEMIのセラフィムのシリーズから廉価盤として発売されていたこともあるけど、最近は国内盤ではみかけなくなってしまった。
これも時代かもしれないけど、もう少しだけ知られてほしい名盤のひとつ。
特に有名なのはカラヤンとのもので、次いで小澤やターリヒのものがよく知られ、そして聴かれているようです。
そんな中で1957年4月にロストロポーヴィチが初めて西側で、しかもステレオで録音したのがこのエードリアン・ボールトとの共演のもの。

だがじつはこの録音、とても気になっている事がある。
それはオケがロイヤル・フィルハーモニーだということ。
自分は最初これがロンドンフィルだとばかり思っていたので、ロイヤルフィルと分かった時は正直かなり驚いた。
ボールトが指揮するオーケストラというと、まずは1924年に初代の首席指揮者となったBBC交響楽団、第二次大戦後はロンドンフィル、その後ロンドン響やニュー・フィルハーモニアと録音が増え、晩年はロンドンフィルとBBCがまた増えるというかんじだった。
それを考えるとこのドヴォルザーク録音時、ボールトが指揮をするのなら首席指揮者をしていたロンドンフィルと録音をするのがふつうなのだが、なぜかオケは前述したとおりロイヤルフィル。しかもその時のロイヤルフィルの指揮者は、ボールトと決して良好な関係ではなかったビーチャムだから猶更だ。
ここからは自分の勝手な想像だけど、おそらく当初は前年彼と共演し録音もしたマルコム・サージェントがこのセッションの指揮も担当するはずだったのが、何らかの理由で不可能となり、急遽ボールトにそれがまわってきたのではないかという気がした。
ロストロポーヴィチは当時まだ三十歳になったばかりだし、ソ連の当時の事を思うと指揮者に希望とかそういうものを言える立場にはなかったので、彼の希望によりボールトが登場したという可能性は低いが、彼がこの時それとなく誰だったらいいのかと聞かれ、前年ソ連にロンドンフィルととともに訪問し好評を博したボールトに好印象をもっていたとしたら、その名前を出したかもしれない。
とにかく最初からこの組み合わせありきで組まれたとはちょっと思えない気が自分にはしている。
ただそれにもかかわらずこの演奏はいい。
録音はステレオ初期のせいか弦の横の拡がりがあまりなかったり、ロイヤルフィルというあまり縁のない、それこそボールトにとってはある意味アウェイな状況であったにもかかわらず、彼らしい端正ながら瑞々しい響きと味わい深さが素晴らしく、しっかりとした聴き応えのあるものとなっているが、ドヴォルザークよりもブラームス風の佇まいをみせているのはボールトらしいというべきか。
ロストロポーヴィチもその響きの中、五年前のターリヒとの共演とまた違う、やや寛いだ感のある演奏を展開している。
演奏時間は、14:43、11:46、12:45。
かつてLP時代はEMIのセラフィムのシリーズから廉価盤として発売されていたこともあるけど、最近は国内盤ではみかけなくなってしまった。
これも時代かもしれないけど、もう少しだけ知られてほしい名盤のひとつ。
ノイマンの「わが祖国」 [クラシック百銘盤]
今年(2020)9月に生誕百年を迎えるチェコの名指揮者ヴァーツラフ・ノイマン。
1969年の初来日から最後の来日となった1991年迄、チェコフィルだけでなく、日本のオーケストラに客演するなど、当時日本ではお馴染みの指揮者だった。
だがその名声が確立するのは来日してすぐというわけではなかった。
1969年の初来日はそこそこ好評だったものの、十年前のアンチェルやスロヴァークが率いて行われた初来日公演程の話題とはならなかった。
これには前年夏に起きたチェコ事件のそれが影を落としていたのではという意見もみられたが、またそれはオケだけでなく、その件を機に名門ゲヴァントハウスを辞任しチェコに戻ったノイマンにも言えることだったのかもしれない。
ノイマンはこの初来日前に行われたプラハの春では「わが祖国」の指揮をとり、それは三年程続いたし、1970年代に入るとチェコフィル初のドヴォルザーク交響曲全集を録音した。
また当時彼はテルデックとも契約していて、ドヴォルザークのスラブ舞曲全曲やスラブ狂詩曲全曲、さらにフチークの作品集等を同レーベルに録音しており、1972年にはミュンヘンフィルの初来日公演に、健康に不安を抱えるケンペに代わり帯同が予定されるなど、その活躍が国際的なものになりつつあった。
だが、このミュンヘンフィルとの来日公演はノイマンの出国許可がチェコから降りずノイマンの再来日はなくなった。そしてこの年のプラハの春の「わが祖国」はノイマンではなくコシュラーになった。
これから後しばらくノイマンのチェコフィル以外との来日公演は無くなり、テルデックとも契約は終了、スプラフォン一本となったが、この頃ノイマンは自分についての不安を口にしていたという話を聞いたことがある。
やはり同じソ連傘下の共産圏体制下ということで、ライプツィヒを抗議の辞任をしたノイマンにはいろいろと当局からきつい縛り等があったようだ。
そんなノイマンが再来日したのは1974年6月。
この年のプラハの春は前年に続きノイマンが「わが祖国」に復帰したが、この来日公演終盤であのFM東京が主催した「わが祖国」の公開放送が行われ、その入場希望の応募ハガキが十万通以上という大騒ぎになった。
これが翌1975年春のこのコンビによる「わが祖国」の正式なセッション録音実現に繋がり、同年10月には当時二枚組のクラシック音楽の新譜LPとしては破格の3500円という価格で発売され、大きな話題と絶賛を博し、セールスもかなり良かったとか
当時「わが祖国」の音盤は、このノイマン盤が発売される前はボストン響を指揮したクーベリック盤がベストと評価され、しかもこの年の5月にはそのクーベリックがバイエルン放送と来日し、この曲を文化会館で指揮したそれがテレビやFMで放送されていたので、その評価はさらに高まっていた。
そのためこの盤が出てからは、LP時代はこの二人の「わが祖国」が当時はベスト盤でありスタンダードといわれたものでした。
もっともノイマンの場合、前年の来日公演初日がテレビで放送されたそれがオケも指揮者も本調子でなく、しかも雑誌で酷評されるは、放送では「チェコフィルは来るたびに指揮者がつまらなくなる。オケの弦もまるで(悪い意味で)生の野菜をバリバリ食わされているようだ」と酷評されるはと散々で、このアルバムはそんなことで不本意に広まった汚名を返上する起死回生の一発となったようです。
(尚、自分が「わが祖国」を初めて全曲聴いたのがこのノイマン盤であったため、この1975年盤は自分にとって「わが祖国」のひとつのスタンダード+刷り込みとなりました)
ところでそんなノイマンの「わが祖国」は全部で七種類ある。
1967年ゲヴァントハウス
1975年チェコフィル
この二つが正規のセッション録音だがそれ以外に、
1974年の先にあげたチェコフィルとの日本での公開放送のもの。
1978年のN響定期公演客演時のライブ。
1982年の日本公演における「わが祖国」初演百周年ライブ。
というものがある。この三つ目も発売時に話題になり、また演奏会そのものもすぐに売り切れた話題の公演でしたが、今考えると同曲初演百年という記念すべき日に、なぜチェコフィルがプラハではなく日本にいたのかというのが自分には未だに謎で、当時のチェコ当局がプラハでこの曲の百周年公演を嫌ってわざとツアーを設けたのではと個人的には勘繰っています。
そしてさらにもう二つ。これらはじつはあまり知られていないが、
ひとつは1981年のプラハの春におけるライブをレーザーディスクのみで発売したもので、これは確か未だにCDとしては発売になっていないようです。
そしてもうひとつが1972年という、ノイマンにとっては穏やかではなかった時期に、プラハの1975年の録音と同じドヴォルザーク・ホールで録音さたれもの。
ただし録音したのはスプラフォンではなく、同じ国営レーベルのひとつPanton。
また1975年盤が六日間かけてじっくり丁寧に録音されたのに対し、こちらは放送用録音もの(ただし無観客)らしくそんなに日にちをかけて録音したものではないように思われることが違う点。
ただ自分の持っている当時の東芝EMIから出ていた国内盤では、最後ちょっと音に痛みがわずかに感じられるところがあるものの、音質はちゃんとした良好なステレオで収録されているので、放送用録音であったとしてもかなり整った環境で収録されたものと思われます。
じつはこの72年盤がなかなか侮りがたいものとなっている。
75年盤は、弦を中心としたオケの音がホールの響きと美しくブレンドされ、極めてオーソドックスなスタイルと相まって、素朴ながらも音楽細工のような美しい佇まいをもった、地酒的とも国宝的ともいえる「わが祖国」そのものを味わう最高の演奏にまで昇華された名演となっていたが、こちらの72年盤はそれとはかなり様相が違い、管楽器、特に木管の表情がかなりハッキリ聴きとれるし、ティンパニーの打ち込みもより明確で、ハープの響きも明晰にとらえられている。
そのためオーソドックスであることや基本線は変わらないものの、より強く音が響いている印象があり、そのことによりオケのここという時の立ち上がりが75年盤より明確に感じられる。また演奏にわずかながら75年盤より勢いがあるように感じられるせいか、ライブ感覚的なものが多少そこにはあり、そのためノイマンの82年盤にもどことなく繋がるようなものも感じられるし、また同時期にノイマンがチェコフィルと録音した、ドヴォルザークの交響曲全集やスラブ舞曲全曲にも相通じる活き活きとしたそれが感じられる。
演奏時間は72年盤の方が75年盤より「ヴィシェフラド」が多少かかっている以外は他の五曲とも72年盤の方がやや速いものの、全体では一分ほど72年盤の方が速いという程度にその差はとどまっている。
だが「シャールカ」の序盤で聴かれる木管の表情など75年盤と大きく印象が異なるところもあり、細部では72年盤の方が75年盤より表情の変化が多様な部分散見されるため、演奏時間以上にその差が自分は感じられた。
そして何よりも75年盤がノイマンとチェコフィルの理想的な共同作業というつくりなのに対し、72年のそれはよりノイマンがチェコフィルを強くリードしているように感じられるという気が強くした。
そういう意味でもこの72年盤はもう少し評価され、そして市場に出回ってもいいような気がする。
因みに自分のこの感想は前述したように国内盤と1991年に出回ったものに対してであって、同年、もしくは1980年代半ばに出たPantonの輸入盤のものではない。というかPanton盤は未聴なので、国内盤と同じか違うのか確認していません。
もしもPanton盤の音質がこれとまた違ったら、印象もまた変わるのかもしれません。
といったところで唐突に〆です。
下のそれは比較的最近も中古等でみかけるPanton盤のCDジャケ。

1969年の初来日から最後の来日となった1991年迄、チェコフィルだけでなく、日本のオーケストラに客演するなど、当時日本ではお馴染みの指揮者だった。
だがその名声が確立するのは来日してすぐというわけではなかった。
1969年の初来日はそこそこ好評だったものの、十年前のアンチェルやスロヴァークが率いて行われた初来日公演程の話題とはならなかった。
これには前年夏に起きたチェコ事件のそれが影を落としていたのではという意見もみられたが、またそれはオケだけでなく、その件を機に名門ゲヴァントハウスを辞任しチェコに戻ったノイマンにも言えることだったのかもしれない。
ノイマンはこの初来日前に行われたプラハの春では「わが祖国」の指揮をとり、それは三年程続いたし、1970年代に入るとチェコフィル初のドヴォルザーク交響曲全集を録音した。
また当時彼はテルデックとも契約していて、ドヴォルザークのスラブ舞曲全曲やスラブ狂詩曲全曲、さらにフチークの作品集等を同レーベルに録音しており、1972年にはミュンヘンフィルの初来日公演に、健康に不安を抱えるケンペに代わり帯同が予定されるなど、その活躍が国際的なものになりつつあった。
だが、このミュンヘンフィルとの来日公演はノイマンの出国許可がチェコから降りずノイマンの再来日はなくなった。そしてこの年のプラハの春の「わが祖国」はノイマンではなくコシュラーになった。
これから後しばらくノイマンのチェコフィル以外との来日公演は無くなり、テルデックとも契約は終了、スプラフォン一本となったが、この頃ノイマンは自分についての不安を口にしていたという話を聞いたことがある。
やはり同じソ連傘下の共産圏体制下ということで、ライプツィヒを抗議の辞任をしたノイマンにはいろいろと当局からきつい縛り等があったようだ。
そんなノイマンが再来日したのは1974年6月。
この年のプラハの春は前年に続きノイマンが「わが祖国」に復帰したが、この来日公演終盤であのFM東京が主催した「わが祖国」の公開放送が行われ、その入場希望の応募ハガキが十万通以上という大騒ぎになった。
これが翌1975年春のこのコンビによる「わが祖国」の正式なセッション録音実現に繋がり、同年10月には当時二枚組のクラシック音楽の新譜LPとしては破格の3500円という価格で発売され、大きな話題と絶賛を博し、セールスもかなり良かったとか
当時「わが祖国」の音盤は、このノイマン盤が発売される前はボストン響を指揮したクーベリック盤がベストと評価され、しかもこの年の5月にはそのクーベリックがバイエルン放送と来日し、この曲を文化会館で指揮したそれがテレビやFMで放送されていたので、その評価はさらに高まっていた。
そのためこの盤が出てからは、LP時代はこの二人の「わが祖国」が当時はベスト盤でありスタンダードといわれたものでした。
もっともノイマンの場合、前年の来日公演初日がテレビで放送されたそれがオケも指揮者も本調子でなく、しかも雑誌で酷評されるは、放送では「チェコフィルは来るたびに指揮者がつまらなくなる。オケの弦もまるで(悪い意味で)生の野菜をバリバリ食わされているようだ」と酷評されるはと散々で、このアルバムはそんなことで不本意に広まった汚名を返上する起死回生の一発となったようです。
(尚、自分が「わが祖国」を初めて全曲聴いたのがこのノイマン盤であったため、この1975年盤は自分にとって「わが祖国」のひとつのスタンダード+刷り込みとなりました)
ところでそんなノイマンの「わが祖国」は全部で七種類ある。
1967年ゲヴァントハウス
1975年チェコフィル
この二つが正規のセッション録音だがそれ以外に、
1974年の先にあげたチェコフィルとの日本での公開放送のもの。
1978年のN響定期公演客演時のライブ。
1982年の日本公演における「わが祖国」初演百周年ライブ。
というものがある。この三つ目も発売時に話題になり、また演奏会そのものもすぐに売り切れた話題の公演でしたが、今考えると同曲初演百年という記念すべき日に、なぜチェコフィルがプラハではなく日本にいたのかというのが自分には未だに謎で、当時のチェコ当局がプラハでこの曲の百周年公演を嫌ってわざとツアーを設けたのではと個人的には勘繰っています。
そしてさらにもう二つ。これらはじつはあまり知られていないが、
ひとつは1981年のプラハの春におけるライブをレーザーディスクのみで発売したもので、これは確か未だにCDとしては発売になっていないようです。
そしてもうひとつが1972年という、ノイマンにとっては穏やかではなかった時期に、プラハの1975年の録音と同じドヴォルザーク・ホールで録音さたれもの。
ただし録音したのはスプラフォンではなく、同じ国営レーベルのひとつPanton。
また1975年盤が六日間かけてじっくり丁寧に録音されたのに対し、こちらは放送用録音もの(ただし無観客)らしくそんなに日にちをかけて録音したものではないように思われることが違う点。
ただ自分の持っている当時の東芝EMIから出ていた国内盤では、最後ちょっと音に痛みがわずかに感じられるところがあるものの、音質はちゃんとした良好なステレオで収録されているので、放送用録音であったとしてもかなり整った環境で収録されたものと思われます。
じつはこの72年盤がなかなか侮りがたいものとなっている。
75年盤は、弦を中心としたオケの音がホールの響きと美しくブレンドされ、極めてオーソドックスなスタイルと相まって、素朴ながらも音楽細工のような美しい佇まいをもった、地酒的とも国宝的ともいえる「わが祖国」そのものを味わう最高の演奏にまで昇華された名演となっていたが、こちらの72年盤はそれとはかなり様相が違い、管楽器、特に木管の表情がかなりハッキリ聴きとれるし、ティンパニーの打ち込みもより明確で、ハープの響きも明晰にとらえられている。
そのためオーソドックスであることや基本線は変わらないものの、より強く音が響いている印象があり、そのことによりオケのここという時の立ち上がりが75年盤より明確に感じられる。また演奏にわずかながら75年盤より勢いがあるように感じられるせいか、ライブ感覚的なものが多少そこにはあり、そのためノイマンの82年盤にもどことなく繋がるようなものも感じられるし、また同時期にノイマンがチェコフィルと録音した、ドヴォルザークの交響曲全集やスラブ舞曲全曲にも相通じる活き活きとしたそれが感じられる。
演奏時間は72年盤の方が75年盤より「ヴィシェフラド」が多少かかっている以外は他の五曲とも72年盤の方がやや速いものの、全体では一分ほど72年盤の方が速いという程度にその差はとどまっている。
だが「シャールカ」の序盤で聴かれる木管の表情など75年盤と大きく印象が異なるところもあり、細部では72年盤の方が75年盤より表情の変化が多様な部分散見されるため、演奏時間以上にその差が自分は感じられた。
そして何よりも75年盤がノイマンとチェコフィルの理想的な共同作業というつくりなのに対し、72年のそれはよりノイマンがチェコフィルを強くリードしているように感じられるという気が強くした。
そういう意味でもこの72年盤はもう少し評価され、そして市場に出回ってもいいような気がする。
因みに自分のこの感想は前述したように国内盤と1991年に出回ったものに対してであって、同年、もしくは1980年代半ばに出たPantonの輸入盤のものではない。というかPanton盤は未聴なので、国内盤と同じか違うのか確認していません。
もしもPanton盤の音質がこれとまた違ったら、印象もまた変わるのかもしれません。
といったところで唐突に〆です。
下のそれは比較的最近も中古等でみかけるPanton盤のCDジャケ。