アンドレア・バッティストーニ指揮東京フィルハーモニー交響楽団を聴く。(11/17) [演奏会いろいろ]

2023年11月16日(木)
東京オペラシティ コンサートホール 19:00開演
曲目:
チャイコフスキー:幻想序曲『テンペスト』op.18
チャイコフスキー:ロココの主題による変奏曲 op.33
チャイコフスキー:幻想序曲『ハムレット』op.67a
チャイコフスキー:幻想序曲『ロメオとジュリエット』(第3稿)
チェロ:佐藤晴真
指揮:アンドレア・バッティストーニ
チャイコフスキー没後130年を記念しての演奏会だが、シェイクスピアの戯曲をまとめて出版した最初の作品集といわれている「ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、史劇、悲劇」、通称「ファースト・フォリオ」が出版されて今年でちょうど四百年を記念しての演奏会ともいえるこの日のプロ。
前半はチャイコフスキーが国民楽派色の強かった時期の作品、後半はチャイコフスキーが西欧を旅行し急速に西欧の影響を強く受けていく時期の作品と色分けしている。
当然こちらもそのあたり意識して臨んだけど、演奏がそういうことはさておいてというくらいに、とにかくそういう要素を吹っ飛ばすくらい、特にシェイクスピアの三曲は強烈だった。
聴いていてチャイコフスキーというより、まるでイタリアオペラの序曲や間奏曲が演奏されているかのようで、歌うわ歌う、そして強烈な程の情熱の叩きつけと、シェイクスピアにまったく疎い自分が聴いていても(自分がシェイクスピアで読んだことがあるのは「ヘンリー四世」と「ウインザーの陽気な女房たち」のみ)、その原作の素晴らしさが伝わってくるように思われる演奏だった。
指揮のバッティストーニは以前聴いた時も曲から驚くほどのエネルギーを引き出していた。
当時自分はこう書いている。
「(前略)~ 前半の曲を聴いていて思ったのは、とにかく音がクリア。そして弦を中心にひじょうにブレンドされた響きが素晴らしく、弦の弱音や木管の表情付けなどかなり細かく神経が行き届いたものになっていました。
また音のクリアさとブレンド感がうまく合わさっていることと、弱音がひじょうにコントロールされているせいか、無理に大きな音を出さなくてもホール全体に強音がしっかり伸び伸びと響くので、大きな音になっても決してギスギスしたり濁ったりせず、バランスもしっかりとれていて、どの曲もとても安心して聴いていられました。
ただこう書いているとオケにあまり推進力が無いように感じられかもしれませんが、オケが弦を中心に表情豊かな流動感のようのものを強く感じさせ、それがとても自然な推進力を音楽に与えており、これがヴェルディやポンキエッリでかなり大きな武器になっていました ~(後略)」
これが今回のチャイコフスキーにもそのまま当てはまっていたが、今回の方がこの指揮者の魅力がより強く感じられた。なにしろ「ロメオ」も「テンペスト」もトランペットがブラームスの交響曲と同じ二人だったにもかかわらず、まるでリヒャルト・シュトラウスなみに豪奢に鳴りに鳴り捲ったのだからこれには正直驚いた。
この指揮者は表題系や曲がドラマ性を豊かに持ち合わせている方がより実力を発揮するタイプなのかもしれない。だとするとドラマという物に対し鋭く反応し実力を発揮する傾向がある東フィルとの相性がいいのは当然なのかも。
おそらくそれらが今回のチャイコフスキーでフルに発揮されたのだろう。
とにかく圧巻のチャイコフスキーによるシェイクスピアでした。
尚、前半演奏された「ロココ」も佐藤さんの熱演もあって、こちらはとても爽やかに聴くことができた。箸休めというとちょっと語弊があるかもしれないけど。
余談ですが、シェイクスピアは徳川幕府初代将軍徳川家康とほぼ同じ時代。それに対しチャイコフスキーは15代将軍徳川慶喜とほぼ同じ時代を生きている。そのことを思うと二百五十年以上の歳月をまたいでの二人の巨人の邂逅をこうして一晩で聴けたのはとても貴重な体験だったような気がします。
今後もまたこういう作家、もしくは画家や彫刻家との作曲家の邂逅をテーマとして取り上げてほしいものです。
最後に個人的なことをひとつ。
自分が初めてクラシックのコンサートに行ったのは、1973年11月17日に東京文化会館大ホールで行われた東京フィルハーモニー交響楽団 第164回定期演奏会だった、
指揮はハンス・レーヴライン、ゲストにバリトンの木村俊光氏を迎えてのワーグナーとその流れをくむ作曲家を扱ったもの。
つまり今回の演奏会はこの初めてのコンサートからちょうど50年目に当たっていた。しかもオケも奇しくもその時と同じ東フィル。
当時今より簡素極まりなかった文化会館で、あまり人の入りが芳しくはなかったもののあの頃からオペラに強かった東フィルが、ワーグナーのトリスタンの前奏曲と愛の死やシュトラウスの「ばらの騎士」組曲、特に後者でじつに素晴らしい演奏を聴かせてくれ、アンコールにもう一度「ばらの騎士」組曲の終結部のワルツをノリノリで聴かせてくれたことが今でも忘れられない。
あの1973年11月。
N響にはギュンター・ヴィッヒ、東響は音楽監督であり常任指揮者の秋山和慶さん、日フィルは同団初登場のスメターチェク、読響は名誉指揮者オッテルロー、都響は音楽プロデューサーとしても有名なオットー・ゲルデス、新日フィルは手塚幸紀さんが指揮をとっていた。
レーヴライン(1909~1992)が最後に東フィルの定期に登場したのが1980年、バッディストーニ(1987~)が初めて東フィルの定期に登場したのが2012年。
そんなことを思いながらの、ちょっと自分にとって感慨深いものもあったこの日の演奏会でした。
しかし東フィルはこの半世紀で別次元の進化を遂げたようです。
月日が経つのは早いですが、その間いかに頑張ってきたかが今の姿なのでしょう。
因みにこの日の演奏会は録音されていたようで楽しみです。
以上で〆



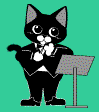

コメント 0