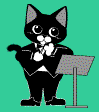ユージン・オーマンディについて。 [クラシック百物語]
内容は彼の経歴やラフマニノフとのことなどがあったが、それ以上に彼が何故日本では低く評価されているかということに重きがあった。
奥田さんは日本に誤った情報が広まった事が大きな要因と言われた。
これは彼はオペラが指揮できない、なのでウィーンフィルなどからも評価されずにヨーロッパで相手にされない。という間違った情報が広く流布されたことが少なからずあるというもので、実際は彼が1950年代から60年代にかけてかなりウィーンフィルの定期に呼ばれていたということを強く指摘していた。
また一部評論家の中身の無い空虚な音楽という評も指摘していた。
自分もこういう評を当時よく目にしたし、中にはオーディオファン向けの音楽と切って捨てたりとか、この音楽を支持するフィラデルフィアの街の人たちに対する誹謗ともとれるような言い方とか、とにかくどちらの人達にも失礼極まりないものすらあった。
だがはたしてそれだけだろうかという気もじつはしている。
これについてはかつていろんな人達と意見を交わした事があるが、個人的にはもっと根深いものがあるような気がしている。
ひとつは日本で起きた1950年代頃からのアメリカの機能至上主義や商業主義みたいなものへの否定で、これは反米的なものが高まりをみせ、後に学生運動へと大きなうねりとして発展していったものなのですが、当時インテリ層みたいな似非肩書をもっていた(もしくは錯覚していた)評論家がそれに迎合する、もしくは否定的な事を言ってバッシングされないための保身に走ったことも要因としてあるのではないか。
ひとつは、ヨーロッパ楽壇への埋めようがない劣等感を癒すため、アメリカのオケや指揮者(アメリカを主戦場としている外国人指揮者を含む)を精神的に貧しいとか、そのオケも機能ばかりを追求し音楽を逸脱していると評し、「精神的」な面で自分達の方が上というくだらない満足感を持とうとしたこと。
ひとつはオーマンディが協奏曲や小品をかなり高いレベルで演奏しているにもかかわらず、それらを大量に録音しているというだけで協奏曲しか取り柄が無い、小品録音を大量製造するポップス指揮者みたいに思われたこと。
ひとつは、規格外の凄いものを聴かされたとき、現実を直視することができず結果苦し紛れの否定に指揮者もろともまきこんでそれに走った事。特にこれなどは昭和の頃の貧弱な日本のオケにどっぷり浸かったがために起きた弊害という気もした。もっとも当時の日本のオケの団員は評論家と逆で、それら評論家から全否定されたアメリカのオケを口を極めて絶賛していた。そしてそこにはセル&クリーブランドだけでなくオーマンディ&フィラデルフィアがあり、一部ではこの両者こそ世界最高のオケとまで称賛する声があった。
そして最後は、日本は特に「陽性」な演奏家をやや低く見るきらいがあるということ。どららかというと陰影のあるものを持ち上げるということ。そして時には音の汚れまでもそれと同じように扱うというケースまで散見されること。
というのが他の理由としてあると思っている。
このためショルティとシカゴ、そしてオーマンディとフィラデルフィアは初来日当初からこういうポジションに立ち位置をもった人達から、かなり手厳しい言葉を浴びせられることとなった。
じつにくだらない事だけど、声がデカくてご立派な肩書を持った人がもっともらしい能書きを垂れてしまうと、悲しいかなどうしても昭和の頃はそれにへいこらひれ伏して右に倣えとズルズル引きずられる人が多かった事も事実。
ただ令和の今は、さすがにそういう愚かな物言いに左右されることもなく、目の前の音楽にイーブンに対峙してくれる方がほとんどなので、オーマンディもフィラデルフィアも今はかなり真っ当に評価されているように感じられる。
因みに奥田さんは触れなかったけど、自分はオーマンディはロバート・ショウ同様、トスカニーニに強く私淑した直系に近い指揮者だと思っている。
それは彼が聴きやすいが媚びたりあざとさに走る事がない、真摯で誠実な演奏スタイルがそれを如実に物語っていると思う。またあの決して笑わない目が音楽をこちらの想像以上に深いところで見据えているような気がしてならない。
(ただしときおり大胆なアレンジを施したヴァージョンを演奏することはある)
その最たるものが西側初録音となったショスタコーヴィチの交響曲第4番と、晩年EMIに録音したシベリウスの「四つの伝説曲」とヒンデミットの「弦楽と金管のための協奏音楽」だろう。

前者のその切り詰めた緊張感と力感は凄まじいものが有り、フィラデルフィアのオケの精度の高さも相まって驚異的な演奏となっているし、もしこの曲をムラヴィンスキーが録音していたとしも一歩も引けを取らないレベルの演奏だと思う。
また後者は1978年に神奈川県民ホールで聴いたこのコンビを、これほど彷彿とさせる録音も稀というくらい素晴らしくその魅力がとらえられおり、演奏の見事さも相まって、このコンビの実演でのそれをかなり忠実にとらえた名盤と自分は確信している。
(個人的にはRCAものは音質が堅く、かつてCBSソニーから出ていた国内盤は着色過剰ともいえるような音質だったと感じています)
とはいえ曲目がややマニアックなので、もし人にこのコンビを勧める時は、1978年に録音した「英雄の生涯」と、XRCD化されたシベリウスの2番、そして「英雄の生涯」と近しい時期に録音されたメンデルスゾーンの「スコットランド」を上げる事にしている。
あと合唱ものではメンデルスゾーンの「最初のワルプルギスの夜」やベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」もなかなかだけど、何故かオーマンディの合唱ものは、声を器楽扱いしているという評のせいかあまり芳しい印象が日本ではないのが残念。
ただ前述したけど、かつてに比べれば随分まともに評価されるようになっただけでもありがたいし、1967年の初来日公演がCD化されたことなど昔を思えば夢のようです。
とにかく昭和の時のように、おかしな色眼鏡でものをみたり、保身や人気取りで物事を語ったりするのは令和のこの時期にはもう勘弁です。
まもなく没後40年。
これからもオーマンディとフィラデルフィアが真摯に評価され続ける事を深く願います。
〆
指揮者ロバート・ショウ雑感。~特にアトランタ響時代の事~ [クラシック百物語]
ショウは何種類ものクリスマスアルバムのヒット

ロバート・ショウ合唱団そのものの名声。

そしてトスカニーニとの共演とその名演の数々に参加したことで、日本でもかなり早い時期からその名前を知られており、1950年代初めに出た音楽辞典の人名篇にも、アメリカ人としては彼より少し年下のバーンスタインやスターンと並び、早くも紹介されている。
だが日本での彼はそこで「将来性のある合唱指揮者」と言われているように、合唱指揮者としてのイメージが強いためか、1967年のロバート・ショウ合唱団の活動終了以降、つまりアトランタ交響楽団と歩んだ、約三十数年が抜け落ちているきらいがあり、そのためその時期に録音された多くの録音が不当に低く評価されているふしがあります。
そこでここではそんなショウの事について自分の雑感を述べたいと思います。
まずは経歴ですが、いくつかのサイトからそのまま翻訳したものを多少付け加えたりして掲載します。ご了承ください。
ロバート・ショーは1916年にカリフォルニア州の福音派教会の牧師の四人兄弟の一人として生まれました。彼の祖父も牧師で、母親もその教会の合唱団で歌っていたということで、彼は宗教と音楽に囲まれた幼少期に育ち、その後教会の合唱団のリーダーをしたりしていました。ショウは学校では哲学、文学、宗教に興味を持ち、ポモナ大学ではグリークラブに所属していました。
そんなおり、著名なミュージシャンでありDJでもあったフレッド・ワーリングがポモナ大学で映画を撮っていた時、聖歌隊を指揮したショウの演奏に感動し、彼にニューヨークに来てグリークラブを担当してほしいと頼みました。
1941年、「Collegiate Choral」(現在の名匠は「MasterVoices」)を設立。
1944年頃に自身初録音。
1945年にバーンスタイン指揮による自作「オン・ザ・タウン」の録音に参加、以降バーンスタインと親交を結ぶ。
同年、ヒンデミットに委託した「戸口に咲き残りのライラックが咲いた頃」を初演。
1946年にボストン交響楽団の客演指揮者を二シーズン担当。主に合唱付きのプログラムを演奏。
1948年にロバート・ショウ合唱団を31人のメンバーで発足。メンバーは時に応じ60名以上の規模にまで拡大されることがあった。
そして同年トスカニーニと共演する。
第九の練習時にトスカニーニが練習を止めると楽団員に対し、
「私が探していたマエストロをついに見つけた」
と、ショウを激賞した。これには周囲も驚いたが、本人も遥かに年下の自分をマエストロと呼んだことに驚きと深い感銘を受けたという。
この1948年から始まったトスカニーニとの共演は、年齢を超えた互いの強い信頼関係により、トスカニーニが引退する前月まで絶え間なく続くことになります。
(因みにある時はトスカニーニのマネージャーによりトスカニーニの自宅で彼にサプライズで合唱団が歌唱を披露した事もあったといいます)

1952年にブロードウェイ・ミュージカル「My Darlin' Aida」のコーラス・ディレクターを務める。
この頃までにオーケストラに対する指揮の手ほどきをモントゥやロジンスキーに受ける。
1953年Collegiate Choraleを退任し、サンディエゴ交響楽団の音楽監督になる。
1954年3月、トスカニーニとの最後の共演。
この時の曲目は、
ヴィヴァルディの「2つのヴァイオリンとチェロと通奏低音のための協奏曲」ニ短調 RV565
ヴェルディの「テ・デウム」
ボーイトの「メフィストフェーレ」からのプロローグ
共演はヴィヴァルディを除く二曲。
1957年(1958年?) サンディエゴ交響楽団の音楽監督を退任。同年ジョージ・セルに請われ、クリーヴランド管弦楽団の合唱指揮者兼助手となる。セルとは気質の違いから衝突が起きたと言うが、結局1967年迄その地位にあった。この間セルの指揮からいろいろと勉強した。
(尚、これは推測ですが同時期に同じく助手をしていたルイス・レーンからもいろいろ助言等を受けたかもしれません)
1960年に、7週間で36都市36公演の「ロ短調ミサ」ツアーを33人の歌手と29名の楽団員とともに挙行。最終公演地のNYで自身二度目の「ロ短調ミサ」をこのときのメンバーで録音。因みにヴァィオリンにはオスカー・シュムスキーも参加。
(この時、数分で組み立て可能な小型パイプオルガンを特注し、それを持ち運んでのツアーとなりました)
1962年に、その「ロ短調ミサ」で初めてグラミー賞を獲得。

1967年クリーヴランドを離れアトランタ交響楽団の音楽監督に就任。それと同時に1948年以来活動をつづけていたロバート・ショウ合唱団の活動を終了。この間RCAに録音したアルバムは総計100万枚以上売れたという。
1972年、第3回国際合唱祭に招かれた16カ国の大学合唱団から選ばれた640人の合唱団を指揮し、アメリカの大学キャンパスで2週間のコンサート・ツアーを行った後、ニューヨークのリンカーン・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで公演。
1976年、アトランタ交響楽団初の商業用録音をショウの指揮で発売。
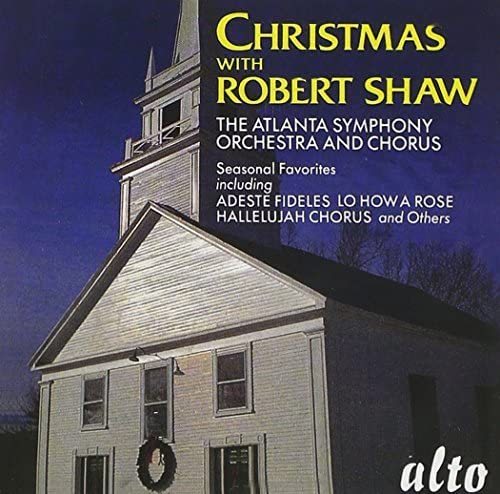
1977年から1983年まで、当時アクロン交響楽団の音楽監督だったルイス・レーンを、アトランタ交響楽団の共同指揮者として迎える。
1978年、テラークと初録音。以降、ショウの録音の多くがテラークで行われる。
1986年、ベルリオーズのレクイエムでグラミー賞のクラシック部門のベストアルバム賞を獲得。自身にとってもアトランタ響にとっても初。

1988年、アトランタを退任するショウにバーンスタインから贈られた「ミサ・ブレヴィス」をショウ自身の指揮で初演。
※後にこの曲をショウが再演した時、初演時よりもスコアが厚くなっているのに気づき、出版時にバーンスタインが加筆した事を初めて知ったとか。ショウはこの再演時その出版稿で演奏、この版もとても気に入り将来この版で再録音しようとコメントしていたようですが、残念ながらそれは実現しませんでした。
同年、アトランタとの欧州ツアー等を行った後勇退。以降同団の名誉音楽監督兼桂冠指揮者。ショウの在任期間中にアトランタは全米オケの「エリート11」にランキングされる。
1989年、グラミー賞のクラシック部門ベストアルバムを、ヴェルディの「レクイエム」で二度目の受賞。

その後クリーヴランドやボストンなど他のオーケストラに客演し、合唱指揮者や歌手を対象とした夏季フェスティバルやカーネギーホールでのワークショップで教鞭をとる。
1994年に翌年創立50周年を迎えるアトランタ響の記念アルバムとして、ボニー、クイヴァー、ハドリー、ハンプソン等を迎えた豪華メンバーによる、メンデルスゾーンの「エリア」を録音。
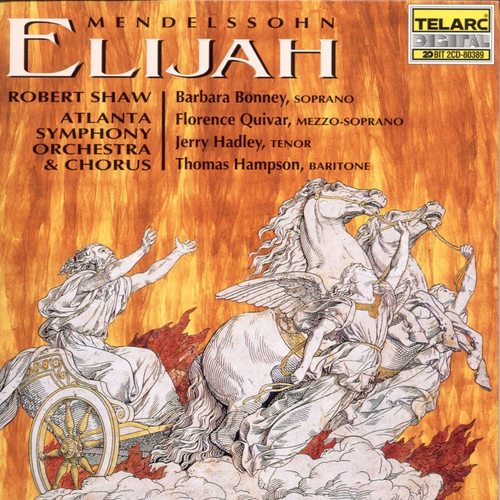
1998年、ドヴォルザークの「スターバト・マーテル」を録音。これが最後の録音となった。
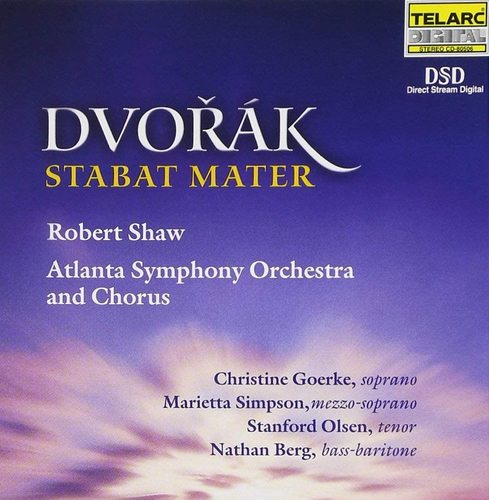
1999年、脳卒中のため、コネチカット州ニューヘイヴンにて脳卒中により82歳で死去。
以上が経歴。
さてロバート・ショウの録音はじつに多い。
1946年に「クリスマスの讃美歌とキャロル集」を出した翌年、バッハの「ロ短調ミサ」を初録音。これは史上三番目の同曲全曲録音となった、
(さらにその四年後には「ヨハネ受難曲」全曲を録音)
その後ロバート・ショウ合唱団との多くのアルバムの他に、トスカニーニをはじめとした多くの名指揮者との共演が続く。

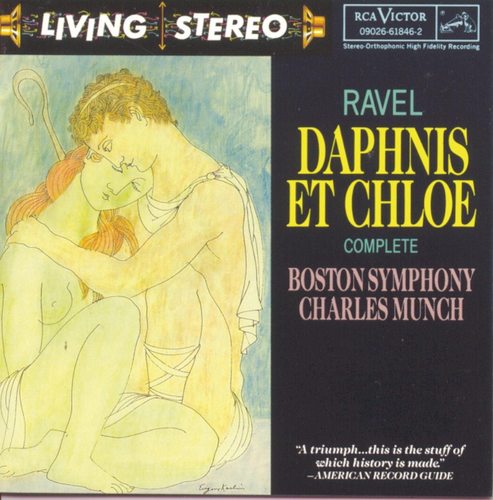
そして1957年頃よりステレオ録音により、讃美歌、黒人霊歌、フォスターの歌曲集などを録音。
さらに1960年に前述した「ロ短調ミサ」の録音皮切りに、二年後にはクリーヴランド管弦楽団と宗教音楽の合唱曲集をRCAに録音。

当時クリーヴランドはコロンビアと契約していましたが、同年春に、セルがベートーヴェンの第九をショウ指揮のクリーヴランド合唱団とコロンビアに録音したことで、その代わりにRCAへのショウ指揮クリーヴランドの録音が実現したようですが、後者の曲目はセルがクリーヴランドと公式のセッション録音を遺していないものばかりということで、とても貴重なものとなりました。
そしてアトランタ赴任が決まり、ロバート・ショウ合唱団の終了が決まった時期の1966年に、ニューヨークフィル(名義は契約上ただの「オーケストラ」となっています)とともにヘンデルの「メサイア」を録音。
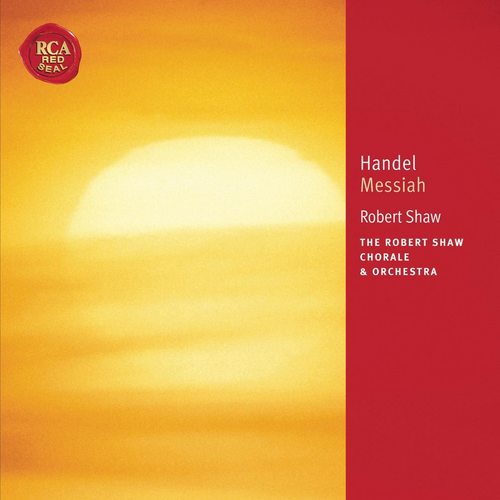
この「メサイア」(1751~1752年版)は、合唱の人数が総勢31人という、設立時のロバート・ショウ合唱団と同人数で録音したもので、演奏はひじょうにアグレッシブで元気なもの、特に最後のアーメンコーラスなど、ノリと勢いにまかせたような感すらあるもの、決して雑な感じはせず、なかなか爽快な出来となっています。
そしてこのアルバムも前述した「ロ短調」同様、1966年のグラミー賞クラシック合唱部門優秀賞を受賞しています。
ショウは1967年のシーズンからいよいよアトランタ響のポストに赴任しますが、その直前の8月、ショウはロバート・ショウ合唱団と最後のアルバム「アイルランド民謡集」を録音します。尚、そこには「別れの盃」という曲が収録され、このアルバムの編曲を担当した盟友アリス・パーカーが、それに対しライナーで思いの丈を語るかのような一文を載せています。
1967年以降、ショウはアトランタに集中し、セルがクリーヴランドで行った再現をするために努力します。
アトランタ交響楽団。
1945年にアトランタ・ユース・オーケストラとして創設され、二年後に現在の名前に改称という比較的若いオケで、初代指揮者のヘンリー・ソプキンが21シーズンに渡り指揮をとりました。オケはプロアマ混合といった編成ではあったものの、ソプキン在任中に全米トップ20に入るまでの実力をつけました。
そんなアトランタにショウは赴任すると、同オケは完全にプロ化され、合唱団の設立もします。ショウは二百名規模の合唱団をつくると同時に、その中の六十名ほどのメンバーで室内合唱団も設けました。
ただアトランタの事務方がショウに期待した録音にはかなり慎重で、初録音は1975年12月に録音した「クリスマスアルバム」まで待つ事になります。そしてこれはアトランタ響待望の初の商業用録音となりました。
1978年。ショウ指揮のアトランタはテラークと契約、いよいよ本格的な録音にとりかかります。
最初の録音は「火の鳥」と「イーゴリ公」より序曲と「韃靼人の踊り」。

オケをメインに合唱もちゃんと取り入れるという、アトランタ響のメンバーが出来る限り多く参加できる曲目であり、テラークの録音の良さも誇示できるアルバムとなっています。
ただ演奏は効果を狙わない比較的堅実な演奏、ただしそれだけに終わらない、随所に詩的な歌心をもった旋律の歌わせ方にショウの指揮の特長が感じられる出来となっています。
翌年、ショウは合唱メインの曲を録音します。
ヴェルディの「テ・デウム」とボーイトの「メフィストフェーレ」からのプロローグ。
そう、これはショウが1954年3月にトスカニーニと最後に共演した時に演奏した曲で、この年はそれからちょうど25年が経ったということでそれを機に録音したのかもしれません。
演奏はこれも先のストラヴィンスキーと同じラインの演奏ですが、トスカニーニへ捧げるという意味もあったせいなのか、かなり気合と熱気に満ちたものとなっています。
あとこれはショウの特長のひとつですが、シンバルなどを鋭角的、もしくは刺激的に鳴らす事を意図的に避け、かわりにバスドラ(大太鼓)を重く深く響かせる傾向があるようで、それがこの曲にも、そして後に録音されるオルフの「カルミナ・ブラーナ」にも感じられます。
その後ショウはテラークに膨大な録音を行い、同社とアトランタ響に数々のグラミー賞をもたらすこととなります。
そのほとんどは合唱付きの作品で、しかもソリストも原則すべてアメリカ人で行われるというのもショウの方向性がよく表れていると思います。
例外は80年代前半に録音された、エリー・アーメリングとのベルリオーズの「夏の歌」とフォーレの「ペレアス」くらいでしょうか。因みにこれを聴くとアトランタが、78年の「火の鳥」以降さらに良い状態になっていることが伺えますが、それは一時このオケの指揮者となっていた、ルイス・レーンの力によるところも大きかったかもしれません。
因みにレーンはアトランタ時代にテラークでコープランドとレスピーギの各作品集を録音していますが、彼にとってもそれらが自身の代表作となったようです。
そして1986年のグラミー賞で、クラシック部門のベストアルバムをベルリオーズの「レクイエム」で受賞します。

この演奏、弦がときおり硬く洗練度に賭ける音を出したり、オケが走り気味になったりしますが、演奏そのものはかなり出来が良く、「怒りの日」などはテラークの録音も手伝ってなかなかの迫力となっています。
またコーラスの静謐な美しさも随所に感じられ、この巨大性だけでなく、美しさも良く描かれいます。グラミーをとってもおかしくない出来となっています。
ショウのレパートリーは大変広く、アトランタ響と録音したものだけでも、ヴィヴァルディ、バッハ、ヘンデル、ハイドン、モーツアルト、ベートーヴェン、シューベルト、メンデルスゾーン、ブラームス、マーラー、ヒンデミット、ヴェルディ、ベルリオーズ、フォーレ、プーランク、ドヴォルザーク、ヤナーチェク、バルトーク、シマノフスキ、ヴォーン=ウィリアムズ、ウォルトン、ブリテン、バーバー、バーンスタイン等々といった作曲家の曲が並びます。
もっともそのほとんどが合唱付きの作品というのがいかにもですが、かといってそこには合唱指揮者がついでにオケを指揮したという感はまるでありません。
ふつうオケの指揮以外で名を馳せた人が指揮をすると、どうしてもオケのそれが緩かったり、いろんなことをしようとしてかえってピンボケのような演奏になったりと、その人が名を馳せた分野での演奏に比べるとかなり聴き劣りのするものが多く感じられる事があります。
ですがショウの場合はそれがほとんど感じられず、アトランタとの関係が深くなるにつれ、オケのバランスはもちろんですが、全体の洗練の度合いが深まり、表情は細やかかつ大きなものになっていきました。
そのいい例がマーラー没後80年の年に録音された、マーラーの交響曲第8番。

バーンスタインのような大波のようなエネルギーはそれほどではないものの、クリアさやバランスの良さ、そして熱気や音楽の大きさも充分兼ね備えたものになっています。
しかしこの演奏ほどコーラスの弱音の美しさを感じさせる演奏はなかなか無いのではというほど秀逸で、そういう意味ではベルリオーズのレクイエムの演奏と相通じるものがあるように感じられました。
ただショウも曲によってはかなり押出の強い、かなり風格豊かな演奏を聴かせる場合もけっこうあり、モーツァルトのレクイエムやフォーレのレクイエムなどがそういうタイプの演奏となっています。ただ演奏が大きくなっても決して大味になっていません。
それはフォーレと一緒に収録されている、デュリュフレのレクイエムでも同様です。尚、このデュリュフレのレクイエムでは、声楽のソロパートを合唱にすべて置き換えていますが、これは当時まだ存命だった作曲者自身が、このソロパートを合唱でやることを気に入っていたという事をショウが聞き、その意志を尊重したとのこと。
そのためちょっとユニークな演奏となっています。

ショウはテラーク時代に「メサイア」「天地創造」「エリア」と、ほぼ五十年おきに出現したこれらの三大オラトリオをすべて英語版で録音している。

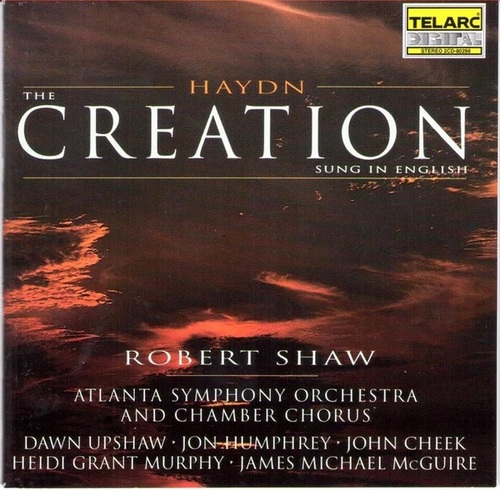
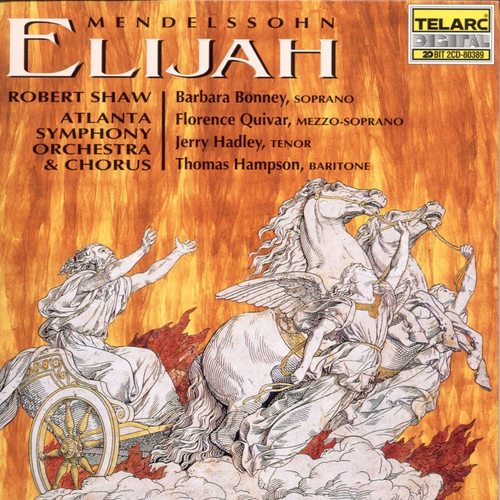
どれも風格のある演奏揃いだけど、ひとつの語法と色で染め上げているせいか、作曲家の違いのようなものはあまり感じられないが、この語法に慣れると、これほど安心して聴いていられる演奏はそうそうない。
しかも劇的な雰囲気や迫力にも事欠かないが、ショルティあたりのオペラ風の劇的感覚とは違うのも面白い。トスカニーニやライナーと合唱指揮者としてオペラに参加したことはあっても、劇場畑てばない部分がこういうところにあらわれているのかも。
因みに「エリア」を除く二曲は室内合唱団編成を採用しているため人数は60人程、「エリア」のみ200人編成のレギュラー編成で行っていますが、印象がそれにより大きく左右されるということは思ったほどありません。
尚、これらはべて英語版なのであれですが、英語以外のショウが専門分野ではない国の言語で歌う場合は、かならず専門家の指導を受け、発音等をチェックしながら演奏しているそうです。
ところでロバート・ショウ合唱団時代とアトランタ時代と、かなりコンセプトが変わったような気がします。
前者の時代。
彼の合唱はオケと共演しても常に前面に出て強い自己主張を独自に出しながらオケと共演するという、そういう感じのものが多く、録音もRCA独特のやや硬めで強い音作りがさらにそれに輪をかけたような印象がありました。それはクリーヴランドとの前述した合唱曲集でも同様。
ところが後者の時代。
アトランタ響に赴任して以降の手ラークの録音となるとかなり雰囲気が違う。
なんというのかオケと合唱の共演関係ではなく共同作業的色合いがとにかく強い、というより合唱もオケのパートの一部という感じのそれになってしまっている。
それは極端に言うとオケだけのアトランタがベートーヴェンやブラームスを演奏しているそれで、合唱がついたアトランタはマーラーやRシュトラウスを演奏しているそれというような、ようするにオケの編成や楽器が増えるような感覚で合唱がONされたという感じ。
そのためオケだけはもちろんだけど、合唱がそれに加わっても「&合唱団」ではなく、名義上はともかく、実質上「三百名編成のアトランタ交響楽団」というような趣になっています。
これはテラークの録音が合唱を前面に出すことなくひとつの響きの中にブレンドさせるそれも大きいと思う。もしこれをショウが嫌っていたらテラークにいろいろと指示していたと思うが、それが録音のレベルこそ年々上がっていったものの、基本ラインは最後のアルバム迄変わる事はなかった。
この響きの作り方は、ひょっとするとショウの幼少時の教会における響き等が影響しているのかもしれないが、そのあたりはよく分からない。
あとこの合唱団を含めた響き。
自分はそこにかつて実演で聴いたオーマンディとフィラデルフィアを思い出してしまう。特にフィラデルフィアのあの透明感と色彩感、それにときおり風圧を兼ね備えたあの弦の響きと、アトランタの合唱がひじょうにイメージとして強く重なる。
また音の方向性もどこか似たものがあり、聴きやすいものの原則効果はあまり狙わず、真摯に音楽に対峙する基本姿勢を崩さないそれも、どこか強く共通点を感じる。
そこにはこの二人がトスカニーニ私淑していたという共通点があることと、ともに最初は指揮者ではなく、ヴァイオリンや合唱指揮の名手でありながら、そこから専門的な指揮教育を受けることなく、半ば独学でオケのトップにたちひとつの時代を築いたことにも何か要因があるのかもしれない。
そういえばショウが最初に定期的に客演するようになったボストン響の当時の指揮者クーセヴィツキも彼らと似たような経歴の指揮者だった。そう思うと彼らが成功したのは、そういう経歴でも実力次第ではしっかりと受け入れてくれた、当時のアメリカの土壌というのもあったのかもしれません。
と、長々ととりとめもなく話しましたが、まとめていうと、ロバート・ショウは偉大な歴史に残る合唱指揮者であり、その特徴をオケの指揮者としても存分に活かしながら、まったく独自のスタイルに昇華させた、これまた大指揮者だったという気がします。
それを思うと欧米においての指揮者としての評価に比べ、日本では彼が何故あまり評価されなかったのかが分かる気もしましたし、「合唱指揮者」というレッテル貼りが悪い方にも作用したという気もしました。
これにはクーセヴィツキやオーマンディへの日本での評価とどこなく相通じるものも感じました。
あと余談を少々。
彼の宗教音楽に関するレパートリーはかなり膨大なのですが、何故かそこからブルックナーがすっぽり抜け落ちている。宗教的な問題なのかは分からないけど、とにかく彼の交響曲どころか宗教音楽もまったく見当たらない。彼の指揮でブルックナーを一度聴いてみたかったです。
もう一つ。
彼はベートーヴェンの第九に強い畏敬の念をもっていたらしく、彼は
「この曲を演奏するのはこれが最後かもしれないと、いつも思っています。アメリカの上院で演説するようなものだし、ウィリアム・バトラー・イェイツのためにアイルランドの詩を読むようなものだ。この作品をやるときは、いつでもイベントです。そして、それは大きなイベントなのです」
と語ったとか。彼の指揮で年末の日本で第九を聴いてみたかったです。それは共演した日本の合唱団にとっても大きな財産になったはずですから。これだけは本当に残念です。
因みに彼は第九の録音を1980年代にセッションとライブの二種類残していますが、どちらもテラークへの録音ではありません。

1985年のセッション録音。

1988年、ショウがアトランタの音楽監督在任時の最後の演奏会におけるライブ録音。
尚、彼が20世紀の合唱曲で高く評価していたのは、
〇シェーンベルク「地上の平和」
〇バルトーク「カンタータ・プロファーナ」
〇ストラヴィンスキー「詩篇交響曲」
〇ヒンデミット「戸口に咲き残りのライラックが咲いた頃ー愛する人々へのレクイエム 」
の四曲とのことで、これらすべてテラークに録音されています。
最後に。
彼が日本で欧米ほど人気が無いのは「合唱指揮者」という悪い意味でのレッテル貼りや、日本においてアメリカのオケや指揮者の欧米ものに対し、伝統的ともいえる「偏見」も要因としてはあるけど、それ以上に彼がアトランタに赴任した時期から本格化した古典派以前に対するピリオドへの流れ、また彼とほぼ同時期に同様に長期政権を築いたショルティとシカゴ響の存在、そしてテラークの日本でのクラシックにおけるブランド、さらにはそのテラークもアトランタが録音を始めたころは、日本ではボストン、クリーヴランド、シンシナティポップスの方が話題性があり、日本でも戦略的にそちらが優先されたような感じになった事等も影響として大きかったといえる。
特にピリオドへの流れは、それと逆行するような彼のモダンスタイルが時代遅れと思われるようになってしまったことは、決して他の多くのモダンスタイルの指揮者のように大編成合唱至上主義ではなかったものの、やはり彼へのそれに響いたことは間違いないと思う。
ただ彼の丁寧かつ一貫性のある真摯な姿勢と音楽に対してまで、はたして同様な姿勢を聴き手がとるのはとても残念だしもったいない気がするのは何とも残念な気がします。
今後彼の音楽がどう日本で評価されていくかは分かりませんが、かつてエードリアン・ボールトがまったく日本で黙殺状態に近かった状況が今は大きく改善されたように、将来ショウとアトランタも将来もう少しじっくりと聴かれるようになれば嬉しいです。
以上で〆
長々とおつきあいいただきありがとうございます。
ドヴォルザークのイギリス [クラシック百物語]
例えば画像検索でやってみると
かなりそれらのものがヒットしてくるはず。
かつてはこのように、
どうしてそうなったかは分からないけど、
今では死滅したいろいろな謎の表題というか、
いわゆるサブタイトルが目についた。
これはマーラーも例外ではなく、
第四交響曲に
「大いなる喜びへの賛歌」
というのがかつてはごく日常につけられていた。
これは終楽章の歌詞の誤用という説があるらしいけど、
ただ1950年代の日本の音楽辞典には、
同曲にそのような表題はないので、
誰かが勝手に流布したのかもしれない。
第三交響曲にも
「夏の朝の夢」
というものがつけられていたけどそれはかなりレアで、
これは早々に目にしなくなった。
ただ上記したその音楽辞典にも、
不思議なそれがいくつか見受けられる。
例えばマーラーの第七交響曲「夜の歌」は
「ロマンティック」となっている。
そしてその「ロマンティック」とついている第四交響曲を作曲した、
ブルックナーの項をみていると、
00番と0番の両方に「リンツ」というタイトルがついている。
またボロディンの第二交響曲には「英雄」とついているが、
ショスタコーヴィチの第五交響曲に「革命」とはついていない。
ハイドンの交響曲をみると
一番「ルカベック」
十三番「ジュピター」
二十六番「クリスマス前夜」
(現在では二十六番は「ラメンチオーネ」[嘆き])
となっている。
こうしてみていると、
いろいろと情報不足の時代にはびこっていた、
不確定要素の大きな情報によってつけられたものや、
意味がないということで切り捨てられたタイトルが、
けっこうあったことが如実にわかる。
またかつてタイトルをつけることで、
多くの聴き手に興味を抱かせよう、
もしくは印象づけさせようとしたものが、
その役目を果たし看板をおろすことで、
本来の形に戻ったというものもあったように感じられた。
今後まだこれらの流れによって淘汰されるものがでてくるのか、
それともいったん終了かは分からないけど、
それだけ聴き手が内容勝負にこだわってきた、
もしくはネットでいろいろと聴くことができたり、
その曲の情報をいろいろと仕入れるようになったことで、
今後増えるということはないと思う。
ただ正直言うと、
あまりかえりみられていない日本の作曲家による交響曲等は、
ひょっとしてこういうものがまだ必要なのかもと、
そんな気もちょっとしたりしています。
もっとも「勝鬨と平和」のように、
今となっては内容的に、
むしろ誤解を生むかもしれないようなものは、
さすがにもうこりごりという気はしますが。
〆です。
ウィーンフィルは本当にこの百年間ダメになり続けているのか [クラシック百物語]
なんか少なくとも日本ではそんな雰囲気が長い間続いている。
古くは1930年代後半に書かれた、
野村あらえびす氏の「名曲決定盤」にて、
ウィーンフィルは昔の方がうまかったという意味の、
そんな一文があったことからだった。
あらえびす氏は実際のウィーンフィルを聴いていないので、
おそらくこの「昔」とは、
1920年から30年代初めのまだ常任指揮者がいた時代、
つまりシャルクやクラウスの録音時のそれを指してのそれだと思う。
たがこういう論調はこれではすまなかった。
その後第二次大戦後も、
ウィーンフィルは戦前の方がうまかったという話があった。
それはワルターヤワインガルトナーの時代も含めたものだったが、
それはあらえびす氏がうまくなくなったというその時代も含まれているようだった。
そしてこれはさらに続く。
ステレオ録音の1960年代ごろになると、
ウィーンフィルは戦前やモノラル時代の方がよかったというそれが、
評論家やマニアからもけっこうよく出てきたという。
それは1970年代になっても続いたし、
ショルティやアバドとともに来日したときにも、
やはり同様のそれが聞かれた。
1975年にベームとともに来日したとき、
ようやくそれに歯止めがかかったようだったが、
1980年代に入ると、
またまた「昔はよかった」「ベームと来た時の方がうまかった」という
そういう感じの空気になっていった。
ヘッツェルが事故で急逝したときも、
そのせいかかなり危惧されたものの、
クライバーが「ばらの騎士」で世紀の名演をやったことで、
その空気は一度消えたけど、
今世紀に入って、
やはり「昔はよかった」と、
今度はかつてダメになったといわれた、
1970~1990年代とも比較されても言われるようになった。
これをみていて、
確かに峠の上り下りみたいな部分はあるけど、
とにかくひたすら前の時代に比べダメになったというそれが、
幾年月がひたすら過ぎようと、
少なくとも日本では常につきまとっているように思われた。
似たようなもので
「ニューヨークフィルはトスカニーニ時代が最強」
「コンセルトヘボウの最盛期はメンゲルベルク」
「クリーヴランドはセルの時が頂点」
というものがあるけど、
ウィーンフィルのそれは、
前の時代に比べて「下手になった」「味がなくなった」という、
そういうものが短いスパーンで繰り返し繰り返し続けられ、
(50年代より40年代、40年代より30年代、30年代より20年代という具合)
これが何年何十年と時代が過ぎても続いているため、
ちょっと前の三者とは違っているように感じられた。
なんかそれをみていると、
「ウィーンフィルってこの百年間ひたすらダメになっているのか?」
という疑問が湧いてきた。
しかもその百年間ダメになりつづけているオケが、
未だにベルリンフィルとともに世界最高峰に君臨しているということは、
じゃあ今のオケのレベルっていったい何なんだという疑問が湧いてくる。
日本のオケのこの半世紀の進化はすさまじいものがあり、
海外の一流オケと比較しても遜色ないレベルの演奏を聴かせることも、
今は決して珍しいことではない。
にもかかわらず上であげたような図式があるということは、
かつてのオケは人知を超えたレベルだったということなのか、
それとも今のオケはじつは本当はダメなレベルで、
それに耳が慣れた我々の錯覚なのかと、
正直???状態なのです。
この「ウィーンフィルがひたすらダメになり続けている説」の検証を、
音楽評論家やジャーナリストがやったというのを、
自分はまだ残念ながら目にしていないけど、
この件について一度ぜひ専門家に詳しく論じてほしいです。
おそらく技術的というより音楽的、
もしくは質的な変化がそういう基なのかもしれませんが……。
因みに自分が最後に聴いたウィーンフィルは、
かなり以前のラトル指揮のベートーヴェンだったけど、
それの四半世紀前に聴いたベームのベートーヴェンと比べて、
そんなにオケがダメになったかというと、
じつは全然そういう印象が無い。
指揮者のせいか雰囲気は変わった気はしましたが。
それだけにこれについては本当に?なのです。
じっさいどうなんでしょう。

LFJTOKYOのホールAについて。 [クラシック百物語]
毎年GWに有楽町の東京国際フォーラム全館を使用し行われる、
クラシック音楽を中心とした祭典。
いつも大盛況なのは素晴らしいことだが、
自分にはいつも不満がある。
それは5000人が入るホールAの使い方のこと。
正直このホールはクラシック音楽を「聴く」には。
あまり適したホールとは言い難い。
通常オーケストラを聴くのに適したホールは、
定員二千人以下というのが比較的多い定説といわれている。
大きくても二千五百が限度というところで、
NHKホールもそういう意味では適しているとは言い難い。
だがこのホールAはさらに大きく五千というキャパだ。
正直ここでよほどの大編成ものでないかぎり、
かなり無理のあるホールといっていい。
このためこのホールを埋めるため、
名曲絡みや顔ぶれが豪華な協奏曲やガラで、
ここの公演を埋めているのがLFJの現状といえる。
ただこのことそのものは決して悪くはないが、
LFJは毎年テーマが決まっているため、
当然それに沿った曲目しか選べないため、
選択肢が限られてしまう。
ただでさえ足かせのきついホールでは、
当然曲目も一部に苦しい物が見受けられ、
魅力的にも環境的にも他ホールに比べると低いケースが多い。
そのため他ホールが売り切れているから、
時間稼ぎ等でしかたなくいく人の比率も増える。
まあ確かにそういうガス抜きホールがあってもいいもしれないが、
正直このままでいいのかなという気はする。
なので個人的な意見ですが、
このホールAはもう毎年のテーマから除外し、
単純に毎年「フェスティバル」というテーマで、
より自由に縛りの無い公演をうつべきではと考えている。
そうすれば曲目にも幅ができるし、
登場する演奏者もより多彩になる。
場合によっては半分だけ曲目を決め、
後半はゲストも曲目も当日発表という、
そういうお楽しみ公演も毎日可能になる。
これもまた「フェスティバル」の醍醐味だろう。
前半と後半違うオケがやるというのも面白いし、
そのときの舞台転換も見せ場としててつくれれば、
「聴く」だけでなく「観る」という部分への売りも可能かと。
個人的にはそうなれば、
「映画やアニメで使われたクラシック音楽」
とか
「音楽の教科書に出てくるクラシック」
さらには
「仲がよかった作曲家たちによる名曲」
とか
「同じ年に初演された名曲たち」
「今と違う名曲のオリジナルの姿」
という括りでのプログラムも可能。
アイデアはいくらでも出せるだろうし、
その方が聴く方も楽しいというもの。
「今年のテーマは興味ないからいいや」
という人も少なくなると思う。
このホールはとにかくその大きさや特性から、
ある意味クラシックとしては規格外。
ならばこちらからあえて規格からはずというのも有りかと。
このあたり多少柔軟に運営には考えてほしいと願う次第です。
〆
あらえびすの「名曲決定盤」を読んで。 [クラシック百物語]
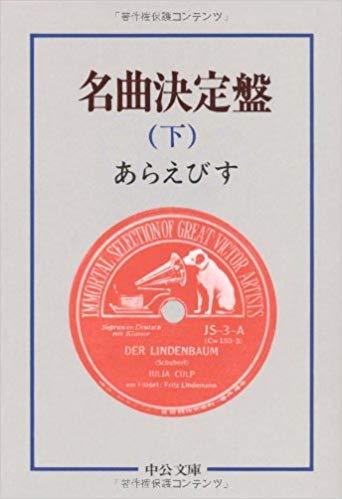
第二次大戦以前の昭和の名盤ガイドというと、
たいていこの本がでてくる。
当時の音楽ファンはこういうものを読んで参考にし、
今では考えられないくらい高価な音盤を購入していたんだなあと、
そんなことを考えながら久しぶりに読んだ。
で、ぶっちゃけた感想としては、
当時としては驚異的に音盤を購入していたクラオタによる、
盛大な感想文大会という範疇を抱ない代物で、
今のクラオタならこれくらい書ける人はけっこういると思われる、
そんなレベルの内容かと。
しかも現代と同様に好き嫌いと良し悪しがちゃんぽんになった内容で、
当時これを鵜呑みにして聴いた人がさぞ多かったんだろうなあと、
ある意味当時の日本のそれの一端を垣間見るような気がしたし、
その悪癖を未だに継いでいる間抜けな評論家いることも、
残念な現実として再認識させられた。
ただこの本はそういう負の部分だけで構成されているわけではない。
今となっては忘れ去られてしまった演奏家にふれていたり、
演奏家は知られているが、
その人にこんな録音があったのかというものが分かったりと、
そういう資料的な価値はかなりのものがある。
それに今とは扱われ方が大きく違う人もかなりいる。
中には当時の音盤量が少なかったり、
第二次大戦以降に円熟していった人もいるので、
そういう部分はしかたないけど、
それ以外にも今とはけっこう評価が違う人がいて、
このあたりはなかなか興味深かった。
他には当時の日本の音楽に対する価値観や、
独墺至上主義的なものの考え方が伺えたりと、
そのあたりもけっこう面白いものがあった。
ただ当時の独墺至上主義的なそれと、
そこから派生したような米英系を低くみる傾向は、
当時日本の一種の劣等感からきたものであって、
戦後に大きく蔓延した独墺至上主義や米英系を低くみるそれが、
思想的なものが介入していた部分があることから、
それらとはやはり違って感じられた。
あと当時と今とでは年齢に対する感覚が違い、
五十代の人も今でいう六十代かそれ以上の年齢のように話している所が散見される。
五十代の声楽家を老婆とよんだり、
六十代の指揮者を古老と表現したりと、
今では?となってしまうところがけっこうあったり、
その表現が今では大丈夫なんだろうかというものもあった。
もっともこのようにかなり時代的なものがあるせいか、
戦前の好楽家の雰囲気というもの、
もっとくだいていえば、
当時のクラオタの雰囲気や匂いみたいなものが強く感じられ、
そういう部分はとても楽しいものがある。
また書いている事がけっこう後腐れが無い書き方のせいか、
いろいろと問題のある表現はあるものの、
最近のもののように、
読んだ後に酷い嫌悪感を感じることもない。
このあたりは書き手のさっぱりした、
悪意のない潔い姿勢がそこにあらわれているからだろう。
もっともそこにはいい意味で、
酒の席で自分を慕う後輩との音楽談義で、
自分が語ったそれをそのまま文字にしたような、
そんな趣のある書き方を、
なんとなくだけどしているからかもしれない。
いつも言っている事だけど、
音楽を語る事はじつは音楽を語っているのではなく、
自分自身をじつは語っているにすぎないと自分は確信している。
それを思うと、
上で感じたような書き方をするあらえびすと言う人は、
じつに魅力あふれる人だっんだろうなあと、
これを読んでいて感じさせられるものがある。
そういう意味では当時の貴重な資料というだけでなく、
あらえびすの人柄の一端に触れられる一冊といえるかもしれない。
興味のある人はぜひ一読をお勧めしたいです。
〆
シェーンベルクの「私的演奏協会」のブルックナー。 [クラシック百物語]
1918年秋にウィーンにおいて、アルノルト・シェーンベルクによって旗揚げされた音楽団体。純粋に同時代の音楽に興味をもつ人々のために、入念なリハーサルのもとに良質な演奏を行うことをうたった。1919年2月から、1921年12月にオーストリア共和国の超インフレのため活動停止を余儀なくされるまでの3年間、117回のコンサートを行い、154作品を上演した。
と、wikiに書いてあるが、
同時代の作曲家の作品だけでなく、
それ以前の作曲家の曲や、
後期ロマン派の大編成の作品を、
ビアノや室内楽編成に編曲して演奏するという、
なかなか意欲的なそれであったといわれている。
そのいくつかを聴いてみたけど、
とにかく編曲が巧妙で原曲の良さをよく引きだしながら、
新鮮な感覚も随所にみせたものになっている。
またなんとなくですが、
どこか「浅草オペラ」を思わせるような、
妙に懐かしい響きも感じさせられるものがあります。
まあ師匠も編曲は上手かったので、
弟子も当然そういう技術には長けていたのだろう。
そんな中でいちばん驚いたのが、
エルヴィン・シュタイン、ハンス・アイスラ、カール・ランクルという、
三人のシェーンベルクの弟子たちが、
各々ひとつないしふたつの楽章を担当した、
ブルックナーの交響曲第7番の室内楽版。
しかも編成が先のマーラーより小さく、
ヴァイオリンが二人以外は、
ヴィオラ、チェロ、コントラバス、
ホルン、クラリネット、ピアノ、ハルモニウムが各一名という、
打楽器がまったくいないという9人編成。
この曲本来の編成が、
フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、
ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、
ワグナーチューバ4(テノール2とバス2)、
コントラバス・チューバ、
ティンパニ、シンバル、トライアングル、弦五部。
そして弦も最低でも四十人以上が動員されるという、
とにかく大編成の曲。
こういうこともありかなり心配したけど、
聴いてみるとこれがなかなか素晴らしい。
たしかに迫力とかはないけど、
その美しく詩的で清澄な瑞々しい響きに、
とにかく魅了されてしまった。
しかもそこには、
まぎれもないブルックナーの響きがある。
これには驚いた。
ただ残念なことにこの編曲が1921年に完成されたものの、
演奏される前に「私的演奏会」が活動停止を余儀なくされたため、
公開演奏されることなくお蔵入りしてしまったとか。
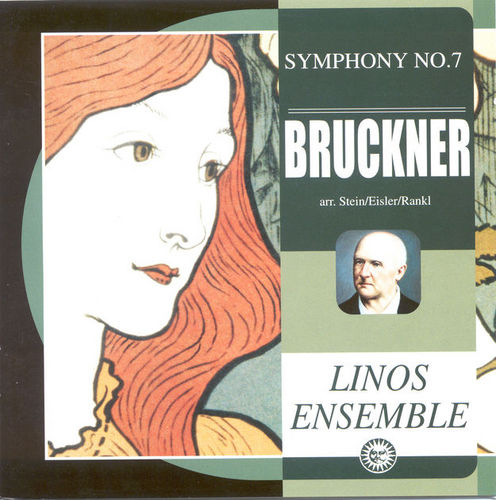
現在は上記の録音があるので、
もし機会があればぜひ聴いていただきたい内容です。
尚、今年(2018)の秋は、
この「私的演奏会」が開催されてからちょうど100年という、
記念すべき年に当たりますので、
できれば実演で聴いてみたいなあと思っていたらなんと、
◎
バラホフスキーとともに
バイエルン放送交響楽団の名手たちを迎えて
ブルックナー交響曲第7番(室内楽版)
http://www.kioi-hall.or.jp/20181205k1900.html
というコンサートがあるとのこと。
最後はこの嬉しい情報を書いて〆。
ハンス=マルティン・シュナイト(2007年記) [クラシック百物語]
●2018年6月5日追補
ハンス=マルティン・シュナイト氏がお亡くなりになられました・
自分にとって大きな音楽上の恩人を失った気分です。
今回以前書きましたそれをそのままこちらに上げ、
心より哀悼の意を表させていただきます。
本当に素晴らしい音楽の数々を与えていただきありがとうございました。
※以下2007年に記述しました本文が続きます。
ハンス=マルティン・シュナイトという指揮者がいる。
1930年生まれというから今年77歳。喜寿ということになる。
よく外国の指揮者が日本に住む、もしくは長期断続的に滞在し
演奏活動を続けるという例は
戦前の日本音楽史の創成期からままあったことで
そんなに珍しいことではない。
だがこのシュナイトの場合はちょっと違う。
シュナイトはミュンヘン・バッハ管弦楽団を15年以上率い
またそれ以外にも各国のオーケストラやオペラハウス
さらにはユース・オーケストラの指揮も行うなど
ドイツではまだ現役バリバリの指揮者だったし
その評価もかなりのものがあった。
それが東京藝大の教授に就任しただけでなく
自らの名前を冠して創設された合唱団の指揮を引き受け
ついには今年から神奈川フィルの音楽監督に就任した。
しかも今までその活躍の場でもあった地元ヨーロッパ、
そのヨーロッパにおける演奏活動をすべて引退しての日本での活動である。
こういうことはあまり例がない。
何度かの客演後三顧の礼 をつくされた後にトップについたものの
それでも地元の活動を引き続き続ける
もしくはそちらのでの活動を主にして日本でのそれを片手間にするという
そういうことがほとんどだったのだが
シュナイトは完全に日本でその音楽人生の総決算を締めくくる覚悟で
日本でのすべての仕事を受けている。
またそれらの仕事も自分のために創られた合唱団
東京からみれば地方の一プロオケである神奈川フィル
そして藝大での教鞭というぐあいに
いわゆるメジャーオケのトップに赴任して自分の音楽を披露するというのでなく
自分の音楽を伝えるために教えるという
ようするに「伝道」に近い精神でそれぞれの仕事に当たっているのだ。
ありがたいことにこの「伝道」の記録は
創設十年を超えたシュナイト合唱団の公演や
一昨年あたりからはじまった神奈川フィルとの公演などが
それぞれライブ録音として刻まれている。
このある意味極めて異例ともいえるシュナイトの演奏活動。
それは上記ニ団体の演奏に近年はっきりと成果としてあらわれており、
そのひとつひとつが聴き逃せないほどの素晴らしいものとなっている。
特に神奈川フィルとは練習も公開しており、
この稀有な関係がどのような過程を経て創造されていくのかを
自分の耳で聴き確かめるという貴重な機会をもつこともできる。
シュナイトについての感想は
http://www003.upp.so-net.ne.jp/orch/page236.html
に、まとめてあります。
とにかくシュナイトの音楽そのものを「伝える」という行為が
どのようなものでじっさいあるのか。
南関東(特に横浜)での演奏会が主ですが
聴く機会をもたれましたらぜひその点と、演奏するすべての方々の動き
そしてそれらに耳を傾ける聴衆の雰囲気にもぜひ注目していただきたい。

※↑2005年に録音された神奈川フィルとの「ブラームス/交響曲第1番」のライブ盤。
現在は入手が難しいかもしれません。

※↑2005年に録音されたシュナイト合唱団との「バッハ/ヨハネ受難曲、他」のライブ盤。
[LIVE NOTES WWCC-7540]
http://www.nami-records.co.jp/archive/20061124.html
(↑上記CDを発売しているNami Records社のサイト)
※(当項目は2007年1月書き込み、後に一部改正をしたものです。)
「巨匠の時代は終わった」という酷い発言の話。 [クラシック百物語]
「巨匠の時代は終わった」
と大声で叫んだ一部評論家の為、
そういう酷い空気ができた時代があった。
当時存命していた指揮者陣が、
稀に見る超豪華版だったにもかかわらずです。
しかもそれに一部雑誌も追従した為余計それに拍車がかかり、
昔はよかったみたいな懐古趣味ばかりが先に立ち、
今の指揮者に対して真摯に向き合おうとする、
そういう姿勢が著しく欠如してもOKみたいな、
とにかく今を生きる演奏家を侮辱し愚弄した、
そういう発言が大手を振っていた時代があった。
最初にことわっておくけど、
巨匠というのは何も年をとらなければなれないわけでなく、
若くても並みはずれた素晴らしい演奏をしていれば、
それを巨匠とよんでも何ら問題はない。
前述の最初のそれは、
そこの部分も無視した、
単なる老人指揮者礼賛至上主義に立脚しての発言であり、
じつは巨匠云々とは全然別次元の事を、
巧妙にすり替えイメージとして刷り込ませるという、
たいへん狡猾な発言だったのだ。
ひょっとすると単純に思い違いだったのかもしれないけど、
どちらにしても質が悪い発言と断言して問題ない。
21世紀に入り、
とくにここ数年かなり世代交代が進んでるいるが、
それでも全世代に渡って、
「巨匠」
とよばれていい指揮者が群雄割拠している。
こんな時代は自分もあまり経験が無い。
おそらく今後は今のこの恵まれた時代によって、
こういう馬鹿発言は淘汰され、
忘却の彼方に消えていくだろうけど、
二度とこういう無責任な、
ある意味言ったもの勝ちのような発言は控えてほしい。
(これが売名目的だったら絶体許せない。)
聴き手にとってこれは百害あって一利なしなのだ。
またこれに流されるように同調した、
一部音楽雑誌も今後はこういう発言に同調しないでほしい。
確かに毒のある発言は人を惹きつける力が強く、
雑誌としても美味しいネタかもしれないけど、
そういう目先の事ばかり追い続けていると、
そのうちそういう雑誌は飽きられ淘汰されていくだろう。
少子高齢化が進む昨今、
雑誌は年々どんどん厳しくなっていくだろうけど、
聴くパイをネガティブな発言により狭くする愚行を避け、
より広く聴き手に可能性を提示し、
パイを広げていくことこそこれからの雑誌の命題だと自分は確信している。
真面目な書き手と真面目な読者は、
想像以上にまだまだたくさん存在しているのですから。
繰り返しますが「評論家」という肩書をもった人が、
今の演奏家を愚弄し侮辱するような発言は、
今後絶対慎んでほしい。
いや、慎めよ!
〆
カラヤンのサンモリッツセッション [クラシック百物語]
カラヤンは別荘のあるスイスのサンモリッツにいたが、
この年から1972年の夏まで、
カラヤンはベルリンフィルのメンバーをこの地に招き、
一緒に夏休みを楽しんだというが、
その期間の数日を利用し、
カラヤンはいろいろとメンバーとともに、
バロック音楽や弦楽合奏を中心とした曲を、
たなりの量の録音を行った。
録音会場はサンモリッツにある「ヴィクトリアザール」となってますが、
これは「ホテル レーヌ ビクトリア」というホテルの中にある劇場の事で、
このホテルの公式サイトにも
https://reine-victoria.ch/en/
「A theatre – where none other than Herbert von Karajan conducted an orchestra – and a conference room with a wonderful view towards Maloja provide an elegant setting for events of all kinds.」
というふうにその事が記述してありますし、その写真も掲載されています。
最初のセッションは8月17日から24日にかけて行われ、
バッハの管弦楽組曲の2番と3番。
そしてエディット・ピヒト=アクセンフェルトを迎えて、
バッハのブランデンブルク協奏曲の1番から5番までが録音された。

6番のみは翌年2月にベルリンで録音されたようですが、
これが時間切れだったのか、夏の録音が不満だったのかは不明です。
その後1972年迄の毎年、
ほぼこの時期にカラヤンとベルリンフィルは、
いろいろと録音を行っている。
1965年は
モーツァルトのk.287、334、525、交響曲29&33番。
1966年は
フェラスとのバッハのヴァイオリン協奏曲1番と2番。
ヘンデルの合奏協奏曲5、10、12。
モーツァルトのk.247、251。
1967年は、
ヘンデルの合奏協奏曲 2、3、4、6、7、9

1968年は、
ヘンデルの合奏協奏曲 1、8、11
モーツァルトのk.239、136~138
同ホルン協奏曲全曲をザイフェルトと。
ロッシーニの弦楽のためのソナタ 1~3、6
1969年からは録音会場がホテルから歩いて10分程の所にある、
French Church "Au Bois", St. Moritz
https://www.engadin.stmoritz.ch/sommer/en/sightseeing/franzoesiche-kirche-au-bois/
という教会に変わった。
※ひょっとしたら教会は間違ってるかもしれません。もし間違ってたら申し訳ありません。
アルビノーニの弦楽とオルガンのためのアダージョ
パッヘルベルのカノンとジーグ
ボッケリーニの小五重奏曲
レスピーギのリュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲
モーツァルトの弦楽のためのアダージョとフーガ
ベートーヴェンの大フーガ
R・シュトラウスのメタモルフォーゼン
オネゲルの交響曲第2番
ストラヴィンスキーの弦楽のための協奏曲
というかなり幅のある曲目がこの時は録音された。
尚、この年は8月の上旬にもセッションが行われている。
1970年は、
コレルリ、マンフレディーニ、トレルリ、ロカッテリの合奏協奏曲。
ヴィヴァルディの協奏曲ものが6曲。
1971年のみEMIが録音を行い、
モーツァルトのクラリネット協奏曲、ファゴット協奏曲、
フルート協奏曲第1番、オーボエ協奏曲、
フルートとハープのための協奏曲、協奏交響曲。
ハイドンの交響曲第101番「時計」、交響曲第83番「牝鶏」
1972年は、
ヴィヴァルディの「四季」
ストラヴィンスキーの「ミューズの神を率いるアポロ」

というように録音が行われた。
当時これらの録音のいくつかは、
「粗製乱造」とか「豪華なBGM」とか、
いろいろな言われ方をされていたという記憶がある。
自分はこれらの全てを聴いた記憶はあるが、
正直まったく思い出せないものもある。
今これらのいくつかを聴き返してみると、
リラックスした音楽と、
今からみるとけっこう個性的な演奏というかんじで、
自分でも不思議なくらい楽しく聴くことができた。
もちろんこれはかつても今も、
正統的なバッハやヘンデルとはとてもいえないし、
アンサンブルも今風の線的で清澄感のある颯爽と締まったものでもない。
ある意味メンゲルベルクやストコフスキーのスタイルとは違うものの、
大時代的でユニークな演奏という気がした。
またソロをとっている各人も、
シュヴァルベ、ツェラー、ザイフェルト、ゴールウェイ、
コッホ、ライスター、ピースク、ヘルミスと、
ベルリンフィルの好きな方ならお馴染みの名手が揃っている。
カラヤンのバロックやハイドン、モーツァルトは、
今どれだけ評価され聴かれているかはわからないけど、
録音されてから半世紀経った今の時代に聴いてみると、
とにかくかつての価値観とはかなり違った、
いろいろと感じさせられるものがあります。
興味のある方はぜひ一度聴かれる事をお勧めします。
https://www.youtube.com/watch?v=fSAKvQ2-QQg
カラヤンのヘンデル
https://www.youtube.com/watch?v=nXmObq329JA
カラヤンのモーツァルト
尚、66年と68年のヘンデルではカラヤンはチェンバロも弾いています。