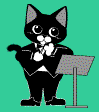トゥガン・ソヒエフ指揮NHK交響楽団を聴く。(1/21) [演奏会いろいろ]

2023年1月21日(土)
NHKホール 14:00開演
曲目:
ラフマニノフ/幻想曲「岩」作品7
チャイコフスキー/交響曲 第1番 ト短調 作品13「冬の日の幻想」
指揮/トゥガン・ソヒエフ
ソヒエフにとってこの1年は激動の年だった。一挙に手にしていた二つのポストを不本意な形で手放したことがそれだが、それでもこうして活動を続けられているのは本当に嬉しいし有難い。
この公演も昨年早々と決定し発表されたことは本当に嬉しかった。これはN響にも大きな賛辞を贈りたい。
この日はラフマニノフとチャイコフスキーがともに二十代の時に作曲した若き日の作品。
まず最初にラフマニノフ。
冒頭からおそろしく雄弁な低弦の歌声からはじまったこの演奏だが、終わってみると暗いながらも瑞々しい雰囲気に満ちた演奏に仕上がっていた。ラフマニノフだとけっこう陰鬱な表情に引っ張られる傾向が強くなりがちだけど、今回そうはならなかった。あと木管のとても冴えた響きが印象に残った。
このあと一呼吸入れてチャイコフスキー。
ふつうサイズのコンサートならラフマニノフのあとさらに一曲あってその後休憩、そして後半のチャイコフスキーとなるところだけど、NHKホール改修終了後再開したN響定期では、この日のように休憩なしで70~80分ほどで終了するプロをひとつつくっており(「Cプロ」がそれにあたっています)、今回はそのためこのような流れになった次第。
そして始まったチャイコフスキー。
第一楽章はとても快適ともいえるくらいの爽快な感じではじまり、全体的にもオーソドックスな雰囲気の演奏になっている。ただとても洗練された演奏で、この曲がまだ国民楽派的要素が濃いということで、中には濃厚な演奏を仕掛けてくるケースがあるけど、初稿やその後出された初版ならともかく、今回よく演奏される三稿のようにヨーロッパを旅するようになり、作風の西欧化が強くなっていった時期に手直しされた稿を使うならば、こういう洗練されたやり方も有りという気がした。
(因みにこの曲の初稿は、第二交響曲の初稿同様第一楽章に大きな変更があるらしく全体的に曲も長かったらしい。いつか可能なら第一第二の二つの交響曲の初稿を続けて聴いてみたいものです)
続く第二楽章は一転遅めの悠揚としたテンポの演奏となる。印象としては第一楽章の倍かかったのではないかというくらいたっぷりとした感じだったけど、濃厚な油絵というよりはむしろ水彩画のような感じがする演奏で、このあたりがちょっとユニークだった。
第三楽章は第一楽章同様オーソドックスな演奏だったが、第四楽章は冒頭第二楽章のような遅めではじまるが、次第に第一楽章のように爽快になっていく。で、このまま最後までこの調子で行くのかと思ったら、コーダの終盤で大きく仕掛けてきた。
33年前に聴いたスヴェトラーノフとソビエト国立響では、スネギリョフという屈指の剛腕ティンパニ奏者がいたことから、オーチャードホールの舞台が抜けるのではないかというくらいの強靭な打ち込みを軸にした、言わば「縦ノリ」に近いような音楽で聴衆を驚かせたが(この演奏は録音されCDでも発売されたが、そこではその凄さがあまり伝わってこないのが残念)、この日のソヒエフはむしろ構え気味で。しかも途中で弓を弦にベッタリつけたような感じで大きな弓使いを要求してきたため、突然音楽の歩幅が大きく強靭になり、最後はまるで巨人の歩みのような音楽へとなっていったのには驚いた。
それはなにか大昔のソ連系の指揮者のような、それこそ先祖返りしたかのようだった。
10年前ソヒエフとN響のチャイコフスキーもかなり強烈だったけど、今回はまた違った意味で強い印象を残してくれました。
このあとソヒエフはサントリーや高崎でバルトーク、ラヴェル、ドビュッシーの公演がありますが、その後はまた来年1月のN響第2001回目の定期公演で、曲目は、ビゼー(シチェドリン編)の「カルメン組曲」、ラヴェルの「マ・メール・ロワ」 と「ラ・ヴァルス」を指揮するとのこと。
次回もまた楽しみですが、その頃にはウクライナでの戦争も終結し、ソヒエフがより演奏に専念できるより良い環境になっていてほしいものです。
以上で〆。
小林研一郎指揮ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団を聴く。(1/17) [演奏会いろいろ]

2023年1月17日(火)
サントリーホール 19:00開演
曲目:
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73《皇帝》
チャイコフスキー:交響曲第5番
ピアノ/仲道郁代
指揮/小林研一郎
ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団を初めて知ったのは、1974年にフェレンチクと初来日をしたときで(当時の名前は「ハンガリー国立交響楽団」)、その時はNHKホールで演奏したベートーヴェンの「英雄」等がテレビやFMで放送された時だった。
その同じ年に今回指揮を担当する小林研一郎さんが第1回ブダペスト国際指揮者コンクールで第一位を獲得、その後このオケと半世紀近く関係を持つことになったのだが、にもかかわらずそれからじつに半世紀近く経って、ようやくこのオケの実演を今回初めて聴くことになったが゛このあたりは巡り合わせの悪さもあってしかたない部分もあった。
また小林さんがプロオケを指揮するのを聴くのも、じつに45年ぶりというのだがらこれまたあれという気はするけど、いつでも聴けるとあとあとまで伸ばすとこういう「いつのまにか」的なことが起きるという、これはひじょうに悪い例だ。
というわけで些か気まずい部分もあった演奏会だけど、この組み合わせのチャイコフスキーの5番はかつてブダペストで演奏された時、センセーショナルなほどの話題を生んだということを以前聞いたことがあり、いつか聴く機会があればということでようやく今回行くことがかなった次第。
当日券はなかなか列が切れなかったようで会場もかなりの入りだった。
前半の「皇帝」。ソロの仲道さんがこの日本ツアーに参加するのはこの日のみ。
オケは14型通常配置で演奏。
演奏は安定感のある、それでいてどこか優雅で風格のある演奏。
仲道さんのソロも爽やかで、そこにはちょっと初期ロマン派的というか、シューベルト風ともいえるような趣も添えられているようにも聴こえた。
そういう意味では歌謡性の強い「皇帝」といえるのかもしれないが、かといって場違いという感はまったくなく、むしろこれこそ王道というかんじすらした。
これには小林さんの正面から外連味なく描き切った音楽が大きかったと思う。
とにかくユニークだけど王道という、相反するような要素が絶妙にブレンドされた聴き応えのある「皇帝」でした。
この後仲道さんがアンコールでシューマンの『謝肉祭』より「ショパン」を演奏。
休憩20分。外は冷たい小雨が降っていた。
そして後半のチャイコフスキー。編成は前半と同じ14型、ホルンは通常より一人増やし五人。
しかしこれはもう小林さん会心の演奏だったのではないだろうか。
第一楽章は緩急がかなり大きい。
序奏はスヴェトラーノフの晩年なみに遅く重たく暗いつくりだが、主部に入ると一転颯爽としたそれこそ若手指揮者がとるようなテンポで音楽が進む。その後は曲想が変わる度にテンポも表情も大きく変わる。
それはまるで舞台転換が次々と行われる舞台をみてるようで、ある意味視覚的なチャイコフスキーというかんじだった。
それにしてもオケが素晴らしい。
決してパワーや音の分厚さで勝負するのではなくむしろその逆といえるオケで、線的ともいえるほどどのパートも素朴かつクリアなため決して厚ぼったくならない。また決まるところはしっかり決めてくるし、音の芯はかなり強い為どんな時も痩せたり頼りなくなることもない。そして何よりも全体の意志統一がしっかりとることができるオケのためか、小林さんの多彩などの表情付けにもしっかり全体で歌いぬいてくるので、その説得力が半端ではない。
これが第二楽章で圧倒的な説得力をもって迫ってくる。ここでは小林さんは第一楽章ほどのテンポの変化はつけていないせいかオケの歌いこみがより強く前面的に出て来るのが本当に秀逸だった。
あとこのオケの低弦はかなり強力で、のべつ幕無しデカい音を出すわけではないが、第二楽章の冒頭など、要所要所でかなり説得力のある強い音を出している。総勢六人という人数を考えると正直ちょっと驚いた。
この第二楽章で熱演のためかヴィオラの一人が弦を切ってしまったらしく楽章終了後舞台裏に退場した。続く第三楽章と第四楽章の途中で出て来たが、小林さんが切れ目なくアタッカで行ってしまったため冒頭の音楽が演奏される中再登場となってしまった。これが正解なのでしかたないかもしれないが、聴いている側がこれによって気持ちが切れることがないくらい、第三楽章、そして第四楽章ともひじょうに濃密な音楽が展開された。
特に第四楽章のコーダは決して激しく煽ったりすることなく、素晴らしいくらいの燃焼度と輝かしさを兼ね備えたものになり、聴いていて心を鷲掴みにされるような気になったものでした。そしてここでのオケの歌いぬきもまた最高潮に達していました。
演奏時間はだいたい50分を少し切る位。
ブラヴォーは出せないものの会場はかなり湧き、アンコールとして超個性的な、それこそメンゲルベルクもビックリなみのブラームスの「ハンガリー舞曲」第五番が演奏されるなど、途中小林さんのMCを挟んで盛沢山の幕切れとなりました。
終演時間午後9時20分頃。
最近、小林さんの音楽は諄いとか暑苦しいとか、以前聴いた小林さんのイメージとは違うそれをよく目にしていたので、ちょっと気になっていましたが、今日のそれに関して自分はそういうことは感じませんでした。やはり実際聴いてみなければ分からないものです。
小林さんといい、ハンガリーフィルといい、とにかく大満足な演奏。
しかし小林さん。本当に82歳なのだろうかというくらい若々しい指揮ぶりでした。
以上で〆です。
ところでPブロックで何か手に持って広げていたけど、声出し厳禁だとこういう形になるものなのかと思ってしまった。
今年中にはコロナも一段落してほしいです。
エリアフ・インバル指揮東京都交響楽団を聴く。(12/20) [演奏会いろいろ]

2022年12月20日(火)
東京芸術劇場 14:00開演
曲目:
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73《皇帝》
フランク:交響曲 ニ短調
ピアノ/マルティン・ヘルムヒェン
指揮/エリアフ・インバル
来年初来日から50年を迎えるインバルは現在86歳。
1980年に86歳で来日したカール・ベームが椅子に座った指揮姿と、音楽にも多少の衰えを感じさせていたことを覚えている者としては、インバルのこの日の指揮姿と音楽に微塵の衰えもみせないそれには、いくら世代が違うとはいえ驚きすら感じてしまった。
これからもブロムシュテットかそれ以上に末永く元気に指揮を続けてほしいものです。
因みに初来日時のインバルは読響に客演しマーラーの5番を演奏しているが、その時一緒に演奏した曲が、別の日にブルックナーの前に演奏されたウェーベルンの6つの小品だった。来年の来日が無いので一足早くその時の曲を思い出のそれとして取り上げたのだろうか。
というわけで前半のベートーヴェン。
とにかく雄弁かつ剛直で構えの大きなインバルのそれにちょっと驚く。また細かい表情、特に弦の動きがとてもクリアに聴こえ、そのせいかときおり室内楽的な雰囲気も醸し出すようにも聴こえ、ある意味とても新鮮な感じすらした。
ヘルムヒェンのピアノは詩的ともいえる繊細な表情と流動感がクリアな響きの中に織り込まれた好感のもてるものだったけど、インバルのあまりにも堂々とした演奏のため、自分の聴いていた場所のせいか、ピアノがやや圧倒されかけているように聴こえることが多く、インバルの「皇帝」の様相を呈したかのように聴こえてしまった。
聴き応えはあったが、正直インバルの音楽のみかなり強く印象に残った演奏となりました。
このあとヘルムヒェンのアンコールとして、シューマの「森の情景」より第7曲「予言の鳥」が演奏されたが、こちらの方が自分はヘルムヒェンの音楽をより強く感じる事が出来た。彼の演奏でシューマンはもちろんだけど、グリーグの作品集も聴いてみたいと思った。
この後20分の休憩の後フランク。
ブルックナーを得意とする指揮者の多くがブルックナーと同時代の、そして同じく傑出したオルガン奏者でもあったフランクを指揮しているが、インバルは録音されていないこともあって強く興味を持ったことと、2018年にプラッソンと新日本フィルで神懸かり的ともいえる空前の大名演に接して以降、この曲に対しての印象が大きく変わった事もあり、今回の演奏は自分の中でさらにどう化学変化を起こしてくれるのかという楽しみもありました。
そしてこの日のインバル。
それはプラッソンを聴く前のこの曲のイメージに近いものだった。ただこの曲のもつ晦渋的な雰囲気はここでは皆無で、おそろしいくらい潔く表情のふっきれた、それでいて前半のベートーヴェン同様、雄弁で剛直なそれが圧倒的なまでに迫ってくるようで、クレンペラーの音盤に匹敵するほどのこの曲のエネルギーを引きずり出したかのような演奏となっていた。
また他の演奏以上にパイプオルガンの音を想起させるような響きが管楽器から聴こえてきて、曲もタイプも違うけど、ちょっとティーレマンで先日聴いたブルックナーを思い出してしまった。
(この時なぜかこの曲の作曲次期がブルックナーが第八交響曲を書いていた時期と重なっていることを思い出した)
この全曲の半分近くを占める第一楽章も、そのせいかどこかブルックナー風の趣が感じられ、最後の方の押しては返す大波のような音楽がさらにそれを強く感じさせられました。
続く第二楽章。プラッソンの時は神懸かり的なイングリッシュホルンのソロを軸に詩的かつ崇高な音楽が紡がれていったのとは違い、イングリッシュホルンのソロも大きな音楽の中に包括させ、オケが一丸となって築き上げていくそれもプラッソンとはまた違った素晴らしさがありました。
またインバルはこの日のフランクでかなり緩急をつけた演奏を展開しており、この曲をブラームスに近しいとよく言われるそれとは真反対の、むしろワーグナーに強い影響をうけていると言わんばかりの濃い表情をつけていたのが面白く、これがこの演奏を他のフランクの演奏とかなり異なるイメージを与えていたようにも感じられました。
そして終楽章は今までのそれらすべてがひたすら最後に向かって高揚していくようで、最後はじつに輝かしく充実した響きに達していました。この終楽章も今迄はブルックナーとイメージ的あまり重なる事はなかったのですが、今回はブルックナーの1番のウィーン版となんとなくイメージさせられたりで、そういう意味でかなりユニークかつ強力な説得力をもった演奏だったという気がしました。
プラッソンがフランスの立ち位置からみたそれなら、インバルがドイツの立ち位置からみたそれというかんじで、しかもブラームスよりはブルックナーに立ち位置が近いという意味で、独得なものだったという気がしました。
しかし正直かなりタフな演奏で、ホルンを一人増員させていたものの、かなりオケもしんどかったのではと思いましたが、それを感じさせない熱演となりました。
四年前のプラッソンとはまた違った満足感を得られましたが、プラッソンとインパルと真反対ともいえるこの曲の名演を聴いたことで、この曲のもつ奥深さと難しさというのもなんとなく分かったような気がしました。
この曲、想像以上に新しさと古さを絶妙なバランスで同居させた曲で、しかも下手なドラマを持ち込む事なく、音そのものをしっかりとらえていくことで音楽の深部に辿り着く事ができるような、ある意味ハイドンと近しい性格も結果的に持ち合わせた曲なのかもしれません。
尚、この日はカメラやマイクがあったので、来年あたり放送されるかもしれません。このあたりは楽しみに待ちたいと思います。
というわけで今年の演奏会はこれで終了です。
来年はソヒエフとフルシャを予定していますがその後は予定なし。まあコロナで三年も苦しんだのでこの三か月は自分としては異例な程演奏会に行きましたが、これからはまた静かになると思います。
しかし8月のポベルカから本当にいい演奏会ばかりに恵まれ本当に幸運でした。ありがたいことです。
以上で〆
と、綺麗に終わりたかったのですが、そうも行きませんでした。
①
とにかくこの日終演後の聴衆の多くが掟破りのオンパレード。
コミケでこれやったらスタッフがブチ切れまくる事必至といったほど、主催者のお願いを黙殺するは無視するはで、ほんと情けないにも度が過ぎるという悲惨なものでした。
年をとると日本人にもかかわらず日本語が分からなくなってしまうのかなあと、かなり愕然とさられました。ほんと酷かったです。
②
あと都響の現在の当日券対応。
その日の一時間前迄にweb受付のみの対応というのはやはりいただけない。
これでは急に都合がついた、開演少し前に偶然会場前を通りかかって初めて知った。というこういう人たちに門前払いで「お帰り下さい」というのと同じで、あまりにも一人一人のお客様に対して不遜だし、民間なら頑張って一枚でも多く売ろうという努力を必死でするところを、都響みたいに公的な所におんぶにだっこされてるところは、そういう苦しみとは別世界の殿様商売でもしているのだろうかと、そう勘繰りたくなるほど血の通ってない悪い意味でのお役所対応にみえてならない。
これが2020年頃ならともかく、行動制限をかけない時期でもこれというのは本当に正解なのだろうか。
自分は正直これには強い疑問と不信感をもっています。
もっとも嫌なら来るなと言われればそれまでなので、その場合は二度と来ません。
パーヴォ・ヤルヴィ指揮ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団を聴く。(12/8) [演奏会いろいろ]

2022年12月8日(木)
東京オペラシティコンサートホール 19:00開演
曲目:
ハイドン:
交響曲第102番 変ロ長調 Hob.I:102
交響曲第96番 ニ長調Hob.I:96《奇跡》
交響曲第104番 ニ長調 Hob.I:104《ロンドン
今から二十年ほど前、指揮者の飯守さんが「ハイドンをやるとお客が入らないから嫌がられる」と言った事があるけど、この日はティーレマンのブラームスあたりとぶつかったり、「驚がく」や「時計」といった人気作品を外しているにもかかわらず、ホールは意外な程人が入っていた、だいたい八割以上は埋まっていたと思う。
これにはヤルヴィの人気と信頼というのも大きかったかと。
自分はドイツ・カンマーフィルを聴くのは、ハーディングとムローヴァかがベートーヴェンをやった時以来なので21年ぶりにということになる。あの日も確か対抗配置だったけどこの日も同じ。なんかいろいろと懐かしい。
それにしてもこのプログラム。
自分はハイドンの交響曲の中で大好きな曲ベスト5のうち3曲も入っていたから狂喜したものの、「驚がく」「軍隊」「時計」といった人気曲をすべて外したこのプロには招聘した側はさぞ不安になったのではないだろうか。
とにかくなかなかの入りで開演。
この日は前半102と96。
20分の休憩後も後半が104だったのですが、一環していたのは、
フォルムがしっかりしている
オケの発する熱量、とくに管楽器が凄い
その管楽器はソロもアンサンブルも絶妙で、弦との呼吸もピッタリ
全曲を通して颯爽とした運び、それに流動感とリズムのキレが心地よい
新しいスタイルにもかかわらずどこか懐かしい旧いスタイルを想起させることもある
といったところだろうか。
特に音楽の颯爽とした運びはかなり新鮮で、本来アダージョの102の第二楽章も、他の二曲同様、まるでアンダンテのようなスピードで演奏されていた。ただそれでいて無味乾燥になることなく、常に瑞々しさと木管を中心とした洒落たニュアンスが織り込まれているのが素晴らしい。
また102と96のメヌエットのノリのいいリズムが秀逸で、思わず踊りだしたくなるほど聴き手を強く揺さぶってくるものがあった。
あと96のメヌエットでは、トリオにおけるオーボエとフルートの表情付けが絶品で、演奏終了後この二人に対する拍手がとても盛大に起きていました。
そして終楽章のスピード感もまた爽快そのもので、クライバー的ともムラヴィンスキー的ともいえる疾走感が最高。特に96のそれがホール全体を熱気に包みこむような熱演で、こちらもまた盛大な拍手が起きていました。
これに対して104は冒頭からベートーヴェンの出現を予期したかのような凄みのある音楽を、40名程のメンバーとは思えない程の強大な音でそれを見事に表現していました。
(因みにハイドンが104番を完成した年は、ウィーンでベートーヴェンがピアノ協奏曲第2番を初演しウィーンデビューを飾った年でもある)
ハイドンが訪ねたころのロンドンのオケは四十名程の編成だったので、この日のカンマーフィルとほぼ同人数だったとか。また当時のロンドンのオケはとても技術的に優秀かつダイナミックレンジが広く、ハイドンがイギリス訪問時に書いた12曲、通称「ロンドンセット」はそれを活かそうとして、それ以前の曲よりダイナミックな曲が多かったと言われており、この日のヤルヴィが味わいや洒落っ気の中にも、ダイナミックなカッコよさを織り込んでいたのはここの部分を意識していたのかも。特に104番はかなりそれが強く感じられ、終楽章の終盤に向かっての高揚感も抜群でした。
そんな感じで、三曲とも聴きどころ満載かつ、気持ちいいくらい音楽が颯爽と流れていくので、どの曲も聴き終わるのがもったいないくらい終わるのが早く感じられました。
できればまたの機会に、82、86、92、といったロンドンセット以前の名曲も聴いてみたいところです。
モーツァルトの最後の交響曲とベートーヴェンの最初の交響曲の間に位置する、これらのハイドンによる交響曲群。
これを機会に「驚がく」「軍隊」「時計」以外ももっと広く聴かれ演奏してほしいものです。
因みにアンコールは弦楽合奏の曲で、
ハンガリーの作曲家、レオー・ヴェイネル(1885 - 1960)の、
「ディヴェルティメント」第1番作品20 (1934)より 第1楽章
でした。
以上で〆
それにしても繰り返しますが本当にこの日のハイドンのオケの熱量は特筆もの。
おそらくベートーヴェンもさぞや名演になることでしょう。
聴きに行けないのがなんとも残念です。
クリスティアン・ティーレマン指揮シュターツカペレ・ベルリンを聴く。(12/6) [演奏会いろいろ]

2022年12月6日(火)
東京オペラシティコンサートホール 19:00開演
曲目:
ワーグナー:《トリスタンとイゾルデ》前奏曲と愛の死
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調(ハース版)
バレンボイムが体調不良の為、指揮がティーレマンに変更。
そして曲目が6日のみ全面変更となった。
シューベルト:交響曲第7番ロ短調 ≪未完成≫作品759
チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調作品64
↓
ワーグナー:《トリスタンとイゾルデ》前奏曲と愛の死
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調
自分などはこの変更に思わず狂喜してしまったが、みんながみんなそうではなかったとのことで、これが場所によって悲喜こもごもの状況を作り出したらしいけど、自分のいた所はそういうことはあまり感じられなかった。ただ妙にまわりの席がごっそりと空いていたのが、個人的には嬉しかったがこれまた妙に気になった。
ところで自分はティーレマンを実演で聴くのは今回が初めて。
過去何度が聴く機会はあったが何故かあまり積極的に聴きに行こうとしなかった。理由は、過去の彼の録音にいまいち興味を惹かれなかったことが大。
ただ一度実演で聴いてみたいという気持ちもあったことは事実で、それで今回聴きに行くことに相成りました。
シュターツカペレ・ベルリン(以下、SKBと略)を聴くのは32年ぶりで、彼らのブルックナーを聴くのは1978年以来じつに44年ぶり。その時は指揮がスイトナー、会場が東京文化会館の改修関係で各社各団体がホール不足に苦しんだ時期だったため、今では考えられないかもしれないが、かの渋谷公会堂だったという公演。
曲目は前半が「ジークフリート牧歌」、後半が今回と同じブルックナーの7番(ただしその時はノヴァーク版)、そしてアンコールにモーツァルトの「フィガロの結婚」序曲というもの。
この公演もなかなか忘れ難い印象があり、そんな事も手伝い余計とても楽しみな演奏会となりました。
それにしてもこの日のプロ。
古いファンの中には、1986年のヨッフムとコンセルトヘボウの来日公演を思い出されたかもしれませんが、じつはこの日、文化会館とオペラシティの違いはあれど、このヨッフムの時と聴いていた席が今回かなり似たような場所で自分は聴くことになったので、その時の事もまたちょっと思い出してしまいました。
(あの時は開演前、立っていて膝ががくがくするくらい緊張した事を覚えています)
まず前半のワーグナー。
対抗配置のSKBによるトリスタン。
ひじょうに神経の張った弱音。その後フレーズを繋ぎながら高揚する時はやや前のめりになるほど一気呵成、鎮静化して行く時は音楽を止めようとしているかのような緩急をつけるが、わざとらしいアッチェランド等は皆無。
そして何よりもまるで部隊が見えて来るかのように劇的。この時、仕草もちょっと似ていた事から、かつて東フィルを指揮してこの曲を演奏していたハンス・レーヴラインを思い出した。音楽の構えとかはティーレマンの方が大きいけど、なんか劇場の叩き上げの共通項みたいなものをどこか感じてしまいました。
しかし聴かせ方があざといほど旨い。さすがという感じでした。
この後休憩20分。そして後半のブルックナー。
こちらも先のワーグナーで見せた特長が随所にあらわれていた。
第一楽章からいろいろと細かく弱音の表情、緩急の使い分けもなかなか計算されている。このあたりの寸法の取り方、音楽の呼吸のバランスのとり方の妙は、オペラで鍛えた手腕によるものなのかも。
第一楽章のコーダは焦らず悠揚と音楽を高揚させていたが、この日のSKBのブラス、特に低音の充実感は素晴らしいものがあった。
44年前も、同様にブラスの低音が素晴らしく、それが管弦一体となった木目の響きの中に絶妙な光彩と存在感を放っていたのですが、この日はさすがに44年前程の素朴な木造感は、その当時より洗練されたことで薄まった感じはするものの、それでも随所にかつての木目風の響きも感じられ、おかしな例えですが「落ち着いた光沢感のある総檜造りのパイプオルガン」とでも形容したくなるような、何とも味わい深い音をこの日は感じました。
第二楽章ではその特徴がさらに強くなったのですが、にもかかわらず面白い事にじつはここまでそんなに宗教的な崇高感は感じられず、むしろ強いタッチによる生々しさの方が何故か強く感じられた。
そういえばティーレマン同様ワーグナーに定評のある飯守さんも、この曲で同様な傾向の演奏をしていたのを思い出す。何かこの二人のこの曲に対するワーグナー視点からみたような共通した意識のようなものでもあるのだろうか。
ところでこの楽章。ハース版にもかかわらずあのクライマックスのところでシンバルとトライアングルが使用された(ただしティンパニーは無し)。これはなかなかユニークなものだったが、下手をするとシンバルが変に浮きかねないが、SKBの地力と尋常ではない音楽の立ち上がりがそのあたりを呑み込んでしまうような感じになったためそのような感じはせず、むしろ弦を中心とした流動感を強く感じさせる非常に新鮮な説得力の方を強く感じた。
このあとのワーグナーの葬送はティーレマンがこの日かなり拘った弦の弱音の表情の美しさが際立った。そしてワーグナーチューバの音はまるでパイプオルガンのように素晴らしい響きを奏で音楽は終了。聴き終わった後、思わずマスク越しに大きく息を吐くほど強く気持ちを集中させられた演奏でした。
続く第三楽章はかなり気合の入った演奏で、スケルツォの後半は音楽が前のめりになるくらい猛烈な演奏になり、弦楽器奏者の多くが全身で音楽を奏でているようにみえるほどの熱演と化す。ただそれでもフルトヴェングラーのような狂気の世界に突入するような事が無いのはティーレマンのバランス感覚の表れかも。
そして第四楽章、慌てることなくしっかりと歩を進めた流動感と管楽器の分厚さを交互に前面に出した、じつに聴き応えのある音楽が連続する。そのせいかこの楽章に演奏によってときおり感じる「物足りなさ」や「あっさりし過ぎ感」がまったく感じられず、先行するどの楽章にも位負けしない程の音楽がそこでは鳴っていた。
それにしてもSKBのこの日の低音はとにかく異常なくらい凄かった。ここまでの威力を感じたのは自分が聴いた中では1986,年のヨッフムが指揮した時のコンセルトヘボウくらいだろうか。
コーダ―前のトゥッティではまるでパイプオルガンが鳴り響いたかのような見事な響きだった。
そしてコーダの輝かしい高揚感も特筆ものだったが、最後の音が終わった瞬間、指揮者が構えを解く迄静かだった聴衆もブラボー。
とにかく終わってみればとんでもないくらいの凄い演奏でしたが、気づいたら最後自分はかかとを浮かせつま先立ちで聴いている事に気づいた。余程聴いていて力が入ったのだろう。こんなことはあまり記憶にないので我ながら驚いた。
ティーレマン自身もかなり会心の出来だったのか、舞台に戻る度にスタンディングオベーションをする聴衆がどんどん増えていく光景に余程嬉しかったのか、とにかく終演後は終始上機嫌にみえた。
二度のカーテンコールの間には、舞台に残っていたブラス奏者の所に小走りに賭けよったりしていた。
(はっきり見えなかったが、みんなで並んで写真をとってもらっていたようにみえた)
しかしティーレマンも素晴らしいけど、自分はSKBに心底感嘆してしまった。
もちろんオケとしての技量や味わいもそうだけど、それ以上にブルックナーをあれだけ自分達の中に取り込み一体化したかのような没我の演奏をしながら、あそこまで音楽を高みに押し上げた底力というかスピリットに感動すらしてしまった。
これが伝統をもった超一流のオケの本気なのだろう。
あと正直このプロがこれ一回だけとはほんとうに残念。
もし急遽このプロで追加公演をしてくれたら、札幌でも鹿児島でも聴きに行くと思う。本当にそこまで思わせるくらい聴かずに死ねるかレベルの超名演だった。
あとひとつ気になったのは、けっこうマイクが散見していたけど、この日の公演、録音とか正式にされていたのだろうか。録音されていたらかなり嬉しいです。
以上で〆・
しかしネットでは無料招待された子供たち云々という声がけっこうあった。当初のシューベルトとチャイコフスキーならともかく、この二曲はあまりにもハードルが高かったようです。
それこそ映画鑑賞で、当初は「ドラえもん」だったのが、都合で「ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン」になったようなものだったのかも。
せめて「田園」「運命」だったらよかったのかもしれないけど、それだと今度は自分が行かないからなあ。
ここの部分だけはちょっと致し方なかったとはいえいろんな意味で残念でした。
因みにこれは招待されたお子様だけでなく大人でもそこそこいたようです。これもまた残念。
あとプログラムが高いというけど、カラヤンが1977年に来日した時は、東京公演と大阪公演が各千円で別々に販売されていた。
当時の価格としてもあれだったけど、日本公演のプログラムが二つに分かれていたのにはかなり驚いた。もっとも自分の購入した東京公演のプログラムは、大きさこそ今回の物より小さいけど、厚さは数倍ありましたが。
ファビオ・ルイージ指揮NHK交響楽団を聴く(12/4) [演奏会いろいろ]

2022年12月4日(日)
NHKホール 14:00開演
曲目:
ワーグナー/ウェーゼンドンクの5つの詩
(メゾ・ソプラノ:藤村実穂子)
ブルックナー/交響曲 第2番 ハ短調(初稿/1872年)
地味だけど噛めば噛むほど味の出るようなプロ。
まず前半は藤村さんのワーグナー。
藤村さんは以前、川瀬賢太郎さん指揮する神奈川フィルとのマーラーの「リュッケルトの詩による5つの歌曲」を聴いて以来。
あの時も素晴らしかったけど、今回のワーグナーもまた良かった。その深く説得力のある声は相変わらずだけど、静かに歌っていてもあの巨大なNHKホールの隅々まで無理なく届き響くその声に驚嘆してしまった。
これが世界レベルの歌なのかとあらためて納得させられたものでした。
またこのバックを受け持つルイージ指揮N響の細やかな表情と陰影に満ちたその響きが絶妙で、特に第三曲「温室で」の「トリスタン」の響きにおける、ステンドグラスに陽光が当たる事で微妙にその色合いが変化していくかのようなそれはまさに絶品で。N響がここまでの演奏ができるようになったのかと、ちょっと嬉しくなってしまうほどでした。
このあたりはルイージの卓越した指揮によるところが大だと思いますが、歌と言い指揮といい申し分ない演奏でした。
演奏は弦12型。
このあと休憩が20分。そして後半。
じつはブルックナーの2番を実運で聴くのは今回が初めて。
音盤としては1975年秋のジュリーニ指揮ウィーン響の来日記念盤として発売されたものを聴き始めて以来というからけっこう長い。
ただこの曲は当時「若書き」の曲としてあまり評価されず、日本初演もその前年のブルックナー生誕150年時に、ペーター・シュヴァルツ指揮札幌交響楽団によってようやく行われたくらい。
(N響はこの二年後にサヴァリッシュの指揮で演奏を行った)
音盤もこの当時、ジュリーニとシュタイン指揮WPO、ハイティンク指揮ACO、ヨッフム指揮バイエルン放送があったくらい。
その後は音盤も演奏会でのそれも増えたけど何故かなかなか自分は聴くことがかなわなかったので、ようやくという感じだった。
ただ今回演奏されたのはよく聴かれる1877年稿ではなく初稿ともいえる1872年稿で、第二楽章と第三楽章の演奏順が入れ替わっているのをはじめかなり1877年稿とは様相が異なっている。
特に1877年稿がかなりの素材を「作曲家」ブルックナーによって見通しとまとまりを良好にするため切り捨てられることになってしまったのに対し、この日演奏された1872年稿は切り捨てられる前に即興演奏の大家であった「演奏家」ブルックナーの閃きによって生まれた多くの素材が、バランスやみてくれそっちのけで盛り込まれている。
なので指揮者にとってこの1872年稿は魅力的な素材が目の前に多く展開されてはいるものの、手際を間違えるとかなり冗漫になりかねない曲であるだけに指揮者のそれがかなり問われるものとなっているはずなのですが、この日のルイージにはそんなことを微塵も感じさせず、じつに素晴らしい演奏を展開していました。
この日のルイージの演奏はとにかく丁寧(弱音の表情などかなり細かい)。そしてじつによく歌う。
このためこの曲がかつて言われたような若書き的弱さも感じなければ、バランスや見通しの悪さ、それに冗漫な趣も感じさせない。むしろこれで決定稿でもいいのではないかと思わせるほどの充実感がそこにはあった。
またこの演奏会では弦を中心とした濁りの無い晴朗感がじつに心地よく、特に第二楽章のトリオや第三楽章ではそれが強く感じられたが、ルイージと同じイタリアのジュリーニとこのあたりどことなく似ているような感じを受けた。ただ使っている稿が違うせいかジュリーニ程の流麗感はこの日のルイージには感じられなかった。
このような感じで第三楽章までは本当に曲への印象の再考を迫るような感じだったが、終楽章はさすがにそうはいかないくらい生煮えのような(それこそブルックナーの第九の未完の終楽章のような)部分があり、このあたりは無理せず巧みに捌いていったように感じられた。
最後、じつはちょっと注目していたコーダの弦の低音のみが第一主題を演奏するところ。
かつてアイヒホルンがこれに否定的なそれを表していたが、思ったよりはっきり聴こえたものの、やはり埋没観は否めなかった。それともブルックナーはあえてその埋没観を何某かの理由で狙っていたのだろうか。ただこの日の演奏は埋没観こそあれ、それを補って余りある高揚感が見事で、そのため物足りないという感じはありませんでした。
と、いろいろ考えさせられたものの、終わってみればじつに充実感のある中身の濃い演奏で、この稿を使ってここまでできる指揮者はそんなにいないのでは?というくらいのものでした。
ルイージとN響の今後にさらに期待を持ちたいです。それにしても本当にN響はヤルヴィ以降大進化しました。驚きです。
尚、ブルックナーの演奏時間は楽章間のインターバルを含め約70分。因みにジュリーニの77年稿ノヴァーク版による演奏は58分です。
以上で〆
といいたいところですが、一部の拍手が早いという不満も多少あったものの、それ以上に「だらしない事演奏中にするなよ」と言いたくなるような人がいて愕然。あれ。後ろに人がいたら喧嘩になっていたかも。
NHKホールの人たちは近いうちにそこそこな騒動が起きる事を覚悟しなければいけないのかも。
トマーシュ・ネトピル指揮読売日本交響楽団を聴く(11/20) [演奏会いろいろ]

東京芸術劇場マエストロシリーズ
2022年11月20日(日)
東京芸術劇場 14:00開演
マーラー:歌曲集『さすらう若人の歌』
マーラー:交響曲第1番 ニ長調「巨人
バリトン=ヴィタリ・ユシュマノフ
指揮=トマーシュ・ネトピル
何度も聴こう聴こうと思いながらなかなか聴けなかったネトピルをようやく聴くことができた。
指揮者としては2007以来来日を重ねているので、もう日本ではお馴染みかもしれない。年齢は今年(2022)47歳というから、ハーディングやネゼ=セガンと同い年ということで、同世代にKペトレンコ、ソヒエフ、ネルソンスがいるのでまさにこれからという指揮者。
以前聴いた「わが祖国」のCDでは、かなり明快かつストレートで、熱量をかなり持ち合わせた指揮者というイメージがあったけど、この日のマーラーはまさにそのイメージ通りだった。
最初の「若人の歌」。
今夏東響で聴いたポベルカを思わせるような、これまたクリアで明快、そして見通しのよい作りだけど、それ以上らに弦や木管の瑞々しい響きと、森を思わせる美しい詩情感がなんとも心地よい。
それでいて陰影もしっかりとられていて、決して濃淡の無い表情の浅い演奏になってないことにも感心。
ただちょっと残念だったのは自分のいた座席の関係か、独唱者の声があまり届いてこなかったこと。また音程がときおり不安定になる時があり、体調が優れなかったのだろうかとちょっと心配してしまう時もあった。
最近は気温の差が激しいのでなかなかこのあたりたいへんなのかも。
この後15分の休憩の後、後半の「巨人」。
こちらも前半でもみられた特長がさらに強く押し出されていたけど、より活力と推進力が増した演奏になっており、ちょっとワルターとNYPOの古い録音を思い出させるようなところすらあった。
また弦の表情や謡いまわし、さらには弦の刻み方にちょっとボヘミア的な感触が感じられる部分があり、「チェコ出身の指揮者にとってマーラーは自分の国の音楽という自負がある」という事を以前教えてもらったそれを思い出す演奏でもありました。
特に第二楽章ではそれが強く感じられました。
味わい深い第三楽章も秀逸でしたが、圧巻だったのは第四楽章。
第一楽章からなかなかいい響きだった金管がこの楽章でさらに打楽器とともに大健闘。最後本当に見事な頂点を築き上げていきました。
(因みに金管は一部増量しており、最後第四楽章でホルンが立って演奏した時、すぐ傍でホルンの補強の為に増量されたトランペットとトロンボーン各一名ずつも立って演奏)
とにかくこの最後の部分でも良くあらわれていましたが、ネトピルのマーラーはここという時の音の盛り上げや輝かしさと熱量、そして集中力と解放感の両立も素晴らしく、決して情念の濃さや煽情的な激情性を感じさせるものではありませんでしたが、健康的かつ爽やかな青春の息吹と向こう見ずなエネルギーの解放を感じさせる、全編聴き応え満点のものとなりました。
この後のネトピルの公演も期待大です。自分は行けませんが。
というわけでとても大満足な演奏会でしたが、最後にちょっと。
じつは自分の席に近い所で、演奏中やたら身体を動かし手で小さくない動きでリズムをとる年配の方がいたけど、近くの人は迷惑ではなかったのだろうかと、かなり心配になってしまった。
そのすぐ傍には小さな女の子を連れた親子連れがいたけど、こちらは終始静かで、「巨人」終了後、女の子が驚くほど熱い拍手を送っててビックリした程。
最近の年配は本当に演奏会でちと情けなくなってしまうような人が目についてしまい、ちょっとわきまえてほしいと思ったと同時に、小さい女の子だからといって、「マーラーなんか連れてきて大丈夫?」と決めつけていた自分もちと反省。
終焉後にもいろいろ考えさせられた公演でした。
〆
井上道義指揮NHK交響楽団を聴く。(11/13) [演奏会いろいろ]

2022年11月13日(日)
NHKホール 14:00開演
伊福部 昭:シンフォニア・タプカーラ
ショスタコーヴィチ:交響曲 第10番 ホ短調 作品93
1954年とその前年に作曲された、日本と旧ソ連の二つの交響曲。
ともにどちらの国にとっても大きな出来事であったが、そんな時代の断面を切り取ったようなプログラム。
まず前半の伊福部さん。
井上さんらしい共感性と熱量の高い演奏で、しかも最後にオケも指揮者もカッコいいホーズをつけたノリノリの演奏ではあったのですが、どこか格調の高さも強く押し出されたようなこの日の演奏。そのせいか何故か途中からモーツァルトの38番「プラハ」が妙にこの曲に被って感じられてしまいました。
正直何の関連性もなく、共通点といえば母国で作曲したものの初演は異国の地だったという部分くらいかも。
とにかくそんな印象を受けた演奏でした。
あとこの曲ですが、1956年に初演された後、少なくともプロオケの定期ではその後一度も演奏されず、1980年の改訂稿が新響によって初演された後、7月にようやく新星日響により演奏されたという事を思うと、1950年から60年代の日本の楽壇はひじょうに無理に背伸びをしなければやっていけない、もっとハッキリいってしまうと料簡が狭いというか、ええかっこしをしたいがために一種の「日本の国民楽派」的なものを軽蔑もしくは排撃する貧しい考え方がその根底にあったのではないかとふと思ってしまった。
もっとも伊福部さんの作品はそういう狭い器量の大きく外側に逸脱した規格外の化け物みたいな曲だったので、もしそういう流れがなかったとしても手に余る代物だったかもしれません。
それにしてもあの大きなNHKホールの三階後方まで余裕で響いてくるその音楽。
もうこれだけでも当時の日本のオケやホールの常識から考えると、異常すぎるくらい異常な曲という事をあらためて痛感させられてしまいました。
本当に凄い作曲家による凄い曲です。
このあと後半のショスタコーヴィチ。
第一楽章冒頭の弦の響きの集中力が凄まじく、まるで弦楽五重奏がそのまま拡大したかのような結晶化したような響きに驚く。
そしてその音はちょっと表現はおかしいけど「透明感の高いどす黒さ」のようなものがあり、何かとんでもないものがはじまったという感じが最初から強く感じられた。これは2007年の日比谷での井上さん指揮のサンクト響の時にはあまり感じられなかったものでした。
自分はかつて井上さんのマーラーを「作曲者の頭の中を覗き込んで、そこからすべての情報を引き出そうとしているかのような演奏」という感想をもったことがある。ただ「それをマーラーはあまりその行為を嬉しく思わなかったかも」とも同時に感じたのですが、今回のショスタコーヴィチの場合、井上さんはマーラーと同じコンセプトで臨んだものの、ショスタコーヴィチの場合マーラーと違い「とことん自分の中からすべてを拾い出してみてくれ」と言わんばかりのつくりのせいか、今回は寸止め抜きでショスタコーヴィチの心象風景が膨大な情報量とともに開帳されたかのような趣の演奏になったように感じられた。
そんな感じではじまったこの日の演奏は、前半二つの楽章はスターリン時代のそれを思わせるような荒れた音楽が主に表出されていたが、第一楽章はむしろ正反対ともいえる随所に聴かれた虚無的ともいえる弱音の方が印象に残る。
そして後半の二つの楽章。ここではN響の木管の筆舌に尽くしがたいシンプルな表情が随所にあらわれ、第三楽章など木管主体のディベルティメントにすら聴こえたほど。だがそういうシンプかつある意味静寂と透明感を全面に出しながらも、その背後にはこれからやはり同様な時代が続くのではないかという作曲者の不安のようなものが隠されているようで、ショスタコーヴィチの底の部分の本音を時としてみせないようにするそれが、極めて強く感じられる演奏だった。
そして第四楽章は今までの三つの楽章が混然一体となり、これまでも地獄だがこれからも地獄、どこにも救いも無く逃げ場の無い状況に追い詰められ、行く先のない絶望の叫びをあげながら最後の狂騒に向かっていくようなその演奏は、すでにショスタコーヴィチには13番の交響曲を書いた時と同じ情景がすでに広がっていたのではないかと思われる程、とにかく救いの無い叫びの音楽に聴こえてきてしまった。
このため音楽が終わった後「これは辛い」と正直感じ、声も拍手もほとんど出せなくなってしまった。
オケは充分すぎるくらい素晴らしく鳴っており、昭和の頃の「顔の無い」状況とは別物になった今のN響の、その表情と方向性のしっかりしたそれはまさに喝采ものだったけど、以上の事からとても喝采を送る気になれなかった。
もちろんこれらは自分の勝手な思い込みとイメージの産物なので、これが正解といった代物ではない。
ただ何か今迄この曲から感じられなかったショスタコーヴィチの救われない精神状態と、彼を取り囲んでいた過酷な状況や苛烈な仕打ちが、この演奏を通してより強く感じられたことは物凄く考えさせられ、そして今のロシアのそれもどこか重なるようにも感じられてしまった。
そしてこのような演奏をやってしまった井上さんの恐ろしい力量にはもはや言葉かがありません。
もしショスタコーヴィチが今日のこの演奏を聴いたらどう思ったことでしょう。
最後に。
指揮者の井上さんは2024年に引退をされるとのことだけど、翌年2025年のショスタコーヴィチの没後50年という年にその指揮が聴けないのは何とも残念。せめてあと一年延ばす事はできないものだろうか。
〆
※
本当はこの後、新海監督の新作を映画館に観に行く予定でしたが、以上の理由からとてもそんな気持ちになれないのでパス。これも本当に予想外の展開でした。
なので終演後の井上さんらしい舞台上でのそれもなんか呆然と眺めていました。
アンドリス・ネルソンス指揮ボストン交響楽団を聴く。(11/9) [演奏会いろいろ]

2022年11月9日(水)
みなとみらいホール 19:00開演
マーラー:交響曲第6番
指揮:アンドリス・ネルソンス
来日前に黒帯修得など話題にも事欠かないネルソンスだが、今回の日本公演最終日の三日後に44歳の誕生日を迎えるという。
そんな彼だけに意気揚々としてこの日を迎えたと思われるが、さすがにこの人の入りには少し驚いたかも。
おそらく6~7割くらいの入りに自分はみえたけど、この組み合わせこの曲目、しかもネルソンスはこの曲をまだ公式録音していなという未知数の魅力ということを考えても。主催者側の座席の割り振りの大失敗は明白だろう。
せめてDはともかくC席をもっと拡大しておけば、ここまで見てくれの悪い入りにはならなかったと思う。
サントリーホールと曲目がバッティングした場合、WPOやBPOのように天井知らずの人気オケならともかく、そうでない場合はやはりもう少し考えなければいけないと思う。自分は神奈川地区で何度かこういう状況を目にしているので、このあたりに対して主催者があまりにも無頓着すぎるのではあるまいかと首をかしげてしまう。
もう少し演奏する側の気持ちにもなってほしいし、そうしないと利益も結果的に芳しくないものになってしまうと思うのですが。
という状況の中で行われたこの公演。ただおかげで満員御礼では感じられない音の豊かさが若干感じられたり、視覚的に自分のいた席から気持ちいいくらい舞台上の隅々も指揮者を含めよく見えたのはありがたかった。なにしろ前一列すっぽり空いてましたので。
第一楽章冒頭。
弦の音を聴いた瞬間。
「ああ、これはニューヨークでもシカゴでもない、ボストンのマーラーだ」
とすぐに感じられた。
じつは自分はボストン響を実演で聴くのはこれが初めて。
なので、当然のこの感想は録音レベルにおける印象からくるものなのだけど、あまりにも自分の想像していた音とほとんど同じだったことで、こういう感想がすぐに出てきてしまった。
ボストンはその響きが、常に内側にエネルギーが放射され、そのことで蓄積された濃密な響きが音楽を構築していくといった趣を持つオケという印象があるけど、この日のマーラーはまさにそのもの。
そのせいか強烈な陰影、感情の振幅、対局から対局への鮮烈な跳躍、情念の奔流といった、直撃的かつ劇的なそれとは距離を置いた、音そのものをじっくり固めたような野太く直球勝負のような愚直ともいえるような響きに彩られたマーラーがここでは展開されていった。
このため第一楽章はネルソンスがいろいろと細かい表情づけをしてはいるものの、ボストンはそれをしっかりと描きながらも、以上で踏まえた特性に則った音楽を愚直なまでに提示してくるためじつに明快というか健康的、しかも悠揚とした音楽感をネルソンスが大事にしていることもあり、田園的とも楽天的ともえるような趣で第一楽章がのびやかかつ手堅く演奏されていった。
この音楽に深刻なドラマやストーリー、さらに情念の噴出や思いの丈を求める人には甚だ好き嫌いが出るつくりになったように感じられたけど、自分には最初に述べたように「ああ、これはニューヨークでもシカゴでもない、ボストンのマーラーだ」というそれが強く、ひじょうに興味深く感じられた。
続く第二楽章は、曲想もあってかネルソンスもかなり攻めの音楽を仕掛け、かつ緩急強弱をすこぶる大きくつけた、ひじょうに表情と対比の大きな音楽を展開していった。
これなど下手すると散漫なとっちらかった演奏にオケによってはなりかねないけど、ボストンはそういう音楽もまた自分たちの特性の中に昇華し、シンプルかつしっかりと演奏しきっていた。これはティンパニを中心とした打楽器群がかなり強力だったことも大きかった。
第三楽章もこれもまたシンプルで、ちょっと映画音楽のようにさえ聴こえるほど、音楽が節度を持ちながらもしっかりと明確に音楽を歌わせていたのが印象的。特に弱音の神経の行き届いた響きが魅力的だった。
ここまででだいたい楽章間の休憩込で一時間。
そして第四楽章。
先行した三つの楽章より複雑で情報量の多いこの楽章。
ボストンは最初の音からいきなり今迄とは違う、というより今まで開けてない引き出しを開けたかのように、ひとつ踏み込みんだかのような、より意志の強い響きを出してきた。
その後音楽は次第に今まで以上に熱を帯び始め、特に二度目のハンマー以降、まるでリヒャルト・シュトラウスの大規模管弦楽のような凄い程の音響の大波のようなものが押し寄せてくるようで、それはちょっと表現のしようがないほど圧巻。
(考えてみればシュトラウスの「アルプス交響曲」との関連性をいろいろと言われている曲なので、このあたりも意識しての演奏だったのかも)
ネルソンスがアクセルを床が抜けるほど踏み込んでるにもかかわらず、ボストン響の前述した特性は微塵も崩れず、それでいてシカゴあたりの目もくらむような絢爛豪華とは違う壮麗かつ圧倒的なそれなのだから、これにはさすがにオケのそれに舌を巻くしかなかった。
(またそれも計算に入れてのネルソンスの指揮も見事)
このあたりはTP、TB、TUBAを横一列に並べ、さらにその一段前にホルンを横一列に並べていたプラスセクションの壮観な響きに負うところも大きかった。
それにしてもこの日のボストンのブラスは、いくら抑制をかけながらも途方もない大音量を出しているのだからとんでもない。これは実際にちょっと聴いてみないと感覚的に分からないかも。
と、とにかく最初は抑制のきいた、そして最後は大音響というマーラーでしたが、総合的にいうと深刻さのない健康的なマーラーであり、明日に向かって元気が出そうな、それこそかつて聴いたティルソン=トーマスのブルックナーとちょっと似たものを感じさせられたものでした。
おそらくこの日のマーラーはかなり好き嫌いが分かれる、もしくはもっと抉ってほしいという意見が出てきそうな感じがしましたが、自分はこういうマーラーも有りという気がしました。
第四楽章最後の音が消えた後、指揮者が棒を完全に下すまで拍手が出なかったのが当たり前とはいえやはり嬉しい。
この時自分の時計をみたら午後八時半をまわっていた。なんと演奏時間が90分近くかかっていました。
そんなにかかっていたのかとちょっとビックリ。
確かにかなり緩急を取っていた部分もあったし、早めの演奏ではないと感じてはいたもののそこまでかかったという感覚は自分にはありませんでしたが、他の方はどう感じられたのでしょう。
その後オケのメンバーがほとんど退場してもスタンディングオベーションが続き、指揮者が舞台に再度登場しお開きとなりましたが、じつは開演前、ブロックごとの規制退場が行われるような事が放送されていたものの、指揮者がオケの奏者を労ったりスタンディングオベーションがけっこう長かったこともあって、その間にかなりの人が五月雨式に退場したり終演後のサイン会に並びにいったりと、ただでさえ満員には程遠い入りの中で自然発生的規制退場が起きたような形になったため、結果正式な規制退場は行われませんでした。
これはこれでありがたかったです。
しかしあれだけの大曲を終演後、少なからぬファンの人たちのためにサイン会を開くネルソンス。
余計なお世話かもしれないけど、そろそろ正直無理せず痩せるように心がけてほしいものです。
バーミンガム時代のアルバムの表紙になっていた頃の彼はいったいどこに…。
以上で〆。
※
しかし今になって、なんか6番というより5番や7番を聴いたような気持ちになっているのがなんか不思議。
※
そういえば今年はボストン響初来日時(1960)にもコンマスをつとめていた歴史的大コンマス、リチャード・バージン(1892~1981)の生誕130年に当たりますが、彼はマーラーの普及に努力し、みずからボストンの指揮台で彼の交響曲を指揮していました。
ボストンというとミュンシュ以前はマーラーとあまり縁が無いように思われるかもしれませんが、バージンなどにより意外と早い時期からマーラーに取り組んできたオケでもあり、ラインスドルフ以降さらにマーラー演奏でも知られるようになっていきます。
ネルソンスもその流れを引き継いだかのように積極的にマーラーを演奏していますが、この6番は2015年に9回、そして今年10月末に7年ぶりに3回指揮した後、今回の来日公演に臨んでいます。
なので今回のそれは両者ともにお互いの手の内を知り尽くし充分手慣れた状況で演奏したといことになります。
そういう意味で、ネルソンスとボストン響の余所行きではない、あるがままの今の姿に近い公演を今回聴けたのかもしれません。
※
三回目のハンマーの時、物凄く嬉しそうな仕草をした方を前方でみかけた。
滅多にない事なので余程嬉しかったのだろうか。
なんかこちらもみてて嬉しくなってしまった。
※
今回ネルソンスとボストンがマーラーで使用したハンマー。
あの箱、おそらく舞台と密着させ、舞台全体を反響させホールに響かせることを目的にしたような作りにみえたけど、もしそうだとすると、ホールによってそれがあまり機能しない事もあったかも。
横浜は自分のいた所はちょうどいい感じだったけど、それを思うと場所によってはホールとの相性で凶と出たところも。
※
そういえば今回、「悲劇的」というタイトルが使われていなかった。
演奏会から一週間以上経って今頃気がつきました。
クラウス・マケラ指揮パリ管弦楽団を聴く。(10/15) [演奏会いろいろ]

2022年10月15日(土)
東京芸術劇場 16:00開演
ドビュッシー:交響詩《海》
ラヴェル:ボレロ
ストラヴィンスキー:春の祭典
指揮:クラウス・マケラ
ある意味、今世界で最も注目されている指揮者かもしれないマケラが、初めて自らのオケとともに来日公演を行ったその初日に行ってきました。因みにテレビ等の収録があったようにみえた。
この日は開演前にプレトークが若い人向きにおこなれたりしていた。若い層の開拓という意味ではとてもいいことだと思う。自分の若いときにこういうのが無かったのが本当に残念。
しかし海外から16型のオケが来日するなんて本当に昨年までは夢のような話。このままコロナが終息に向かってほしいと願わずにはいられなかった。ホールはすでに飲食が解禁されていたのが嬉しかった。
会場は満員とまではいかなかったがかなりの盛況。ただマケラをもってしても満員にならないというのはいったいどうしたことか。彼のここ数年の状況をみると、ちとこれは信じ難いものがあった。こちらが想像する以上に日本での知名度が低いのだろうか。
前半最初は「海」。
これはなかなかの問題作だった。
冒頭から弦管ともにとんでもなくクリアで、しかも弦がやや乾き気味に響いていたせいか(ホールのせいかもしれないけど)、イメージとしてあるドビュッシーの「しっとり感」がまるでなく、とにかく音そのものがクリアに響いて来るといった感じになっていた。
このため聴きようによって音のみで勝負したような、それこそハイドン風ドビュッシー、もしくは新古典派ドビュッシーとすら形容したくなるようなものだった。
だが表情付けがその割に細かく、ちょっと後期ロマン派を引きずったかのような趣もときおり感じられるなんとも独得な演奏だった。
オケの方もこのひじょうに独特な要素をもったためなのか、頭では分かっていてもひじょうに慎重にならざるを得ない部分があったように見受けられ、推進力ある部分でもどこか慎重な足運びを音楽に感じた。
そのせいかどこか聴いていて弱音の美しさや強音の豊かさの素晴らしさはあったものの、どこかオケがいまいち音楽に踏み込んでいないような手探り感があった。ただこれはおそらく回を重ねるごとに解消するようにも感じられた。
この時、ひょっとして日本での全公演で「海」をやるのは、マケラがパリ管に自分の音楽の昇華能力を見定めるために企てたためなのかもと、ちょっと深読みしたくなってしまったほどでした。
岡山や大阪公演あたりまでにこの「海」がどう煮込まれていくのかちょっと楽しみなのですが、自分はそれを聴くことができないのがなんとも残念。
続いての「ボレロ」。
こちらは逆にオケにとって会心の演奏。というかここまでオケ自らが本領を発揮したパリ管の演奏というのを自分はあまり聴いたことがない。
かつてのプレートルとの同曲のそれはオケの魅力を「引きずり出された」的な演奏だったのですが、この日はマケラによって「引き出された」的な演奏で、オケ全体も靡くような動きがはっきりとみてれ、パリ管が本気でのっているという感が強かった。
特に、初めて管弦がいったいとなってテーマを演奏した瞬間、鳥肌が立つくらいの筆舌に尽くしがたいほどの絶妙な響きが醸し出され、思わずこの曲で涙腺が緩みそうになったほどでした。
オケも最後途方もなく強大な響きを築き上げ、これはこの日の白眉というくらい盛大な拍手を受けていました。
久しぶりに聴いた「聴かずに死ねるか」級の演奏でした。
しかし二十代半ばパリ管からここまでその音楽を引き出すだけでもとんでもない指揮者です。
この後休憩。
ホールの係りの人が「会話をお控えください」というボードをもって歩いていたが、みなマスクしていてもそれをやるということは、それってこのホールの換気の悪さを証明してることなのでは? と意地悪く思ったりしたものでした。
そして後半。
この「春の祭典」もまた前半の「海」と似たような感じの演奏となっていた。
ただ「海」よりもオケがもっとマケラの音楽をしっかり掌握していたせいか、あれよりはかなり音楽が前向きに進んでいた。ただこちらも回数を重ねればさらに聴き応えのある演奏になるだろうなという印象は「海」と同じで、大阪公演あたりではそれはそれはより素晴らしいものになっているのではと予想。
(もっとも器用なインサイドワークを身に着けてる人は、「回数を重ねれば」みたいな事はあまり感じさせないケースがあることを思うと、マケらそういうことに無関心な指揮者なのかもしれないし、価値をあまり見出していないのかも)
演奏全体としてはかつてのバレンボイムの猪突猛進でも、ビシュコフの重戦車系とも違う、音の輪郭が視覚的にみえてきそうなくらい、クリアで音の動きが細部まで聴きとれるような、この曲に施したストラヴィンスキーの仕掛けをひとつひとつ開帳していくかのような、ちょっと新鮮な演奏でしたし、彼独特の解釈が随所に見受けられたなかなか個性的ともいえる部分が感じられた演奏でした。
あとこの曲で特に痛感したのはマケラのとても冷静というか「さめた」音楽への対峙の仕方。
ただ冷静といっても他所事他人事のようなものではなく、熱狂や興奮もすべて冷静にコントロールされた中で行われているような、そういう頭のキレというか幅の広さと深さを凄く感じさせられた。
それはかつてのLAPO時代のメータとも相通じるものがあるけど、メータがどちらかというとブレンド感に拘ったのに対し。マケラはクリアさ見通しの良さに拘った感があった。
(このあたりは今夏に聴いたポベルカ、さらにバッディストーニとも相通じるものがある。ひょっとしてこの世代はそういう傾向の人が多くいる世代なのだろうか)
そんなこの「春の祭典」も終わってみればこれまた観客からの盛大な拍手を呼び起こした。
最後に雑感。
一部の古い音楽ファンは未だ「バリ管の全盛期はミュンシュ時代」と言ってはばからない人がいるようだけど、自分は近いうちにこれ等の人達も「今が全盛期」と思うようになるのではないかと、この日のマケラを聴いていて強く感じられた。特に「ボレロ」などは二十代半ばの指揮者かパリ管相手にやってしまったことがすでに仰天物で、いったい今後このコンビ、そしてマケラはどこまで成長し進化していくのだろうかと思ってしまったほどでした。
できればマケラの半世紀後を聴いてみたいがさすがに自分にそれはできない。
若い人たちはムラヴィンスキーやチェリビダッケの実演を聴けたから羨ましいと年長者に羨望の念を感じるかもしれないが、自分にしてみればマケラやポベルカ、それにフルシャやバッティストーニと同じ時代を歩んで生ける今の若い人達の方に強い羨望の念を感じてしまうものがあります。
というわけで〆。
因みにアンコールはパリ管で聴くのは初めての名曲、ムソルグスキーの「モスクワ河の夜明け」でした。これもまた新鮮な演奏。ただしその選曲はかなり意味深。