ヴァント&ミュンヘンフィルのブルックナー [クラシック百銘盤]
ここでお話するのは2001年9月13-15にかけて
ギュンター・ヴァントが亡くなる数ヶ月前に
ミュンヘンで指揮したもののライブCDです。

(PH06046)
ヴァントというと自分は一度だけ1990年の来日時にブルックナーの8番を聴いたが
おそろしく厳しい、それこそ鋼のような意志をもったブルックナーだった。
ただこのときのヴァントのイメージは
それ以前に聴いたLPやそれ以降に発売されたCDをいろいろ聴き続けたものと
ほとんど寸分の狂いのないものでそういう意味でほんとうに自分に対して極めて厳しく
そして妥協無く一貫性をもった姿勢を貫いている指揮者と感じたものだった。
だがこのヴァントのスタイルに自分は深く敬意を表するものの、
そこから創りだされた音楽には自分の価値観とどうしても相反する部分があるためか、
正直最後の部分でどうしてもどこか馴染めないし、全幅の信頼を置ききれない部分があった。
そのせいか2000年に来日したときも、そんな自分が物見遊山混じりの気持ちでいくよりも
まだ一度もヴァントを聴いたことが無い人に
その実演を聴けるチャンスを少しでもあげた方がいいと思いこの演奏会には行きませんでした。
その後このときの演奏会はTV放送やCD化されたものの、
やはりそこからのイメージは
今までのヴァントのそれから大きく離れたものではありませんでした。
もっともその演奏は予想を遥かに上回る素晴らしいものではあったのですが…。
今回のこの演奏はその日本公演から10ヵ月後に、
ミュンヘンフィルの指揮台に最後にあがったときのものなのですが、
演奏された日にちをみてもおわかりのとおり
この一連の演奏会のわすが二日前にはあの911があったわけでして
この演奏会に来た聴衆の多くも深い悲しみと複雑な感情
そしてかなりの不安というものを抱えて来場していたと想われます。
こういう911直後のただならぬ状況で行われた演奏会のCDとしては
9月17日にウィーンで行われた故林達次さん指揮のマタイ受難曲。
同19-21日にロッテルダムで行われた
ゲルギエフ指揮によるショスタコーヴィチの交響曲第7番。
この二点を自分を聴いてはいますが
それらは非常時においても尚かつそのベストを示したものとなっています。
そして今回のヴァントはさらに事件からの日にちが近い演奏会であったにもかかわらず
やはりヴァントらしく厳しく音楽と向き合い
それ以外のものは目もくれない求道的な演奏となっています。
ただ今回のヴァントは今まで聴いたどのヴァントとも違ったものになっていました。
オーケストラがミュンヘンということもあるのでしょうが
音楽の腰がやや高くしかもじつに柔軟な表情と音質に音楽が変化しており
まるでベームがウィーンフィルを指揮したときに起きた音楽的変化と
かなり似たものがありました。
ですがそれ以上に強く感じたことは
ヴァントの意志の力の強固さはそのままなのに
音楽が極めて音質が柔軟なものになっており
肩にまるで力の入っていない、
老匠が作曲家との静かな対話の上に展開された
かぎりなく清澄な心象風景がどこまでも広がっているいくような
そんな感じが強くしました。
しかもそれでいて終楽章の終盤の盛り上がりは尋常ではなく
その感情の万感迫るような果てしない高揚感とあいまって
類稀なほどの強い感銘を聴いていて与えられたものでした。
そしてこのとき自分はかつて1970年にセルとクリーヴランドが来日したとき
その伝説的な「英雄」を聴いた吉田秀和氏の言葉をふと思い出しました。
それは
----------(以上引用開始)
あそこには「完璧への熱狂と責任感」で一生ほ燃焼しつくした人が、
最高を盡しながら、なお、「その上を」望んで、
天に向かって祈ってるみたいな姿勢があった。
----------(以上引用終わり)
というものでした。
このブルックナーにはまさにその言葉がそのままあてはまるような
そんな感じがしました。
そしてこの演奏終演後の聴衆のもの凄いまでの反応!
それは異常な状況下で行われたにもかかわらず
最後はは音楽をして聴き手をその呪縛や不安から解き放ち
音楽が人間にとっていかなるものであるかという
そういう根源的なところにまで訴えかけてきたこの演奏に
聴衆すべてが言葉にならないほどの深い感銘と感謝を
この大波のような拍手と歓声にのせてあらわしていたようにさえ感じました。
この演奏は音楽というものと人間がどうかかわり
そしてどのようなものであるかという
ひとつの極致をみたような気さえするほどのものがあります。
それだけにこの数ヵ月後
自宅で転倒し肩を脱臼した後急速に体調を崩し
そして90歳で亡くなられたのは
当時はしかたないと受け取ってはいたものの
このような演奏を聴かされてしまった今となっては
じつに残念な気がしたものでした。
自分のスタイルを頑なまでに通し究極化した指揮者が
その上に立ってさらに新しい世界を臨み、祈り、
そして新たに追い求めようとしはじめたのではないかとさえ感じられた
このミュンヘンのブルックナー。
ミュンヘンのブルックナーの名盤がまたひとつ自分に増えてしまいました。
尚余談ですが、
終楽章のコーダでこの演奏の六年前にこの世を去った
ミュンヘン・フィルハーモニーの主であり
ヴァントと同い年の指揮者でもあったチェリビダッケの姿が
その背後に感じられるような瞬間がときどきありました。
これはヴァントの求道的な音楽への真摯な姿勢が
このオーケストラに十五年以上君臨し
巨大な影響を深くオケに浸透させたチェリビダッケのその音楽を
共鳴させた瞬類稀な瞬間であったのかもしれません。
http://blog.so-net.ne.jp/ORCH/2006-12-30
(↑当blog内にある「ミュンヘンフィルのブルックナー三題」。
ここには他のミュンヘンフィルのブルックナーのCDのいくつかについて触れています。)



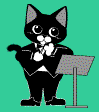

コメント 0