ニキシュのブルックナーの7番って… [クラシック百物語]
どんなんだったんだろう。
これはブルックナー好きの方なら誰もが一度は思ったことだろう。
今(2014)からちょうど130年前の12月。
ブルックナーの交響曲第7番を大成功に導き、
フルックナーを押しも押されもせぬ名作曲家の地位に据えたのは、
このときのニキシュのそれがあればこそと言われている。
だがなにせニキシュにはブルックナーの録音は皆無。
ワーグナーもRシュトラウスも無い。
あるのはアコースティック録音における、
モーツァルト、ベートーヴェン、ウェーバー、リスト、ベルリオーズからの、
7曲8種の録音のみだ。
また不思議なことにニキシュとブルックナーについても、
この大成功に導いたエピソードは数あれど、
その後のニキシュとブルックナーのそれとなると、
突然その情報が無くなってしまう。
ふつうならばその後の初演もニキシュに頼みそうなものだが、
翌年初演された「テ・デウム」はハンス・リヒター。
7番に次ぐ大作8番は当初はワインガルトナーに依頼、
それがダメとなるとハンスけ・リヒターに初演を以来している。
また3番の最終稿も1890年に同じくリヒター。
5番の改訂版は1894年にシャルクが行っている。
突如としてこの大成功の立役者は、
忽然とブルックナーのそれから姿を消してしまったのだ。
話を戻すが、ニキシュはこの初演より何年か前に、
ヴァイオリン奏者として彼の第2交響曲を演奏している。
これは彼の師がこの曲の試演を行ったデッソフであり、
この曲の試演、初演、そして二回目の演奏時に、
ニキシュがデッソフの門下生であり、
また卒業後ウィーン宮廷歌劇場オケの奏者だったことで、
これらの曲を演奏する機会があったのだろう。
ニキシュはその後ライブツィヒに行き、指揮者としての名声を築く。
そんな時期にブルックナーの7番初演の話が舞い込んできた。
ただしこれも最初からニキシュというわけではなく、
当初は当時ゲヴァントハウス管弦楽団の長だった、
名匠カール・ライネッケ(1824-1910)に依頼したのだが、
このモーツァルトやメンデルスゾーン、シューマンを愛好していた人物から、
演奏に難を示され辞退されてしまった。
そのため当時同じライブツィヒの歌劇場の首席指揮者だったニキシュに、
御鉢がまわってきたというのが本当のところだという。
もしこのときニキシュが2番に好意を抱いていなかったら、
やはりライネッケ同様この話を呑まなかったろうし、
ピアノでの試演やスコアを観て感嘆し、
その後ブルックナーと入念な打ち合わせをしたり
自ら有力な評論家に口利きをしたりという、
ここまでの積極的姿勢になることはなかっただろう。
ニキシュは初演の時でも練習当日に総譜をはじめて開くということがしょっちゅうで、
それを思うとここでのニキシュの態度は極めて異例といっていいのかもしれない。
そしてライブツィヒでの初演は当然のごとく大成功に終わった。
史上稀に見る若き天才指揮者と呼ばれたニキシュが全力を注いのだから、
当然といえば当然かもしれない。
しかし、その後ニキシュとブルックナーのそれは表舞台からみえなくなってしまう。
初演後、
第二楽章にシンバルを加える事を提案したシャルクのそれをニキシュが支持したことが、
後々ブルックナーが苦々しく思った為なのか、
それともニキシュがブルックナーと性格的に合わなくなったかはわからないが、
ニキシュが比較的楽天的で細かい事にこだわらなかったといわれているのに対し、
ブルックナーはある意味頑固で神経質に何度も同じ曲を書き改めていたことを思うと、
この二人はしょせん水と油だったのかもしれない。
だがそれ以上にニキシュのこの時の演奏スタイルが、
はたしてブルックナー自身のそれと本質的にあっていたかということだ。
確かに手紙等による事前に細かいな打ち合わせがあったとはいえ、
ウィーンからでかけてライブツィヒではじめて耳にしたそれが、
自分のそれとかなり違っていた可能性もあるし、
それはもはや手直しできなぬ段階に達していたかもしれない。
またニキシュは練習と本番がかなり違うことがしょっちゅうという、
けっこう気ままなところがあったこともあり、
打ち合わせと違う演奏がひょっとすると本番で展開された可能性もある。
それもブルックナー自身の許容範囲を超えていたとすると、
さらにブルックナーにとって信頼のおけない人間とうつってしまいかねない危険性もある。
ニキシュのスタイルはいくつかの文献や証言からみると以下のような特長があったという。
◎極めてロマンティック。
◎即興的に表情が千変万化する。
◎音楽が旋律単位でよく歌う。
◎女性的ともいえるほどの感覚的な柔和さがある。
◎劇的な効果に事欠かない。
◎オーケストラから魔法のように美しい音を引き出す。
というだいたいこんなところがあった。
特に得意としていたチャイコフスキーの悲愴交響曲は、
それを聴いていたガウクはその素晴らしさは認めるものの、
「彼のあまりにもやわらかい女性的とでもいえるような性質は今日のわれわれの感覚にはむかない。例えば「悲愴交響曲」の時にも聴衆を泣かすのみでなく自分も指揮台で泣いたくらいであった。しかし、われわれは今日、この同じチャイコフスキーの曲をもっと堅い古典的な解釈で演奏するようになった。」
という発言をみるとなんとなく想像がつくような気がする。
あえていうと音の感触はウィーン時代のワルター。
表情の動かし方は40年代以前のフルトヴェングラー。
みたいな感じてはなかったかという気がする。
あとボールトがニキシュのレパートリーの中で、
ブラームスの第一交響曲とともに特に評価していたのがワーグナーだった。
そのボールトが指揮したワーグナーは、
高音域の輝かしい響きを軸にしたもので、
これが私淑していたニキシュのそれと音のバランス的に近いという考えも、
それほど無理がある推理とは思えないと思う。
他にもフルトヴェングラーが、
その音のブレンドの仕方を称えていたり、
フルトヴェングラーとボールトがレガートのことを引合いに出していることなども、
この指揮者の特性のひとつだった可能性がある。
確かに音の美しさは遺された録音ではわかりずらいものがあるが、
劇的な迫力というものは、
ロンドン響と録音したリストの「ハンガリー狂詩曲」第1番における終盤の追い込みなど、
1913年の太古の音質からでも充分伝わってくるものがある。
また同年の「エグモント」における表情の豊かさと間の図り方なども、
上であげた特長のあらわれのひとつといえると思う。
だがこれらを総合して出てくるブルックナー像は、
特に宇野功芳氏が我が国に広めてしまったそれとはあまりにも違いすぎる、
それこそチャイコフスキーやRシュトラウスのような美しさと艶をもった、
しかも徹頭徹尾歌いそして泣かせ、最後には情熱的に燃え上がるような、
そんなブルックナーだったのではないかという気がする。
確かに7番ではそれもありかなという気がするし、
遺されたいくつかの録音から、
ニキシュはそれほど遅くテンポをするタイプではなかったと思われるので、
ある意味ものすごくわかりやすく…、
というより感覚的に情と歌心に訴えかけられ、
しかもかなり劇的要素を含んだものだったのではないかという気がします。
第二楽章のシンバルの使用を強く勧めたのもそういうあらわれかと。
これを思うと、はたしてこれを聴いたブルックナーはどう思ったことだろう。
しかも聴衆はそれに熱狂し、演奏は完全な大成功となっている。
4番である程度の評価は得ていたものの、
これほどの成功となると例えどんな演奏でもニキシュに悪く言えるはずがない。
長年夢にまで見た「交響曲作曲家」としての成功を、
60歳をすぎてから勝ち得たのだから、それを否定するこなどできなかったことだろう。
もっともこれらはただの推測であって、
じつはブルックナー自身も大満足するできとなり、
その後も依頼したもののニキシュは多忙ということもあり受けられなかった。
しかもその活動場所がウィーンからそれほど近くない、
ライプツィヒやブダペスト、さらにはボストンやベルリンということから、
その関係も疎遠になってしまったという、
ごくごく単純な理由が真実なのかもしれない。
ただとにかくこの一夜以降、ニキシュとブルックナーの関係は表舞台から消えてしまう。
その後この二人に本当のところ何があったのか、それともなかったのか、
そしてあの夜のブルックナーを作曲者として内心どう後々思うようになったのか、
それは自分にはわかりませんが、
初演以前の関係とはどちらにせよ、
若干は違ったものになったのではないかという気がします。
はたしてあの夜、
ライブツィヒに響いたブルックナーはどんな演奏だったのでしょう。




※ニキシュの指揮姿。
これはブルックナー好きの方なら誰もが一度は思ったことだろう。
今(2014)からちょうど130年前の12月。
ブルックナーの交響曲第7番を大成功に導き、
フルックナーを押しも押されもせぬ名作曲家の地位に据えたのは、
このときのニキシュのそれがあればこそと言われている。
だがなにせニキシュにはブルックナーの録音は皆無。
ワーグナーもRシュトラウスも無い。
あるのはアコースティック録音における、
モーツァルト、ベートーヴェン、ウェーバー、リスト、ベルリオーズからの、
7曲8種の録音のみだ。
また不思議なことにニキシュとブルックナーについても、
この大成功に導いたエピソードは数あれど、
その後のニキシュとブルックナーのそれとなると、
突然その情報が無くなってしまう。
ふつうならばその後の初演もニキシュに頼みそうなものだが、
翌年初演された「テ・デウム」はハンス・リヒター。
7番に次ぐ大作8番は当初はワインガルトナーに依頼、
それがダメとなるとハンスけ・リヒターに初演を以来している。
また3番の最終稿も1890年に同じくリヒター。
5番の改訂版は1894年にシャルクが行っている。
突如としてこの大成功の立役者は、
忽然とブルックナーのそれから姿を消してしまったのだ。
話を戻すが、ニキシュはこの初演より何年か前に、
ヴァイオリン奏者として彼の第2交響曲を演奏している。
これは彼の師がこの曲の試演を行ったデッソフであり、
この曲の試演、初演、そして二回目の演奏時に、
ニキシュがデッソフの門下生であり、
また卒業後ウィーン宮廷歌劇場オケの奏者だったことで、
これらの曲を演奏する機会があったのだろう。
ニキシュはその後ライブツィヒに行き、指揮者としての名声を築く。
そんな時期にブルックナーの7番初演の話が舞い込んできた。
ただしこれも最初からニキシュというわけではなく、
当初は当時ゲヴァントハウス管弦楽団の長だった、
名匠カール・ライネッケ(1824-1910)に依頼したのだが、
このモーツァルトやメンデルスゾーン、シューマンを愛好していた人物から、
演奏に難を示され辞退されてしまった。
そのため当時同じライブツィヒの歌劇場の首席指揮者だったニキシュに、
御鉢がまわってきたというのが本当のところだという。
もしこのときニキシュが2番に好意を抱いていなかったら、
やはりライネッケ同様この話を呑まなかったろうし、
ピアノでの試演やスコアを観て感嘆し、
その後ブルックナーと入念な打ち合わせをしたり
自ら有力な評論家に口利きをしたりという、
ここまでの積極的姿勢になることはなかっただろう。
ニキシュは初演の時でも練習当日に総譜をはじめて開くということがしょっちゅうで、
それを思うとここでのニキシュの態度は極めて異例といっていいのかもしれない。
そしてライブツィヒでの初演は当然のごとく大成功に終わった。
史上稀に見る若き天才指揮者と呼ばれたニキシュが全力を注いのだから、
当然といえば当然かもしれない。
しかし、その後ニキシュとブルックナーのそれは表舞台からみえなくなってしまう。
初演後、
第二楽章にシンバルを加える事を提案したシャルクのそれをニキシュが支持したことが、
後々ブルックナーが苦々しく思った為なのか、
それともニキシュがブルックナーと性格的に合わなくなったかはわからないが、
ニキシュが比較的楽天的で細かい事にこだわらなかったといわれているのに対し、
ブルックナーはある意味頑固で神経質に何度も同じ曲を書き改めていたことを思うと、
この二人はしょせん水と油だったのかもしれない。
だがそれ以上にニキシュのこの時の演奏スタイルが、
はたしてブルックナー自身のそれと本質的にあっていたかということだ。
確かに手紙等による事前に細かいな打ち合わせがあったとはいえ、
ウィーンからでかけてライブツィヒではじめて耳にしたそれが、
自分のそれとかなり違っていた可能性もあるし、
それはもはや手直しできなぬ段階に達していたかもしれない。
またニキシュは練習と本番がかなり違うことがしょっちゅうという、
けっこう気ままなところがあったこともあり、
打ち合わせと違う演奏がひょっとすると本番で展開された可能性もある。
それもブルックナー自身の許容範囲を超えていたとすると、
さらにブルックナーにとって信頼のおけない人間とうつってしまいかねない危険性もある。
ニキシュのスタイルはいくつかの文献や証言からみると以下のような特長があったという。
◎極めてロマンティック。
◎即興的に表情が千変万化する。
◎音楽が旋律単位でよく歌う。
◎女性的ともいえるほどの感覚的な柔和さがある。
◎劇的な効果に事欠かない。
◎オーケストラから魔法のように美しい音を引き出す。
というだいたいこんなところがあった。
特に得意としていたチャイコフスキーの悲愴交響曲は、
それを聴いていたガウクはその素晴らしさは認めるものの、
「彼のあまりにもやわらかい女性的とでもいえるような性質は今日のわれわれの感覚にはむかない。例えば「悲愴交響曲」の時にも聴衆を泣かすのみでなく自分も指揮台で泣いたくらいであった。しかし、われわれは今日、この同じチャイコフスキーの曲をもっと堅い古典的な解釈で演奏するようになった。」
という発言をみるとなんとなく想像がつくような気がする。
あえていうと音の感触はウィーン時代のワルター。
表情の動かし方は40年代以前のフルトヴェングラー。
みたいな感じてはなかったかという気がする。
あとボールトがニキシュのレパートリーの中で、
ブラームスの第一交響曲とともに特に評価していたのがワーグナーだった。
そのボールトが指揮したワーグナーは、
高音域の輝かしい響きを軸にしたもので、
これが私淑していたニキシュのそれと音のバランス的に近いという考えも、
それほど無理がある推理とは思えないと思う。
他にもフルトヴェングラーが、
その音のブレンドの仕方を称えていたり、
フルトヴェングラーとボールトがレガートのことを引合いに出していることなども、
この指揮者の特性のひとつだった可能性がある。
確かに音の美しさは遺された録音ではわかりずらいものがあるが、
劇的な迫力というものは、
ロンドン響と録音したリストの「ハンガリー狂詩曲」第1番における終盤の追い込みなど、
1913年の太古の音質からでも充分伝わってくるものがある。
また同年の「エグモント」における表情の豊かさと間の図り方なども、
上であげた特長のあらわれのひとつといえると思う。
だがこれらを総合して出てくるブルックナー像は、
特に宇野功芳氏が我が国に広めてしまったそれとはあまりにも違いすぎる、
それこそチャイコフスキーやRシュトラウスのような美しさと艶をもった、
しかも徹頭徹尾歌いそして泣かせ、最後には情熱的に燃え上がるような、
そんなブルックナーだったのではないかという気がする。
確かに7番ではそれもありかなという気がするし、
遺されたいくつかの録音から、
ニキシュはそれほど遅くテンポをするタイプではなかったと思われるので、
ある意味ものすごくわかりやすく…、
というより感覚的に情と歌心に訴えかけられ、
しかもかなり劇的要素を含んだものだったのではないかという気がします。
第二楽章のシンバルの使用を強く勧めたのもそういうあらわれかと。
これを思うと、はたしてこれを聴いたブルックナーはどう思ったことだろう。
しかも聴衆はそれに熱狂し、演奏は完全な大成功となっている。
4番である程度の評価は得ていたものの、
これほどの成功となると例えどんな演奏でもニキシュに悪く言えるはずがない。
長年夢にまで見た「交響曲作曲家」としての成功を、
60歳をすぎてから勝ち得たのだから、それを否定するこなどできなかったことだろう。
もっともこれらはただの推測であって、
じつはブルックナー自身も大満足するできとなり、
その後も依頼したもののニキシュは多忙ということもあり受けられなかった。
しかもその活動場所がウィーンからそれほど近くない、
ライプツィヒやブダペスト、さらにはボストンやベルリンということから、
その関係も疎遠になってしまったという、
ごくごく単純な理由が真実なのかもしれない。
ただとにかくこの一夜以降、ニキシュとブルックナーの関係は表舞台から消えてしまう。
その後この二人に本当のところ何があったのか、それともなかったのか、
そしてあの夜のブルックナーを作曲者として内心どう後々思うようになったのか、
それは自分にはわかりませんが、
初演以前の関係とはどちらにせよ、
若干は違ったものになったのではないかという気がします。
はたしてあの夜、
ライブツィヒに響いたブルックナーはどんな演奏だったのでしょう。




※ニキシュの指揮姿。



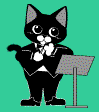

コメント 0