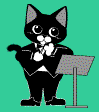エリアフ・インバル指揮東京都交響楽団を聴く(2/22) [演奏会いろいろ]

2024年2月22日(木)
東京芸術劇場コンサートホール 14:00開演
曲目:
マーラー:交響曲第10番 嬰へ長調(デリック・クック補筆版第3稿1版)
マーラーの10番というと、もう半世紀近く前に国内でもフォノグラムから発売になった、ウイン・モリス指揮ニュー・フィルハーモニアによる二枚組LPが自分にとっての全ての始まりであり、未だに強い刷り込みと大きな影響を与えている。
このため過去どのような演奏を聴いても、モリス盤の呪縛から抜けられない状態の為、モリス盤越しにその演奏を聴いてしまうことが延々と続き、ほとんどの演奏に納得したことがない状態が続いている。
その中にはかつてインバルがフランクフルト放送と録音したものも当然入っており、その印象もそれほど大きなものではなかった。
だがあの演奏は1992年録音ということで今から32年も前のもの。当時インバルは56歳、現在は88歳ということでどれくらい印象が変わるか、もしくは変わらないのかということを含めこの日の演奏会を聴いた。
(2014年7月の都響とのそれは、当時この曲を聴く精神状態ではなかったのでパスしています)
冒頭、弦が驚くほど堅い。というより室内楽的ともいえる研ぎ澄まされた感覚の響きといっていいのかもしれない。
よく「ふわっ」とはじまるそれとは明らかに違った。
また全体的にはインテンポだが、随所でテンポを落としじっくり聴かせるところがあるため、一本調子ということにはならない。それどころか第一楽章は過去のマーラー作品のエコーのようなものが聴こえてくるような、過去聴いたどのような演奏よりも表情豊かかつ情報量の多い音楽だった。
それはときには巨人や角笛交響曲の時期、ときにはウィーン時代に書かれた時期の作品のようなものが、まるで走馬灯のように次々とあらわれては消えて行くような、マーラー自身の回想録を聴いているかのような感さえあった。
また例の印象的なトランペットの叫びが聴こえる不協和音の全合奏が、まるで作曲時のマーラーのどす黒い情念のようなもののように響くため、この日のインバルの演奏は前述した事とあわせると、今までのどの演奏よりも過去と現在が激しく鮮烈に、ただし過剰な刺激には走ることなく描かれていたように感じられた。これは演奏の線が太いことも影響しているのかも。
その後の楽章もこの第一楽章で感じたそれが強く感じられた。
第二楽章のスケルツォが19世紀におけるマーラーの心象府警、第四楽章のスケルツォが20世紀におけるマーラーの心象風景のように感じられたのも、第一楽章のそれが影響していたからなのかもしれない。
演奏は第三楽章以降すべて続けて演奏された。
第四楽章における例の葬送の太鼓はひじょうに早めのテンポだったが、これまでのインバルのやり方を思うと早すぎると感じることはなかった。
それはインバルの指揮が真正面から膨大なあのすべての音楽をとらえきっていたことで、マーラーの思いの丈の多くの断片が細かく複雑に散りばめられながらも、あたかもあの巨大な宮沢賢治の「春と修羅」の序の冒頭のような趣さを呈していたように感じられたからなのかもしれない。あまりいい例えではないしはなはだ分かり辛い物言いで申し訳ありませんが。
そして終楽章。
どちらかというと辛口で厳しい雰囲気ではじまった。それは前の楽章かに続く太鼓の決然とした響きにも顕著にあらわれていた。前半に出て来るフルートのソロとそれを受け継ぐかのようにどこまでも美しく高揚していく弦の響きは、それだけにとどまらないものも強く感じられた。
だが最大の聴きものは第一楽章でも出てきたトランペットの叫びを伴う不協和音が静まり、それこそ音楽が止まるのではというほど遅く鎮静化していったその直後。
中低音の弦を軸にした強い響きからはじまるマーラー渾身の歌。
ここから先はある意味マーラーの思いの丈、そこには妻アルマに対する狂熱的な愛情表現と同時に、マーラー自身の自分への嘆息や慟哭のようなものが交錯し、それこそ「自分の人生はこんなものか」と吐き出すような音楽を美しい響きと歌に悲痛なほどのものを乗せて歌い上げた音楽にいつも感じさせられてしまうのですが、インバルはそんな自己を否定するようなマーラーに対し、「それでも自分はあなたのすべてを肯定する」と言わんばかりのありったけの力強い音楽をそこにぶつけていく。
神を信じようとして信じ切れず、最後の最後にはそんな自分さえ信じ切れないマーラーと一緒に泣くのではなく、あなたをすべて肯定するという指揮によってマーラーに応えようとしたインバルのその指揮に、自分はこの曲に強く琴線に触れる感銘と感動を受けた。
モリス盤のように泣けるマーラーではないが、力強く長く深い所にまで心に響く、そしてすべてが救われたようなマーラーであり、マーラーの生涯とその音楽を大団円に導くような演奏だった。
そのせいかこの最後の最後にあるグリッサンドの前あたりから終結部まで、まるでRシュトラウスの「英雄の生涯」の「英雄の隠遁と完成」の終結部とどこか重なるようにもこの日の演奏は聴こえた。
いつもならマーラーの無常を嘆く深いため息のように聴こえてしまうのですが。
とにかく作品を通し作曲家を肯定し尽くすと、ここまでいろいろと見える風景が変わるのかと、本当にいろいろと考えさせられるじつに見事な凄い演奏だった。
演奏終了後、水を打ったように会場は静まり返る。
インバルはそんな中思ったより早く棒を下ろし構えを解いたようにみえたけど、客席の方が一瞬それでも拍手するのを躊躇ったように感じられたのは、この演奏のそれを誰もが強く感じとっていたのだろう。
こういうタイプの感銘を受ける素晴らしいマーラーを、今後自分は聴く機会があるのだろうか。
そんなことを思わず考えてしまうインバルのこの日のマーラーだった。
因みに演奏時間。
都響側は当初74分と推測されていたようだけど実際は80分近い演奏時間となっていた。
最後に。
そして都響も凄い!
以上で〆
久石譲指揮新日本フィルハーモニー交響楽団を聴く(2/16) [演奏会いろいろ]

2024年2月16日(金)
すみだトリフォニーホール 14:00開演
曲目:
J.S.バッハ : 管弦楽組曲第3番より第2曲「アリア」 (献奏)
久石譲:I Want to Talk to You - for string quartet, percussion and strings –
(vn: 崔文洙、ビルマン聡平、va: 中恵菜、vc: 向井航)
モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」
ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」
新日本フィルハーモニー交響楽団 桂冠名誉指揮者である小澤征爾氏がこの演奏会の十日前にお亡くなりになられた。
このため演奏会の最初にバッハのG線上のアリアが久石さんの指揮で献奏された。
事前に団員登場時の拍手は今回ご遠慮願いますという場内アナウンス。その後指揮者の久石さんか登場し小澤さん追悼の為献奏を行うが拍手はせずにしてほしいとマイクを通し場内に伝えられた。
そしてG線上のアリアが演奏。
それは淡々とした早めのテンポで瑞々しく、心地よいほどの軽快なピッツィカートも印象に残る清澄な響きの演奏だった。
この演奏後しばらくの間長い沈黙が続く。
場内が小澤さん追悼の深い祈りに包まれた後、一度指揮者と一部団員が退場。
その後舞台の準備を整えた後、あらためて一曲目演奏を行うための団員(献奏に出ていなかった団員の方々)とソロの四人、そして指揮者の久石さんが拍手に迎えられあらためて登場。
こうして演奏された一曲目。
四人のソロが各々自分の担当に該当するパートの前に立つという(チェロのみ協奏曲のように台の上で座っての演奏)編成。
今回演奏された久石さんの曲は2021年3月に初演された弦楽四重奏と弦楽合奏、それに打楽器を加えた曲で、全体を久石さんのベースであるミニマルミュージックで描かれている。
この曲が演奏された時、自分は小澤さんがお亡くなりになった日の、雪が積もり曇天と冷たい空に覆われた東京のあの日をなぜか思い出してしまった。これはこの曲の雰囲気だけでなく、献奏において自分の中に生じた気持ちが尾を引いていたのかもしれないが、聴いていてちょっと個人的にはしんみりとしてしまった。
途中ちょっとジブリ系の雰囲気をもった音楽が聴こえたりしてなかなか楽しめ、そしてどこか心に染みる曲でした。
続いてモーツァルト。
こちらは冒頭から引き締まり颯爽した音楽が素晴らしい。特に低音弦の威力がなかなかで、全体的にはちょっとアーノンクールとRCOの録音を思い出してしまうような演奏だったけど、演奏側のせいなのか聴き手側の自分のせいなのかは分からないが、最初の二つの楽章が前述した最初の二つの曲の雰囲気を気持ちが引きずってるように聴こえ、なんか今一つ気持ちが乗らないまま目の前を通りすぎていくような感じに聴こえてしまった。
ただ第三楽章以降、曲想のせいもあったのかもしれないけど、一気に吹っ切れたかのように音楽に勢いがつき、素晴らしく活気と推進力に富んだ演奏となっていった。ただこのあたり先鋭さより温かさのようなものの方がより強く出ていて、アーノンクールよりもワルターとNYPOやエルネスト・ブールあたりの演奏に近いように聴こえたのが面白かった。特に終楽章は秀逸。
尚、この日のオケの弦配置は、第一Vn、Va、Vc、第二Vn、Cb、という変則的な対抗配置だったが、ヴィオラが客席側に向いているせいか、中音域が豊かに聴こえていたように感じられた。
このあと二十分の休憩後、後半のストラヴィンスキー。
これがなかなかだった。
決して熱狂的だったり野性的だったりという煽情的な要素を前面に押し出したような感じではなく、全体をとてもクリアかつ見通し良く、それこそハイドンの交響曲のような確かな寸法と設計を施しているようにさえ感じられるほど、すべての音がしつに整然かつバランス良く聴こえてくる演奏だった。それはまさに「音そのもの」で勝負する演奏というべきか。
特に印象深かったのは、そのことでストラヴィンスキーがこの曲の随所に施した、ひとつの音型を執拗なまでに繰り返すという手法がかなり明確に聴きとれたこと。それは強調は繰り返すことで生まれるということを実践しているかのようにも感じられるし、また「春の祭典」初演から半世紀後に姿をみせる、久石さんの音楽のベースにもなっている「ミニマルミュージック」の先触れのようにすら感じられた。
これを久石さんが狙っていたかどうかは不明だけど、そのためかときおりスティーブ・ライヒの「18人の音楽家のための音楽」がイメージ的に何となく重なってしまうときもあり、今までにない感覚をとにかく聴いていて味わった。
この時、「春の祭典」初演から半世紀以上経った時期に録音された、ブーレーズ指揮クリーヴランド盤(旧盤)とメータ指揮ロサンゼルスフィル盤が発売当時じつに新鮮かつ大きな話題になった事を思い出した。
たしかにあそこまである種のインパクトの強い演奏ではないけど、初演から百年以上経ったにもかかわらずまるで古さを微塵も感じさせない、それはまるで古き時代の文化財をものの見事にリフレッシュさせたかのようなこの演奏に、ブーレーズやメータのそれと同じようなものを感じた。しかもそれでいてブーレーズやメータにはあまり感じられなかったどこか原点回帰的なものも感じさせるところもあるという、とにかく今までになくとても新鮮な演奏だった。
またこの演奏、確かに迫力や刺激、そしてそこからくる原始性にはそれほど重きは置いていないけど、すべての音がとにかくバランス良くクリアなことで、この曲のもつ巨大な情報量が一気に開陳されたかのような感じとなり、この曲のスケールの大きさをあらためて強く認識させられる演奏になっていた。
そういう意味では1986年にヘルベルト・ケーゲルが東フィルを指揮した同曲と似た方向性を感じさせられるが、今回の久石さんの方がよりクリアさに秀でていたように感じられた。(ケーゲルはケーゲルで、巨岩が目の前をゴロゴロと転がっていくような圧倒感を感じさせられましたが)
なので第二部最後の「生贄の踊り」における打楽器の強打や金管の咆哮も、曲の巨大性と膨大な熱量を余すことなく伝える事に徹したようなものとなっていた。
音楽は最後も見事に決まったが、そのせいか聴衆の反応も熱狂的というより感心し感銘を受けたというものに感じられた。
残念なことにこの日の演奏は収録等がされていなかったが、そのあたりも含めもう一度聴きかえし、いろいろと確認してみたいと強く思わせる演奏だった。
因みにこのコンビは秋にドヴォルザークとブラームスという超スタンダード、来年にはメシアンの大曲と、かなりふり幅の大きなプロが予定されている。今回の演奏を聴くとはたしてそれらはどのような演奏になるのだろうか。とても興味深いものがあります。
以上で〆。
※この日は満員御礼だったけど、一部空席、しかも一部には隣の人がその空席に荷物を置いてる座席もあった。
空席待ちの長蛇の列が開演前にあったことを思うと、しかたないのかもしれないけどこれには「なんとかならんか」という気持ちになった。
「荷物に曲聴かせるくらいなら並んでる人に聴かせてあげてよ」と思ったのははたして自分だけだろうか。
これだけは何とも残念な光景でした。
高関健指揮富士山静岡交響楽団を聴く(2/6) [演奏会いろいろ]

2024年2月6日(火)
東京オペラシティコンサートホール 19:00開演
曲目:
ブルックナー/交響曲 第8番 ハ短調 (ハース校訂による原典版)
「2020年11月、いずれもNPO法人であった静岡交響楽団(創立1988年)と浜松フィルハーモニー管弦楽団(創立1998年)が合体し、2021年4月より一般財団法人「富士山静岡交響楽団」として県下全域に密着した演奏活動を継続、2022年4月より公益財団法人の認可を受け、財政基盤の強化と更なる演奏力の向上に向けて大きく前進を続けている」
今回聴いたオケの公式サイトにある楽団紹介の一部をあげたけど、この富士山静岡交響楽団は静岡県内唯一の常設プロオーケストラ。
ただ神奈川のお隣のオケということなのに自分は一度もこのオケを聴いた事がない。指揮の高関さんも実演は今回が初めてということで、結構前からじつはかなり楽しみにしていた演奏会でした。
開演5分前に高関さんから今回の演奏についてのいくつかこの曲に対する考えがプレトークで述べられた。
高関さんに言わせるとブルックナーの交響曲のいくつかには、作曲家本人の意思だけでなく弟子たちの少しでも多くの人達に「受ける」ようにしようという「善意」からきた強い意見が反映されたものがあるという。しかもそこには原典版といわれているものにも存在している。
今回演奏される第8交響曲もそのひとつで、1887年の第一稿こそ作曲者がすべてを書き上げたものの1890年の第二稿、つまり最近一般的に演奏されているノヴァーク版(第二稿)やハース版は、完成までに弟子たちの意見によりかなり手が入り、第四楽章に至っては形的に「完成」こそしているものの、内容的には自分の考えと弟子たちの意見が混然一体となり、そこに何の解決も見出さぬままの「未完成」状態であるという。
今回の演奏はそれらのことを踏まえてハース版を基にしているものの、ブルックナー以外の手による部分を極力排除し、ブルックナー自身のそれに近づけようという試みがあるという。
自分はこれを聞いた時、この日の演奏のテーマはブルックナーに対し「あなたの本音はどこにあるのか」ということを曲から聞き出すことのように感じた。
おかしな例えかもしれないが、それはシャーロック・ホームズや金田一耕助のような名探偵が、目の前にある多くのヒントからいかに事の真実に辿り着くかという、その推理と考察にひじょうに似ているように感じられた。
そうなると学究的なものに固執するというより、事実という多くの点と点を理論と感覚と経験をもとに結び付けていくことで、ひとつのドラマに仕上げていくという作業に近いものになるような気がしたのですがはたして。
結論からいうとひじょうに熱量の高く、劇的で強いブルックナーだった。
そういうとかつての飯守泰次郎さんのそれを想起させるけど、あれほど厳しいタッチで強烈に描いたという感はなく、金管などはかなりの咆哮を要求してはいるが、それ以外は鋭角的だったり刺激的だったりという響きはあまり感じられず、むしろ腰を据えた打っても叩いてもびくともしない安定感と音の厚みの方が強く印象に残る音作りになっていた。
また音の厚みというけど、重厚さとはまた違った趣で、第三楽章の冒頭など弦楽四重奏的ともいえる、線的な響きを軸とした横の流れの平行的ともいえる美しさが異常なほど印象に残ったりするところもあった。
プレトークでの高関さんの言葉にもあったように、確かにブルックナー以外の手の入った音にいろいろ施した結果、聴きなれない音や無くなった音などがいろいろとあったように聴こえたけど、聴いているとそんなことよりも、上にあげた音楽そのものの印象の方がより強く感じられるものとなっていた。
特にそれは後半二つの楽章により顕著にあらわれていたような気がする。
じつはこの日。第二楽章終了後オケがチューニングをし、その後第三楽章へという段取りだったのですが、何故かチューニングが終わっているタイミングで、一階席前方から後方扉に向かって退席する女性の方がいた。しかもその靴の音がなかなかしっかりとホール内に(決して大きな音ではなかったけど)が響いていたため指揮が始められない状況がおきた。
これは後半どう影響するのだろうかと危惧したが、むしろそれで火が付いたかのようにより集中度の高い音楽が鳴り響いた。
その第三楽章はヨッフムやチェリビダッケあたりの指揮だと神の声が天から降りてくるような趣になるけど、高関さんの場合は天に向かってブルックナーが渾身の祈りを捧げているような趣だった。
このため宗教性が後退したように感じられたかもしれないけど、モーツァルトのレクイエムやベートーヴェンのミサのような演奏会用宗教音楽的劇性がその分強く投影されたように感じられた。ムラヴィンスキーの同曲の録音における第三楽章でも似たような印象を受けたことをこのときふと思い出したが、そういえばあれもハース版だった。
終楽章も前のめりにならない怒涛の演奏という感じで、煽情的ではないものの、音の流れの強靭さのようなものがとにかく全面に出た演奏で、終演後間髪入れず拍手が起きたのも、ふつうなら余韻を楽しみたいだけに嫌な気持になるところ、この日は「もうこれはしかたない」と、ちょっと納得してしまうほど音楽が聴き手を強く巻き込む類の圧倒的な音楽がそこにはありました。
このため終演後はかなり熱狂的な反応が会場から湧き上がりましたが、これは指揮の高関さんだけでなくオケに対しても当然ありました。
この日初めて聴いた富士山静岡響。編成は14~12型の中間くらいでしたがオケのパワー、特に管楽器がなかなか強力で、ホール内にかなりの音響を形成していました。また弦楽器も表情豊かな音楽を奏でていて、第三楽章のシンバルが鳴る前後の強い思いの丈を感じさせる音楽には強い感銘を受けました。
それにしても四日間でブルックナーの大曲を三カ所三公演というのはなかなか凄いです。ただたいへんだったかもしけませんが、最終日のこの日はそれまで練習と二回の本番で、しっかり練り込まれた見事な演奏で高関さんの指揮に応えていたと思います。
またいつか機会があったら聴いてみたいオケです。
因みにこの日コンサートマスターは、ゲストソロコンマスの藤原浜雄さん。
最後に。
終演後何故かハース版を聴いたにもかかわらず、どこか作曲者自身の手でつくられた初稿版のような感覚がどこか付きまとう、それこそ初稿と二稿の間の、1.75稿みたいな感じが今でもずっとしています。
ブルックナーの音楽は弟子の手を離れれば離れるほど、今日のようにより思いの丈が前へ前へと出てくる熱いものなのかもしれませんし、そこには作曲家ブルックナーだけでなく、オルガンの即興演奏の大家として聴衆を熱狂させた、演奏者ブルックナーの奔放かつ狂熱的な姿がより明確に浮かび上がってくるのかもしれません。
逆に言えば弟子たちのそれはブルックナーのそれをより一般受けさせるために、ワーグナー的な聴きやすさ、もしくは耳の心地よさを織り込んだものといえるのかもしれませんが。これれはあくまでも自分の感覚的な物言いです。
そういう意味でも、とても貴重な体験もできた演奏会でした。
以上で〆
※追加
指揮の高関さん。
なんというのかひじょうにしっかりと音楽を計算し設計しているという印象を受けたのと同時に、熱狂のようなものもある程度計算してつくりだしているような感じを受けました。
もっともそれはスコアを読みつくせばそうなるということの表れともいえるかもしれませんが、そういう意味ではカラヤンやメンゲルベルクとちょっと近しい部分も感じられました。
近々演奏されるマーラーや「幻想交響曲」そして「英雄」やバルトークのオケコンもそれを思うとなかなかの聴きものになるような気がします。